お昼寝は食事や遊びと同様、乳幼児の成長に欠かせない行動の一つです。
お昼寝をすることで様々な能力や機能が発達していきます。
質の良いお昼寝をするにはどうしたら良いのでしょう。
お昼寝について考えてみましょう。
お昼寝の必要性とは?
大人と比べて体や脳が未発達な子どもにとって、昼寝は健康に生活し、心身を発達させるうえでとても大切なものです。
寝ている間には免疫力を向上させたり成長を助けたりするメラトニンというホルモンが分泌され、体の疲れを癒したり緊張を緩めたりする働きをします。乳幼児期は、このメラトニンがたくさん分泌されるので、心身の成長のためにも昼寝は欠かせないものといえます。
また、昼寝をしないとご機嫌が悪くなったり、疲れがとれず体調に影響が出たりすることがあります。日中に適度な睡眠をとることで、子どもの生活リズムは整えられていくのです。
年齢別 お昼寝の時間の目安
ではお昼寝は何歳ごろまで必要なのでしょうか。
もちろんお子様によって個人差があります。そして眠りの深いお子様と敏感に音や光に反応してすぐに目が覚めてしまうお子様もいますが、おおよその時間を見てみましょう。
- 0~2ヶ月
1日で合計16~20時間程度の睡眠時間が必要です。昼夜に関係なく寝たり起きたりを繰り返します。1~2時間起きていて1~4時間寝るというパターンで睡眠をとりますが徐々にまとめて寝るようになってきます。
- 3~5ヶ月
1日平均14~15時間程度の睡眠時間をとる時期です。夜眠る時間が長くなり、昼寝のとり方は午前中1時間、午後の早い時間帯に2時間程度と夕方ごろに30分~1時間程度に変化していきます。
- 6~12ヶ月
この頃になると、日中に起きている時間はだいぶ長くなっていきます。1日に必要な睡眠時間は合計で12~15時間ほどです。午前と午後に1回ずつ1~2時間程度昼寝をすることで、機嫌よく過ごせるようになります。
- 1~2歳
1日1時間程度眠れば大丈夫な子も増えてくる年齢で、多くの子どもは1日1回の昼寝で過ごせるようになります。
- 3歳以上
3歳を過ぎると昼寝をしなくても1日過ごせるお子様も増えてきます。5歳頃には多くのお子様が昼寝をしなくなります。ただし個人差があるため、厳格に年齢で決める必要はありません。また、疲れている時や緊張する場面が多かった日などは昼寝をしたくなることもあるでしょう。
スムーズに眠れるための環境づくり

ナニーはお子様が寝やすい環境を整えて、昼寝の質を向上させるよう心がけています。ミルクや昼食など、お腹が満たされているかも確認もしましょう。
①眠くなってきたサインを見逃さないようにしましょう
お子様の様子をよく見てください。いつもと違う小さな変化が出てきていませんか。
<乳児>
目をこする→
眠くなると涙腺の働きが弱くなり、瞬きの回数が少なくなり、目が乾燥します。
手足が熱い→
身体が眠りに入る準備です。
手足に血流を集中させて身体の内部の温度を下げています。
耳を触る→
自分の耳を、触る事によって安心感を得ています。
顔を擦りつける→
こちらも耳同様に安心感を得ています。
ナニーは抱っこの際、お子様のお肌を傷つけないよう、装飾のない洋服を身に着けてお世話をしています。
あくび→
赤ちゃんにとってあくびは疲れすぎているサインです。あくびが出る前から寝かしつけがベストです。
寝ぐずり泣き→
生後4ヶ月以降から徐々に落ち着きます。
<幼児>
午前中お外遊びをしてから昼食後は静かに過ごせる室内遊びをします。
ゴロゴロし始めたり、機嫌が悪くなってきたらお昼寝が必要なサインです。
イヤイヤ期のお子様は会話に「イヤ‼︎」の回数が増えてきます。
②サインをみつけたらナニーがすること
カーテンを閉めるなど部屋を暗く→
真っ暗にすると、お子様の呼吸確認や表情を見ることが出来ません。薄暗い程度の明るさにしましょう。
外の音が聞こえないよう静かな環境づくり→
可能であればインターホンも無音に出来るとよいでしょう。
室温を整える→
夏 26℃~28℃
冬 20℃~23℃を目安に調整。
私はナニーのお仕事に入る際いつも携帯用の温度、湿度計を持参しております。
入眠時は常に確認が必要です。
お子様が落ち着いて眠れる工夫→
乳幼児は手足が冷えると眠りにくくなります。夏でも足元はタオルケットをかけたり、足マッサージをするとスムーズに入眠できます。
声は小さめで、入眠に導くような絵本の読み聞かせ→
いろいろな絵本を読むよりも、一冊の絵本をゆっくり繰り返し読む方が眠りやすいようです。
ハミングでお歌→
“ゆりかごの歌”、”きらきらぼし”など静かめの曲を選びましょう。
③抱っこからお布団に降ろす時の注意点
抱っこで寝かしつけてもベッドに降ろすと泣いてしまうお子様も多いです。
なぜ泣いてしまうのでしょう?
それは抱っこが子宮の環境(体を丸め、包まれた状態)に近いためだそうです。
抱っこから布団に移動すると背中に感じる温度に差があるため、目が覚めてしまいます。しっかり深く眠った事を確認する事が大切です。
布団に降ろす時はお尻から布団につけます。
先にお尻側の手を外し、お腹の上に置きます。
背中側の手を挟んで、その状態をキープ。
ここで焦らず様子を見て起きそうもなければ背中の手をゆっくり外します。
頭は最後です。優しく手を握っても安心します。
④入眠中に注意すること
お子様の呼吸チェック→
うつぶせ寝による呼吸停止を防ぐためにナニーは胸に手を当てて5分に一度の呼吸チェックを行います。ご家庭でもお子様に変化がないかよく観察してあげてください。
熟睡できているか確認→
バンザイ寝とは両手を挙げてバンザイのポーズをしていることです。これはリラックスして寝ている証拠です。
バンザイによって体温調整をする役目もあります。
新生児から1歳でやめる子どももいれば3歳過ぎてもバンザイして寝る子どももいるので、個人差があります。
⑤明らかに睡眠時間が足りないのにお目覚めになりそうな場合
声をかけずに見守る→
寝言や目を開けてお話しするお子様もいますが
過剰に反応せず、うなずいたりして静かに見守りましょう。
お腹を優しくトントン→
一定のリズムでゆっくりと
寝相が悪くて敷布団から、はみ出して目覚めるお子様への対処→
声をかけずに素早くお布団へ戻し、トントンで見守り環境を整える
起きてしまった‼︎と焦らない→
ゆったりとした気持ちで寝かしつけをしないとお子様に伝わります。
睡眠時間が足りないと、お目覚め後にゴロゴロした状態が長く続いたり、ご機嫌が悪くなったりします。お子様に合った時間を確保出来るように心がけましょう。
まとめ
お昼寝の大切さとコツを理解出来たでしょうか。
ナニーでご家庭にお伺いした時に、よくお母様から
“お昼寝の時は外にベビーカーで連れていかないと眠れないです。”
“抱っこ紐で寝かせています。”
と言われますが
“今日はお布団で眠れました。”
と、ご報告すると、どうやって寝かしつけしたのか驚かれます。
それはお伝えしてまいりましたコツを覚えれば、ほとんどのお子様はお布団でも入眠出来ます。
大切なことはお子様の様子を観察して判断するタイミングとお子様に対する愛情です。
ゆったりとした気持ちで、ぜひ一度お試しください。

この記事を書いた人
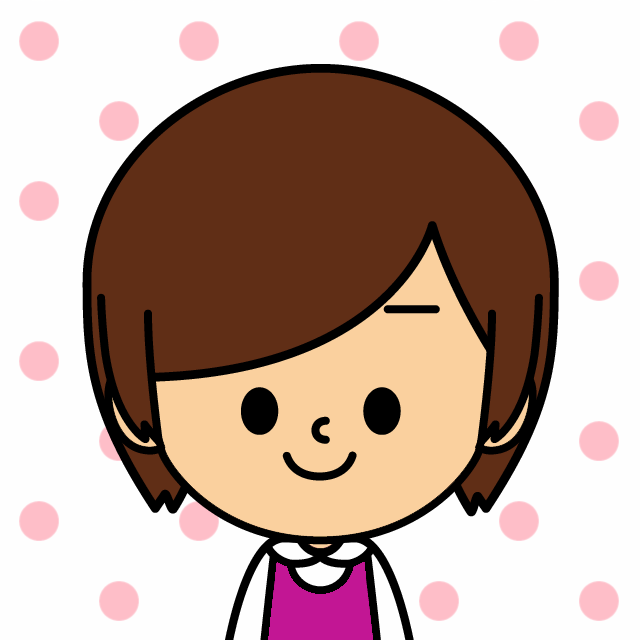
- ハタノケイコ
- 大学にて幼児教育を学び幼稚園教諭ニ種取得。 卒業後は大手百貨店に就職し接客について学ぶ。 児童館での読み聞かせボランティアをきっかけに再び保育の仕事へ。 40代でポピンズに入社し様々な保育現場で仕事をしながら保育士資格取得。 10年の経験と自身の子育てから感じた事を記事に書いて発信中。



 前の記事
前の記事 次の記事
次の記事

