日本は地震や台風などの自然災害が頻繁に起こる国です。また、災害はいつ、どこで起こるかわかりません。そのため、いざという時に備えて防災グッズを準備することが大切です。今回は看護師ナニーとしての視点から、お子様の安全と健康を守るために必要な防災グッズ選び方や必要なアイテムを紹介していきます。この記事を参考に、ご家庭の防災グッズを見直し、万が一の場合安心して過ごせる準備を整えましょう。
contents
基本のもの:食料と飲料水など
災害時に最も重要なのは食料と飲料水です、特にお子様は大人よりも体力が少なく、食事や水分の摂取が健康状態に大きく影響をします。看護師として、栄養バランスを考慮した備蓄品を提案します。
飲料水
飲料用と調理用合わせて1人あたり1日3リットルが災害時には必要です。ライフラインが断絶されてから支援が届くまでの量、少なくとも3日分、可能であれば一週間分の水を備蓄しましょう。保存スペースの問題がある場合は、長期保存水の購入を検討してみてください。
栄養バランスを考えた食料
長期保存が可能な栄養スティックや乾パン、缶詰などを備えておきましょう。特にお子様には、普段慣れ親しんでいる食事を用意することが大切です。
被災時の不安定な状態を和らげるために、いつも食べているものを口にすることで安心感が生まれます。
また、常備食は普段から試食をし、味に慣れておくことが、いざとなった場面で大切になります。毎日の生活の中で、家族みんなで常備食を試食をし、美味しいと思えるものをストックするようにしましょう。
・乾パン
・レトルト食品(ご飯やお粥、アルファ米など)
・缶詰
・インスタントラーメン、インスタント味噌汁
・チョコレートや飴、羊羹
液体ミルク
液体ミルクは即戦力となるため、災害時に特におすすめです。避難生活では母体にもストレスがかかり、一時的に母乳の分泌量が減ることがあります。液体ミルクならば、飲料水の確保や哺乳瓶の衛生管理の心配も少なく、安全に使用できる利点があります。また、避難所での授乳は、安全面からも液体ミルクを使用する方が安全だと感じるお母様も多いという点にあります。
常温保存が可能ですが、直射日光と高温な場所での保存は避けましょう。乳幼児は1回あたり200ml、1日5回が飲料の目安となっています。必要に応じた量を概算して用意しましょう。また、複数のメーカーから、用途に合わせた商品が出ているので、普段の生活の中で試し、お子様にあったものを見つけてみてください。
アレルギー対応食
災害時の炊き出しで、アレルギー対応食を出してもらうのは困難なため、必要な食品を備蓄しておくことが重要です。防災グッズの購入を検討する際、成分表示を確認しながら購入し、備蓄をしておきましょう。
医療用品と衛生用品
災害時には病院や薬局で薬を手に入れることが難しい場合があります。看護師の経験から、お子様に特化した医療用品と衛生用品を選びました。
応急処置キット
消毒液、ガーゼ、包帯、絆創膏、ピンセット、ハサミなどの基本的な処置用品を準備しましょう。絆創膏のサイズはお子様が使用しやすい小さめのものがいいです。
現在、消毒の基本は流水で傷口を洗う方法ですが、災害時は水が貴重になりますので消毒薬があるといいでしょう。また、包帯やガーゼがなくても、手ぬぐいで代用できることがあります。手拭いの用途はに汗を拭く以外にも、マスク、物を包むなど多岐に渡っています。持っていると安心なものの一つです。
常備薬とお薬手帳
急な発熱に備え、解熱剤を用意しておくと便利です。また喘息やアレルギー等の薬は少し多めにストックを持って置くことが大事です。使用期限を確認しながら用意しましょう。
お薬手帳には既往歴や副作用歴、アレルギー歴も記載しておくと処方がスムーズになります。飲むのをやめると症状が悪化する薬や、切らすと命に関わる薬を飲まれている方は、複数の媒体で自身の健康に関する情報を管理しておくといざという時に安心です。
また、マイナンバーカードを保険証がわりに使用している場合は、そちらで情報の管理がされているので、そのデータを照合しながら処方は可能ですが、もし、災害時に手元になかったり、マイナンバーカードを使用していない場合はお薬手帳を防災グッズとして持っていると、薬局で処方をしてもらうことが可能です。
衛生用品
お子様用のオムツ、ウエットティッシュ、お子様用のトイレシートなど、衛生管理に必要なものを用意しましょう。災害時には水が貴重になりますので、多めの紙おむつを備蓄していると良いでしょう。
また、避難所での生活では生理用品の供給が間に合わないことがあります。防災グッズの中に、最低でも一回の周期分の量を入れておくと安心できるでしょう。
その他にも、避難所生活では感染症発生のリスクが高くなります。アルコール消毒液やマスクを備蓄しましょう。
メガネやコンタクト
過去の震災においても、自分が普段着用しているメガネやコンタクトと同じ度数のものを手に入れることが難しいと言われてきました。予備があれば安心です。
お子様の安心を保つアイテム
災害時にはお子様が不安やストレスを感じやすいです。避難所生活では最初は毎日の生活と異なる環境ということもあり、楽しく感じるお子様もいらっしゃいますが、次第に不安が強くなり、心を閉ざしてしまうことがあります。そうならないためにも大事なことは、普段と変わらない生活をさせてあげることです。そのため、お気に入りのおもちゃや絵本、ブランケットやぬいぐるみを防災バッグに入れておきましょう。
お子様でも使用できる防災グッズ
ホイッスル(防災笛)
お子様が使いやすい大きさのホイッスルを用意しておきましょう。もし瓦礫の下などに挟まった場合など、自らの居場所を伝えるための命綱になります。災害時には声が届かないこともあるため、音を出して助けを求めるための道具です。首にかけられるタイプが便利です。
ヘッドライト
お子様が自分で装着できる軽量なヘッドライトを用意します。暗闇でも両手が使えるため、避難時に役に立ちます。電池の予備も忘れずに用意をしましょう。また、万が一の時にすぐに使用ができるように、日頃より使い方の練習をしておきましょう。
簡易トイレ
お子様用の簡易トイレも防災バッグに入れておきましょう。災害時はトイレの利用が困難になることがあります。
ご家族に関する情報のためのもの:身元や連絡先の書かれてあるメモ
いざご家族に連絡を取ろうと試みても、災害発生時には携帯電話が使えないことなどがあります。東日本大震災が発生したときはしばらく携帯電話による連絡ができず、公衆電話に人々が殺到しました。よって、メモにご家族の連絡先を書いたものを持ち歩くことがおすすめです。
定期的な見直しと訓練をしましょう

防災グッズを用意したけれど、いざとなったら使用期限が切れていたり、使用方法に困るものもあります。定期的に防災バッグの中身を確認し、更新していきましょう。家族全員で使用方法の確認を定期的に行うことで日頃の防災意識を高めることにもなります。
まとめ
災害に備えるためには、ご家庭での防災グッズの準備が必要不可欠です。看護師ナニーの視点から、お子様を守るための具体的なアイテムをリストアップしました。日頃から備えておくことで、万が一の時にも家族全員が安心して過ごせる環境を作ることができるのです。

この記事を書いた人
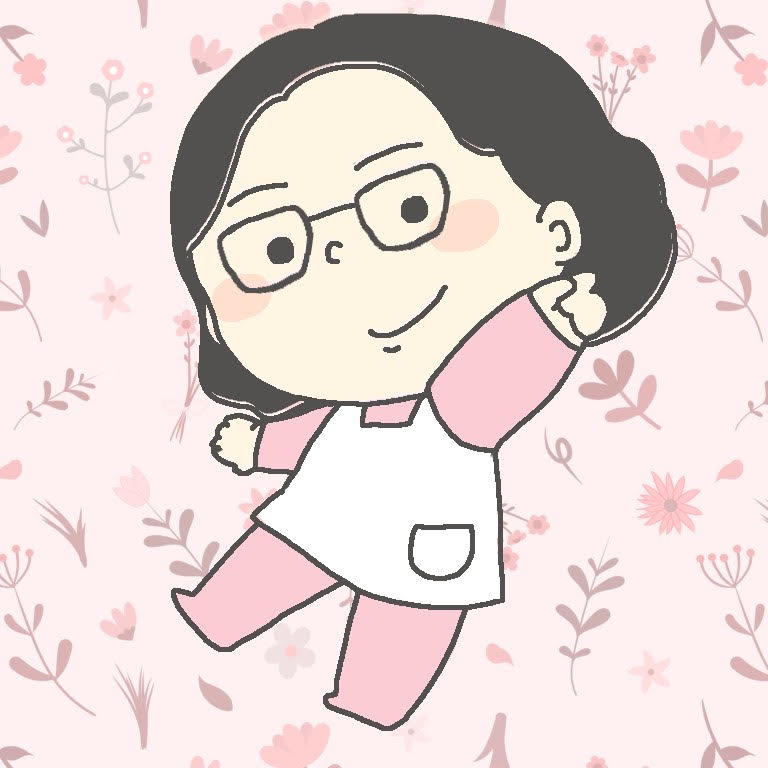
- Naoka
- 看護師、保育士、養護教諭の資格を持つナニーとして活動しています。これまで保育園や小学校、放課後デイサービスなど、さまざまな現場で経験を積んできました。現在ナニーのお仕事をしながら、療育施設にて自閉症スペクトラム症のお子さまたちの支援に取り組んでいます。



 前の記事
前の記事 次の記事
次の記事

