「宿題をやりなさい!」と声をかけても、なかなか進まない…。子どもを見守るパパママにとっては、日々のストレスになることもありますよね。「何とかしたいけれど、どう声をかけたらいいのかわからない」と悩む方も多いのではないでしょうか。
今回の記事では、子どもの発達段階に応じた具体的な方法を紹介しながら、親として子どもの学びをどう支えるかについて考えます。発達特性の有無を問わず、すべての子どもに効果的な工夫のご紹介です。
看護師ナニーとして多くの親子をサポートしてきた経験をもとに、子どもが「やってみたい」と思える環境づくりについて、一緒に考えていきましょう。
contents
なぜ宿題が進まないの?考えられる要因
宿題が進まない理由には、子どもの年齢や特性、家庭環境、心理的な要因など、さまざまな背景があります。一つ一つの原因に目を向けることで、解決へのヒントが見つかるかもしれません。
1.環境の影響
- 集中を妨げるものが周りにある
宿題をする場所にテレビやおもちゃ、ゲーム機があると、気が散りやすくなります。また、兄弟姉妹が近くで遊んでいると、そちらに意識が向いてしまうことも。
- 時間管理の難しさ
時計やタイマーがない環境では、「いつ終わるのかわからない」「ダラダラと時間が過ぎてしまう」という状況になりがちです。
2.子どもの発達段階による影響
- 就学前~低学年の子ども(5~8歳)
時間の感覚が未熟で、「今すぐやる」という行動を理解するのが難しい時期です。「さっと終わらせれば楽になる」という大人の考えが伝わらないことも。
- 高学年の子ども(9~12歳)
この時期は計画を立てる力が発達し始めますが、まだサポートが必要です。「どうすれば効率よく進むか」を一緒に考えることで、少しずつ自分で進める力が育ちます。
3. 疲れや心理的負担
・身体的な疲れ
学校や習い事でエネルギーを使い切り、宿題まで力が残らないことがあります。
・宿題への苦手意識
「宿題はつまらない」「怒られないようにやるもの」と思っていると、取り組む気持ちが低下します。
4.発達特性による影響
発達特性を持つお子さんの場合、以下のような理由で宿題が難しく感じることがあります。
・ワーキングメモリの弱さ
一時的に情報を保持して操作する力が弱いため、「何をするか忘れてしまう」「やり方がわからない」となる場合があります。
・見通し力の弱さ
タスクのゴールが見えず、不安な気持ちでいっぱいになる子どもがいます。そのため、やり始めるのが難しいことも。
これらの理由により、子どもが宿題に取り組めず、親御さんも心が疲れてしまうことがあります。さらにこのような状態が続くことで、本人が自信を失い、悪循環が生まれてしまうこともあるでしょう。ですが、こうした状況は工夫次第で大きく変えられるのです。
子どもが宿題に前向きに取り組むための5つの工夫
学校が毎日宿題を出す理由はなんでしょうか?
- 反復学習
- 学習内容と習慣の定着
- 自己管理をする力を育てる
など様々な理由が挙げられます。宿題は特に3番目の「自己管理能力」を高めるいい練習になります。
少しの工夫で、子どもが「やりたい」と思えるようになります。以下の方法をぜひ試してみてください。
視覚ツールで時間を意識
子どもが宿題を終わらせたときに「やった!」と実感できる環境を作りましょう。例えば、スケジュールボードに「宿題→おやつ→遊び」といった予定を書き込むことで、次の楽しみが見える化されます。毎日コツコツと成功体験を積むことは、子どもの自信へとつながり、宿題が習慣化するきっかけとなります。
<ポイント>
- タイマーや砂時計を使い、時間の流れを視覚化する。時間の感覚を育てることも可能です。
- 達成感を味わえるよう、宿題が終わったらシールを貼るなど、小さな成功体験を積ませる。
集中できる環境を整える
- 宿題専用のスペースを用意する
テレビやおもちゃなど、気が散るものが目に入らない場所を選びます。なるべく帰宅してすぐ取り組むことで、その後の時間をゆっくりと過ごすことができるでしょう。
- 必要な道具を揃える
「何をすればいいのか」がすぐにわかる環境を作りましょう。
小さな成功体験を積ませる
- 宿題を細かいタスクに分け、「今日はここまで」と達成しやすい目標を立てます。
- 終わったときには、「頑張ったね」「上手にできたね」と言葉で褒め、自信を育てます。
自主性を尊重する
- 子どもに「どれからやりたい?」と選択肢を与え、主体的に取り組める工夫をします。
- 「10分だけ頑張ってみよう」と時間を区切り、達成したら褒めることで、次の取り組みへの意欲が生まれます。
宿題後の楽しみを設定する
- 「宿題が終わったら一緒に遊ぼう」「好きなおやつを食べよう」など、楽しみを用意します。ただし、物質的な報酬に頼りすぎないことが大切です。
宿題の前に運動を取り入れるのも効果的!

宿題の前に5~10分間の軽い運動を取り入れると、集中力や記憶力が高まる効果があります。
具体的な運動例
- ジャンプやストレッチなどの全身運動
- ダンスや散歩など、リズミカルな動き
- 親子でスキンシップ
運動をすると、脳への血流が増加し、集中力ややる気が向上します。宿題への切り替えもスムーズになるため、ぜひ取り入れてみてください。
ご褒美に頼りすぎない工夫も大切
一時的な「お菓子」や「ゲーム」よりも、「一緒に喜ぶ」「成功を共有する」ことが子どもの自発性を育てます。
報酬を与える際のポイントは、言葉での承認や、家族での楽しい時間を報酬にすること、また「やればできた!」という達成感を何より大事にすることです。
発達段階別のサポート方法
子どもの年齢に合わせた声かけや工夫を取り入れることが大切です。
就学前~低学年
- 短時間で終わるタスクに分ける。
- 「一緒にやろう!」と親も前向きに寄り添う姿勢を見せる。
- 「練習曲を3回弾く」「プリント1枚」「ドリル1ページ」と具体的に数値化した分量を伝える。
- いつもと同じ宿題のルーティンを作り、それに従って取り組んでもらう。
- 困っている様子を見せたら、タイミングを見て声をかけてあげる。全てを教えるのではなく、「ここはどうすればいいと思う?」とヒントを与えてあげることで解決をすることもある。
中学年~高学年
- 自主性を尊重し、宿題の順番を本人に決めてもらう。
- さりげなく「取り組む順番の利点」を一緒に考える。優先順位の付け方を鍛えるきっかけにする。
- 振り返りを行い、「次はどうする?」と改善を一緒に考える。
- 長期的な目標も設定できるよううながす。
おわりに

宿題が進まないことは、親子で向き合う時間を増やすチャンスとも言えます。「なぜできないのか」を一緒に考え、少しずつ前進することで、子どもは「できる」を増やしていくでしょう。あれこれ試してはみたけれど、どうしてもお子様が学習に取り組むことができず困っているようでしたら、専門家による適切な判断と介入のもと、本人にあった学習サポートを受けられるよう、一度相談をしてみることもお勧めします。
宿題を通じて、お子様と笑顔で向き合える時間が増えることを願っています。

この記事を書いた人
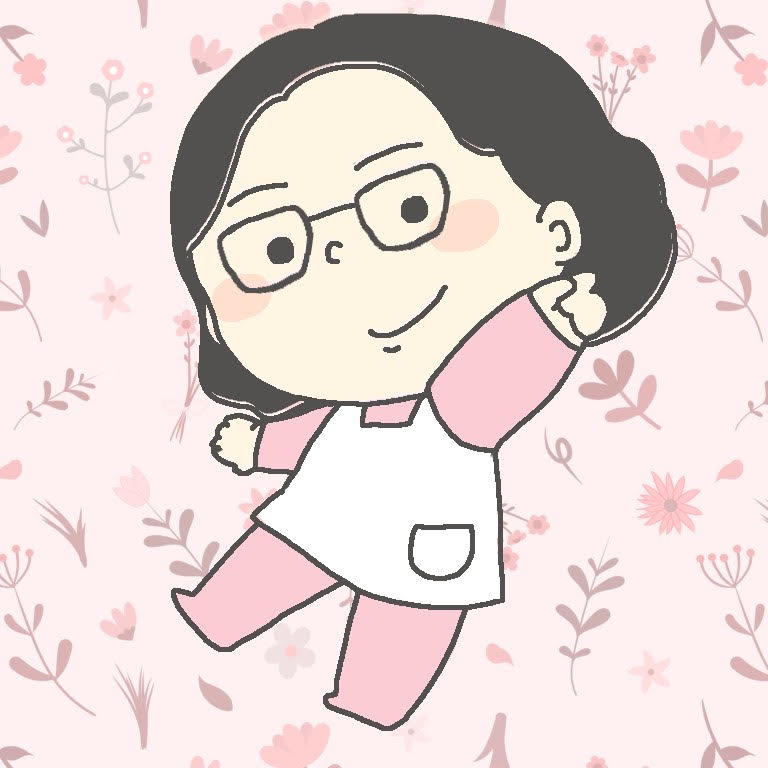
- Naoka
- 看護師、保育士、養護教諭の資格を持つナニーとして活動しています。これまで保育園や小学校、放課後デイサービスなど、さまざまな現場で経験を積んできました。現在ナニーのお仕事をしながら、療育施設にて自閉症スペクトラム症のお子さまたちの支援に取り組んでいます。



 前の記事
前の記事 次の記事
次の記事

