contents
はじめに:新生活の始まりに・・・「パパママと離れるのが辛い」のは当たり前
4月は、新生活が始まる時期。特に、小学校に入学したばかりのお子さまにとっては、幼稚園や保育園とは違う新しい環境に適応する、大きな変化のタイミングです。この時期、パパママからこんな声をよく聞きます。
「人見知りが激しくて、新しい環境に慣れるのに時間がかかる。進学してやっていけるのか心配です。」
「うちの子どもは親から離れられない。学校でちゃんと過ごせるの?」
入園・入学後も、こんな様子が見られることがあります。
- 朝になると急に「行きたくない」と言い出す
- 登校前に泣いてしまう
- 毎朝ぐずって、親もどう対応すればいいのかわからない
ナニーとしてご家庭に伺うと、こうした相談を時々お受けします。
「このままでは学校生活が大変なのでは?」と不安になりますよね。
でも、安心してください。これらの行動の背景には、「分離不安」が関係している可能性があります。
分離不安は 成長の一部として誰にでも起こり得るものですが、いざ目の前でわが子が泣き続けたり、登校を渋ったりすると、親としては「どうしてこんなに嫌がるの?」「学校が合っていないの?」と心配になってしまうもの。
でも、大丈夫です。
子どもが「親と離れるのが不安」と感じるのは、ごく自然なことです。特に、進学や進級などの環境が大きく変わるタイミングでは、一時的に分離不安が強くなることがあります。
「人見知りが強いから、この子は大丈夫?」と悩む必要はありません。多くの子どもは時間とともに適応していくもの です。
この記事では、
- 分離不安とは何か?
- パパママができるサポートとは?
- どんなときに専門機関に相談すべき?
といったポイントを詳しくお伝えします。
分離不安とは?——成長の上で当たり前のこと
分離不安とは、親(特定の愛着対象)と離れることに強い不安を感じる状態 のことです.
これは成長の過程で誰しもが経験する自然なもので、特に以下のような場面で強く現れることがあります。
- 乳幼児期(1〜2歳):「ママがいないと不安!」と泣く
- 幼児期(3〜6歳):保育園や幼稚園の登園時に泣いたり、後追いする
- 小学校入学時:新しい環境に緊張し、親と離れがたくなる
- その他:長期休み明け、ご家族の生活の変化(転職、引越し、きょうだいの誕生など)
「親と離れるのが不安」という感情は、裏を返せば親と安心できる関係を築けている証拠。不安になること自体は、決して悪いことではないのです。
また、お子さまの「朝になるとお腹が痛い」「玄関で泣いて動かない」などの行動は、決してわがままではなく、不安の表れです。
進学や環境の変化で分離不安が強くなる理由
進学や進級などのタイミングでは、分離不安が一時的に強くなることがあります。これは、子どもにとって 「親と離れること」+「新しい環境に慣れること」というダブルの負担がかかることが主な原因です。
特に、人見知りが強い子ども、環境の変化に敏感な子どもは、不安が大きくなりやすいです。
でも、安心してください。新しい環境に馴染むのに時間がかかる子どもでも、慣れる時間を十分にとりながら、少しずつ適応していくものです。
「私たちの育て方のせい?」——原因探しをしなくて大丈夫です
「うちの子、人見知りが激しいのは私のせい?」
「もっと友達と遊ばせるべきだった?」
「もしかして発達に何かがあるの?」
分離不安が強いと、ご家族はつい「自分のせいかもしれない」と責めてしまいます。
しかし、基本的にこれは「性格」の範囲であり、ご家族の育て方の問題ではありません。
もちろん、発達特性として極端な不安の強さを持つ場合もありますが、大半のケースでは、成長とともに落ち着くものなので、必要以上に心配しなくて大丈夫です。
分離不安を和らげるためにパパママができること

まずは、お子さまの気持ちを受け止める
「行きたくない」と言われると、つい「そんなこと言わずに行きなさい!」と言いたくなるかもしれません。しかし、子どもが不安を感じているときに、無理やり行かせようとすると逆効果になることもあります。
→ 学校に行くのが不安なんだね
→ ママと離れるのが寂しいんだね
と、まずは気持ちを受け止めて共感することで、お子さまは安心します。
朝のルーティンを決める・視覚的なサポートを取り入れる
登園・登校までの流れを毎朝同じにすることで、お子さまの心が整いやすくなります。発達特性のあるお子さまはもちろん、そうでないお子さまにとっても「毎日の見通しが立つ」ことは安心につながります。
たとえば、
例:「朝ごはん → 着替え → トイレ → 玄関でハイタッチ → 出発」
のように順番を決めておくと、気持ちの切り替えがしやすくなります。
また、その流れをイラストや写真で「見える化」することで、小さなお子さまでも自分で行動しやすくなります。これは特別な支援ではなく、誰にとってもわかりやすく、自立につながるサポートです。必要に応じて、タイマーやカウントダウンアプリなどを組み合わせても効果的です。
「あと何をすればいいのか」が視覚的にわかると、親の声かけが減り、朝のイライラも少なくなります。特に新生活が始まったばかりの時期には、おうちの中の“いつも通り”が、子どもにとっての安心材料になることも多いのです。
「学校が楽しい場所」と思えるようにする
学校が「楽しい」と思えれば、不安は少しずつ和らぎます。
- 先生に協力をお願いし、「その日の楽しいこと」をお子さまに伝えてもらう
- 学校での楽しみを見つける(好きな文房具を使う、楽しみな給食のメニューを話すなど)
「学校には楽しいことがある」とお子さまが思える工夫をすると、登校しぶりが和らぐことがあります。
親の不安を伝えすぎない
ご家族が「大丈夫かな?」と不安そうにしていると、お子さまは「やっぱり学校は怖いところ?」と感じてしまうことがあります。
- 「パパとママも応援してるよ!」とポジティブな声かけをする
- 「帰ってきたら一緒に○○しようね」と、帰宅後の楽しみを作る
ご家族の安心感が、お子さまにとっての心の支えになります。
必要に応じて段階的に慣らす
どうしても登校が難しい場合は、無理に丸一日登校させようとしないことも大切です。
・担任の先生と相談し、短時間だけ登校する
・保健室登校・別室登校の選択肢を検討する
無理やり行かせるのではなく、少しずつ慣れるためのステップを作ることが重要です。
看護師ナニー直伝、「いってきます!」ができるようになる優しい声かけ
どんなお子さまでも、「今日はパパやママと離れるのが寂しいな」「お家でゆっくり過ごしたいな」と感じる日があります。そんなときは、無理に「泣かないで!」と言うのではなく、気持ちに寄り添いながら、前向きな声かけをしてあげることで、子どもの気持ちが少しずつ落ち着いていきます。
ぜひ、これらの声かけを参考にしてみてください。
朝のバイバイは短く、明るく
お別れの時間が長くなると、かえって寂しさが増してしまうこともあります。「いってらっしゃい!」「楽しんでおいでね!」と、明るく送り出してあげましょう。
「ママ(パパ)は必ず迎えに来るよ」と伝える
新しい環境では、まだ毎日の流れがつかめず、「本当にママやパパが迎えに来るのかな?」と不安になることがあります。毎日繰り返し「ちゃんとお迎えに行くよ」「帰ったら一緒に〇〇しようね」と伝えることで、少しずつ安心できるようになります。
新しい環境にも楽しいことがあることを話す
「○○ちゃんと遊べるね!」「新しい先生に会えるね!」といったように、ワクワクできることを一緒に見つけてあげるのも効果的です。一緒にお気に入りの持ち物を準備したり、園や学校での楽しい場面を想像できるような話をすると、前向きな気持ちになりやすくなります。
「不安なのは普通のことだよ」と伝える
「大丈夫だよ」と励ますだけでなく、「最初はみんなドキドキするよね」「パパやママも、新しい環境は緊張することがあるよ」と共感してあげるのも大切です。「僕(私)だけじゃないんだ」と思えると、お子さまの気持ちが少し楽になることもありますよ。
「もしかして心の不調?」——分離不安症とは?
多くの場合、分離不安は一時的なもので、子どもが成長する中で自然に落ち着いていくものです。しかし、ごく稀にですが「分離不安症」と呼ばれる状態に当てはまることもあります。これは、親と離れることへの不安が非常に強く、日常生活に支障が出るほど続く状態を指します。
これは DSM-5-TR(精神疾患の診断基準)に定められた不安症の一種 で、以下のような症状が6ヶ月以上続く場合に診断されることがあります。
- 親と離れることへの強い恐怖やパニック
- 登校拒否や日常生活への支障
- 親が見えないと過度に泣く、暴れる
- 「親がいなくなるのでは」と強い恐怖を持つ
こうした状態が続く場合は、一度専門家(小児科・児童精神科・スクールカウンセラー)に相談してみるのも一つの手です。
大切なのは、「これは甘えではなく、子どもなりのSOSかもしれない」と気づいてあげることです。
まとめ:焦らず、お子さまのペースを尊重する。

分離不安による登園・登校しぶりは、多くのお子さまが経験するものです。
「どうして行きたくないの?」と責めるのではなく、「不安なんだね」と気持ちに寄り添うことが何より大切です。お子さまは、安心できる環境があれば、少しずつ新しい生活に慣れていくことができます。今は不安でも、時間をかけて少しずつ慣れていけばいいと、焦らずサポートしていきましょう。もし登校しぶりが長引く場合は、スクールカウンセラーや専門家に相談するのも選択肢のひとつです。
このように、お子さまの気持ちを受け止め、そっと寄り添いながら成長を支えるのが、教育ベビーシッター(ナニー)の大切な役割です。
お子さまとご家族にとって、安心できる存在になるために――。
あなたも、ナニーとしての一歩を踏み出してみませんか?ナニーのお仕事にご興味のあるかたはぜひこちらをご覧ください→

この記事を書いた人
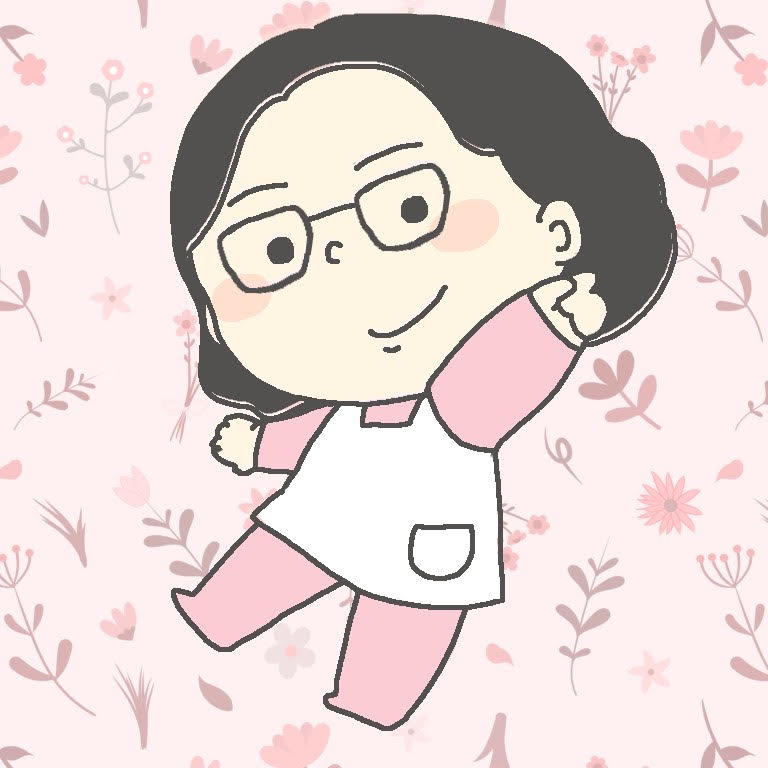
- Naoka
- 看護師、保育士、養護教諭の資格を持つナニーとして活動しています。これまで保育園や小学校、放課後デイサービスなど、さまざまな現場で経験を積んできました。現在ナニーのお仕事をしながら、療育施設にて自閉症スペクトラム症のお子さまたちの支援に取り組んでいます。



 前の記事
前の記事 次の記事
次の記事

