contents
病児・感染症対応が求められる理由
お子さまが体調を崩した際に
- 仕事を休めない…
- どうしても外せない予定がある…
- 病児保育がいっぱいで預け先がない…
といった状況に直面する保護者の方は少なくありません。
こうした場面で、自宅で安心してお子さまを預けられるナニーサービスは、心強い選択肢のひとつです。ナニーは病児・感染症ケアの知識を持ち、お子さまの体調管理や適切な対応ができる専門家です。ご家族に代わり、ナニーが心を込めてお世話いたします。
症状に合わせたケアを行いながら、お子さまが少しでも快適に過ごせるよう配慮します。また、万が一の緊急時にも会社と連携を取り、適切な判断ができるため、ご家族にとっても安心してご利用いただけます。
本記事では、看護師ナニーの視点からナニーサービスにおける病児・感染症対応の具体的な内容や、お子さまのケアのポイントを解説します。
ポピンズナニーサービスの病児・感染症対応とは
事前に医療機関を受診のうえ、「病児」または「感染症児」オーダーとしてご依頼いただきます(病児または感染症児の特別料金となります)。とはいえ、病児・感染症児の場合は、前日または当日にお電話でご依頼を頂くことが多いため、コーディネーターが発症日や症状、受診の有無、診断名、ご家族の罹患の有無等、詳細を丁寧にヒアリングさせていただきます。
そして保護者様のご指示の元、体温、呼吸状態などのバイタルチェック、水分補給や食事の介助、「薬についての依頼書」(ポピンズナニーサービスフォーマット)に基づいた処方薬の服薬介助、安静に過ごせる環境づくりなど感染拡大のリスクを抑えながら、ご家族に代わり、心を込めたケアを行います。
病児対応
風邪、発熱(37.5度以上)、下痢、嘔吐、中耳炎、お怪我などのお子様特有の病気に罹患しており、保育園などで通常の保育を受けることができないものの、ご自宅での両党が可能なお子様をお預かりするサービスです。
また、病気や怪我の回復期にあるお子さま(発熱がなくても、咳や鼻水などの呼吸器症状がある場合など)でも、ご家庭での療養を希望される場合は病後児対応としてお引き受け可能です。
病児オーダーの場合、通常のシッティングに加え、お子さまの体調管理や安静に過ごすためのケアを行います。
感染症対応
インフルエンザや胃腸炎など、ポピンズファミリーケア指定の感染症と診断されたお子さまをお預かりするサービスです。
以下の場合は「感染症対応」となります。
- インフルエンザ・百日咳・麻しん・風しん・流行性耳下腺炎・新型コロナウイルス・ウイルス性胃腸炎・水痘・アデノウイルス、急性出血性結膜炎、溶連菌など、ポピンズファミリーケアの指定する感染力の強い疾患と診断された場合
- 同居されているご家族が上記感染症に罹患された場合
感染症対応では、より厳格な感染対策が必要となるため、対応できるナニーが限られることがあります。
病児・感染症児対応の流れ
⑴事前連絡
病児・感染症児の場合、通常のお世話の確認事項に加え、以下の内容を訪問前日の事前電話で確認します。
- お子さまの症状(元気の有無・食欲・睡眠状況など)
- 発熱がある場合:発熱の開始時期・体温の推移・解熱剤の使用の有無・嘔吐や下痢の有無・呼吸器症状の有無・かかりつけ医の指示
- 保護者のお世話の希望
<ナニーが持参するもの>
- マスク・ハンドタオル(ペーパータオル推奨)
- ティッシュ・ディスポーザブルグローブ(5枚程度)
- 消毒用アルコール・ビニール袋・エプロン
- 着替え(ナニー自身のもの)
- 「薬についての依頼書」
⑵当日の対応
打ち合わせ
事前連絡の内容をもとに、お子さまの体調・症状を詳しくヒアリングします。食事・排泄・睡眠のパターンや緊急時の対応について確認し、スムーズなお世話につなげます。
<ご家庭で準備があると便利なもの>
- 体温計
- 健康保険証・診察券・お薬手帳
- 水分補給用の飲み物(経口補水液・麦茶・リンゴジュースなど)
- お子さまの着替え・タオル・ビニール袋(嘔吐・下痢対応用)
- かかりつけ医の連絡先
- クーリング用品(保冷剤など)
※貼るタイプの冷却シートは特に乳幼児には窒息のリスクがあるため、ナニーサービスでは推奨していません。
お世話
【発熱時のケア】
- 1時間ごとの検温と記録
- 水分補給の徹底
- 室温、湿度や衣服の調整
- 尿量の確認(脱水を避けるため)
- 咳や鼻水のケア
※ナニーサービスでは鼻水は原則ふき取りのみで、家族の指示が有り、必要がある場合のみ鼻吸い(手動・自動問わず)の対応を行っています。
【嘔吐と下痢時の対応】
- 嘔吐時の素早い処理と着替え
- 吐しゃ物が逆流しないよう、横向きに寝かせる
- おむつ交換の頻度を増やし、脱水の有無を観察
【その他の注意点】
- お昼寝時は5分おきにブレスチェックと体勢(うつ伏せ寝の防止)を確認
- 手洗いと消毒の徹底、感染拡大の防止
- 体調の変化を「ポピンズメモリー」に記録
お世話終了と報告
- 「ポピンズメモリー」をご覧いただきながら体調の変化やケアの内容を保護者の様に報告
- 帰宅後は感染拡大をしないよう衣服をすぐに着替え、手洗いうがいを徹底します
*「ポピンズメモリー」とは?
ポピンズメモリーは、当日のお世話の内容や出来事、体調についてご家庭へ報告をするものです。病児・感染症児のお世話の際は以下のような内容を記載します。
- バイタルチェック:1時間おきの体温の推移、内服薬や坐薬の使用時間、食事と水分量、尿の回数と色
- 呼吸器症状:呼吸パターン、咳の有無、音、多い時間帯、痰の色や粘稠度など
- 消化器症状:嘔吐と下痢の回数、性状、形状、色と時間
看護師が解説|病児・感染症児のお世話のポイント

病児・感染症児のお世話をする際、「どこまで対応すればいいのか」「何に気をつければいいのか」と悩むことも多いかと思います。特に、発熱や嘔吐などの症状があると、お子さまの体調変化に気を配りながら適切にケアすることが求められます。
私は看護師資格を持つナニーとして、これまで多くのお子さまの体調不良時のお世話に携わってきました。その経験をもとに、病児対応のポイントをまとめました。無理のない範囲で取り入れながら、お子さまが安心して回復できる環境づくりを目指していただければと思います。
体調管理のコツ(バイタルチェック・観察のポイント)
お子さまの体調は変化しやすいため、こまめな観察が重要です。以下のポイントを意識しながら、お世話を行いましょう。
- 熱の測り方:脇の下でしっかり測る(耳式・額式体温計は補助的に使用)
- 顔色・呼吸の観察:唇の色が悪い、呼吸が苦しそうな場合は要注意
- ぐったりしていないか:反応が鈍い・元気がない場合はすぐに受診を(ナニーさんは会社に報告)
- 発疹や皮膚の変化:赤み・腫れ・かゆみの有無をチェック
また、発熱時に汗をかいた場合は、こまめに汗を拭き、必要に応じて着替えをさせることで体温調節をサポートできます。
脱水予防・食事の工夫
- 水分補給をこまめに(スプーン1杯ずつでもOK)
発熱や下痢・嘔吐があると、体内の水分が失われやすいため、脱水を防ぐことが大切です。
- 飲みやすいものを選ぶ(麦茶・経口補水液・薄めたリンゴジュースなど)
- 消化の良い食事を用意(お粥・うどん・すりおろしリンゴなど)
無理に食べさせる必要はありませんが、水分は少しずつでも摂れるように工夫しましょう。水分が摂れず、尿量も減少している場合は脱水のおそれもあるため受診を考えましょう。
※ナニーさんは飲み物、食べ物の準備は保護者様のご指示に沿ってください。
安静に過ごせる環境づくり
病気のときは体力を回復させるために、できるだけ安静に過ごすことが大切です。
- 室温・湿度を調整(室温20~23℃、湿度50~60%が目安)
- 照明を少し落として、落ち着いた空間をつくる
- 絵本の読み聞かせや静かな遊びで気を紛らわせる
お子さまが安心して休めるよう、無理のない範囲で関わりながら、ゆったりと過ごせる環境を整えましょう。
感染予防対策
感染症のお世話をする際は、周囲の大人が感染しないよう十分に対策を取ることが重要です。
- マスク、手袋とエプロンを適宜着用
- 手洗いとアルコール消毒をこまめに実施
- 使用したタオルやおもちゃは消毒・洗濯する
- 嘔吐や排泄物の処理は、使い捨て手袋を使用し、処理後はすぐに手を洗う
以上のように、病児・感染症児のお世話では、体調管理・脱水予防・安静確保・感染対策が重要です。
お子さまが安心して過ごせるよう、細やかな配慮を心がけながら対応していきましょう。
熱性けいれん時のお世話のポイント
ナニーとして病児保育を担当する際、発熱に伴う「熱性けいれん」に対応することがあります。多くの場合、短時間で自然に治まるものの、初めて立ち会うと驚いてしまうこともあるかもしれません。ここでは、熱性けいれんが起こった際の具体的な対応方法をご紹介します。
けいれんが始まったら落ち着いて対応する
お子さまが突然けいれんを起こすと、ご家庭も動揺されることが多いですが、ナニーは冷静に対応することが大切です。
まずは以下を確認しましょう。
- けいれんが始まった時間を記録する
- 呼吸の状態(顔色が青白くなっていないか)
- けいれんの様子(全身か、体の一部か)
- 意識の有無(名前を呼んで反応があるか)
けいれんが5分以上続く、または繰り返す場合は、すぐに119番通報しましょう。
また、6カ月未満のお子様のけいれんや、発熱を伴わないけいれんは早急な受診が必要です。けいれんの様子を動画で記録しておくと、診断の助けになります。
※ナニーさんはすぐに会社へ連絡し、指示を仰いでください。119番通報も会社が行います。
安全な体勢をとる
けいれん中のお子さまは、誤って窒息しないよう配慮が必要です。
以下の体勢をとりましょう。
- 仰向けまたは横向きに寝かせる(嘔吐時の誤嚥を防ぐ)
- 口の中に物を入れない(舌を噛むことはないため、無理に押さえない)
- 周囲の危険物を遠ざける(ぶつかりそうな家具を避ける)
けいれん後のお世話
けいれんが治まった後、お子さまはぐったりしたり、しばらく眠ることがあります。
けいれん後は次の点に注意しましょう。
- 呼吸が整っているかを確認する
- 無理に起こさず、落ち着くまで見守る
- 水分補給は意識がはっきりしてから行う
受診が必要なケース
以下のような場合は、すぐに医療機関の受診をおすすめします。
- けいれんが5分以上続く
- 1日に2回以上けいれんを繰り返す
- けいれん後、意識が戻らない・ぐったりしている
- 発熱以外の原因が考えられる(頭を強く打った後など)
まとめ

病児保育は、お子様の体調が優れないときにご家族に寄り添い、安心して過ごせる環境を提供する大切なお仕事です。看護師や保育の経験を活かしながら、お子様の看病・見守りをすることで、働くお母様・ご家族を支えるやりがいを感じられます。
「急な発熱で仕事を休めない…」
「病児対応をしっかり任せられる人にお願いしたい」
そんなとき、24時間365日対応のポピンズナニーサービスの病児対応を利用すれば、経験豊富なナニーがご家庭と連携をとりながら、お子様をしっかりサポートします。万が一のときにも安心してご依頼いただけます。
「病児・感染症対応のスキルを活かしたい」
「働くママを支える仕事がしたい」
そんな想いをお持ちの方、一緒に働いてみませんか?
ポピンズナニーサービスでは、ナニーとして安心して働ける環境を整えています。 急な病状の変化にも会社と連携しながらサポートできるため、不安なくお仕事を始めることが可能です。お子様とご家族を支える、やりがいのあるお仕事です。
あなたの経験を活かして、ぜひチャレンジしてみませんか?詳しくはこちらをご覧ください→

この記事を書いた人
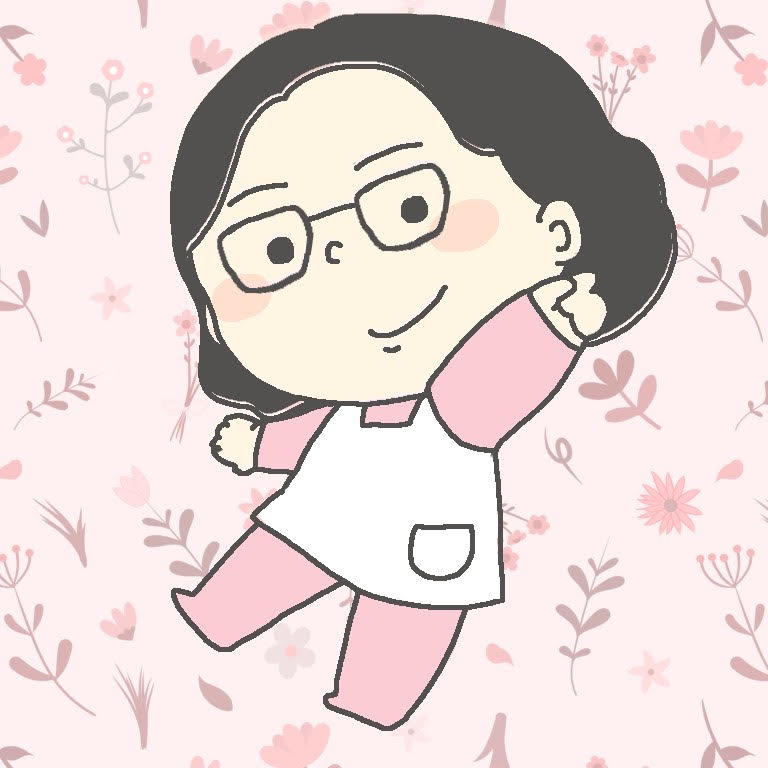
- Naoka
- 看護師、保育士、養護教諭の資格を持つナニーとして活動しています。これまで保育園や小学校、放課後デイサービスなど、さまざまな現場で経験を積んできました。現在ナニーのお仕事をしながら、療育施設にて自閉症スペクトラム症のお子さまたちの支援に取り組んでいます。



 前の記事
前の記事 次の記事
次の記事

