保育士には資格が必要ですが、保育士の資格がない人でも保育補助として保育園で働くことはできます。しかし、保育士と保育補助では、担当できる仕事も変わってくるため、保育補助の経験を持つ人の中には保育士の資格取得を目指したいという方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、保育補助から保育士資格を取得する方法や保育士資格の取得メリットなどについて分かりやすくご説明します。
保育補助から保育士資格を取得することは可能?方法を紹介
保育補助から保育士資格を取得することはできます。保育補助の経験を持つ人が保育士資格を取得する方法としては、以下の4つの方法が考えられます。
保育系の専門学校・短大を卒業する
保育士の多くは、保育士資格を取得できる保育系の専門学校や短大、大学で学んでいます。各都道府県知事が指定する指定保育士養成施設で必要な科目を履修し、卒業すると保育士資格を取得できます。
指定保育士養成施設は、2年制のものから4年制のものがあり、保育士の多くは、指定保育士養成施設を卒業しています。全国にある指定保育士養成施設の一覧表は、こども家庭庁のWebページからダウンロードが可能です。
こども家庭庁:指定保育士養成施設一覧(令和6年4月1日時点)(Excel/165KB)
通信やスクールで学んで保育士試験を受ける
保育系の専門学校や短大で学び、卒業した場合、保育士試験を受けることなく保育士資格を取得することができます。しかし、専門学校や短大で学ぶには、まとまった額の費用が必要です。また、最低でも2年間は通学が必要になるため、保育補助として働きながら保育士の資格取得を目指したい方にとっては、非現実的な方法になるでしょう。そのため、保育補助として働きながら保育士資格の取得を目指すには、専門学校や短大への入学はハードルが高いといえます。
指定保育士養成施設ではない大学や短大、専門学校を卒業している場合は、保育士の知識を学べる通信教育や資格取得スクールなどを活用し、保育士試験を受験することが可能です。保育士試験は毎年4月と10月の年2回開催されています。保育士試験に合格すれば、保育士資格を取得できます。
保育士試験の受験にあたっては、通信教育や資格取得スクールの受講が受験要件になっているわけではありません。しかし、保育士試験の合格率は例年20~30%程度と低く、独学で勉強するよりも、効率よく試験のポイントを学べる通信教育や資格取得スクールを活用したほうが、試験には合格しやすくなります。
実務経験を積んで保育士試験を受ける
児童福祉施設での実務経験が2年以上あるときには、大学や短大、専門学校を卒業していない高校卒業の方でも保育士試験を受けることができます。また、所定の児童福祉施設での勤務経験時間の条件を満たせば、中学卒業であっても受験資格を得られます。
児童福祉施設とは、次のような施設です。
- 認定子ども園
- 幼稚園
- 家庭的保育事業
- 小規模保育事業
- 居宅訪問型保育事業
- 事業所内保育事業
- 放課後児童健全育成事業
- 一時預かり事業
- 離島その他の地域において特例保育を実施する施設
- 小規模住居型児童養育事業
- 乳児等通園支援事業
- 障害児通所支援事業
- 一時保護施設
- 18歳未満の者が半数以上入所する障害者施設や指定障害福祉サービス事業所 など
高校卒業の人は、これらの児童福祉施設において、2年以上、かつ2,800時間以上、児童などの保護や援護に従事した場合、保育士試験の受験が可能です。また中学卒業の人は、5年以上かつ7,200時間以上従事した経験がある場合、保育士試験の受験資格を得られます。
※ナニーのお仕事は上記の居宅訪問型保育事業に該当します。ナニーのお仕事をしながら保育士資格取得を目指す方も多く、お薦めです。
資格がなくてもOK!保育補助経験を生かしてナニーとして働いてみませんか→
保育補助として働いて保育士試験を受ける
保育園によっては、保育補助として働くスタッフに対して、保育士資格の援助を行うケースもあります。また、保育補助者の保育士資格取得を支援する補助金制度を用意している自治体もあります。
例えば、東京都の保育従事職員資格取得支援事業は、指定保育士養成施設の入学料や受講料、保育士試験の受講料、教材費、通信講座の受講料などの費用や代替職員の雇用経費の一部を支援するものです。認可保育所や認定子ども園、認証保育所、認可を受けた小規模保育事業等で保育補助の仕事に就いている人が対象であり、資格取得後1年以上保育所等に勤務することが補助条件となります。(※1)
また、ほかの自治体でも保育補助として働く人の資格支援サポート事業を行っています。保育補助から保育士資格の取得を目指す際には、自治体の補助金制度なども確認してみるとよいでしょう。
保育補助から保育士資格を取得するメリット

保育補助を経験してから保育士資格を取得する場合、次のようなメリットを得られます。
より深い知識を習得できる
保育士試験では、保育に関する専門的な知識が求められます。保育に関わった経験がなければ触れることのない知識なども出題されるため、保育士資格の合格率は決して高くありません。しかし、保育補助として、保育の現場で働けるため、実践でなければ身に付けることができない知識やスキルを身に付けられます。また、保育士試験で出題される専門的な知識も保育補助として現場で働くことで、自然に学べるケースが少なくないのです。保育補助として保育の現場を体験し、日常的に目にすることや耳にすることが出題されるため、保育士試験の勉強も進みやすくなるでしょう。また、保育補助者が保育士資格を取得するために、専門的な知識を学ぶと、保育補助の仕事を行う上でもより的確に対応できるようになります。
担当できる仕事が増える
保育補助と保育士では、担当できる業務に違いがあります。保育補助者が保育士資格を取得して保育士として働くと、クラス担任を受け持つことが可能です。クラス担任になれば、子どもたちの指導計画やクラス運営にも関わることができます。また、七夕祭りや運動会、クリスマス会、生活発表会などのイベントの企画や運営も保育士が中心となって進められるため、保育補助はサポート的な役割でしか関われません。しかし、保育士の資格を取得するとこれらのイベントにも主体的に関わることが可能です。
そのほか、子どもたちの担任として保護者と接する機会も増えるため、より保護者と連携しながら保育を進めることもできるようになります。担当できる仕事が増え、保護者とも積極的に関われるようになると、やりがいも大きくなるでしょう。
就職に役立つ
保育補助は、正社員ではなく、パートなどの雇用契約になるケースが多くなっています。しかし、保育士の資格を取得すれば、正社員として働くことも可能です。保育補助の経験があり、保育士資格を保有しているとなると、即戦力として高い評価を得られる可能性があります。また、保育補助として働く施設で、そのまま正社員の保育士として雇用されるケースもあるでしょう。慣れ親しんだ保育園で働くことができれば、就職活動の必要もなく、スムーズに保育士の仕事に順応できるのではないでしょうか。
保育士資格を取得した場合、保育補助に比べて賃金条件もよくなります。就職に役立つ点と賃金アップが期待できる点も、保育士資格を取得するメリットだといえます。
働きながら保育士資格を取得するためのポイント
保育補助から保育士資格の取得を目指す場合、保育補助として働きながら勉強を続け、試験を受ける方法と、一度退職し、指定保育士養成施設に入学して卒業する方法があります。保育補助として働きながら保育士資格の取得を目指すことは、勉強できる時間も限られるため、決して簡単ではありません。そのため、働きながら保育士資格の取得を目指すのであれば以下のポイントに気を付けることが大切です。
スケジュールをしっかりと立てる
保育補助として働きながら保育士資格を目指す場合、昼間は仕事をしているため、勉強できる時間は夜間や休日に限られてしまいます。限られた勉強時間で試験に合格するためには、試験日までの期間を逆算しながら綿密な勉強のスケジュールを立てることが大切です。試験範囲を確認した上で、1カ月や1週間単位で勉強の計画を立て、十分に準備を整えた状態で試験に臨めるようにしましょう。
体調管理に注意する
働きながら保育士資格の勉強をするとなると、本来は休息に充てるべき仕事終わりの時間や休日に勉強をしなければなりません。特に保育補助の仕事では、子どもたちのお世話に体力が求められます。仕事で疲れた後に勉強をするとなると、身体への負担も大きくなります。
感染症が流行しやすい時期などに、疲れによって免疫力が低下していると、子どもたちから病気がうつってしまう可能性もあるでしょう。体調が悪化すれば、仕事を休まなければならなくなったり、勉強のスケジュールが遅れてしまったりする可能性もあります。また、試験当日に体調を崩すと、本番でこれまでの勉強の成果を十分に発揮できないおそれも出てくるでしょう。
そのため、疲れているときには休息を優先するなどし、仕事と勉強の両立で無理をしすぎないようにすることも大切です。
試験内容を把握しておく
働きながら保育士資格を目指す上では、試験内容を把握し、効率よく勉強することが最大のポイントです。保育士資格の出題範囲は非常に広くなっています。しかし、重要な部分はある程度決まっており、出題される問題には一定の傾向が見られるものです。そのため、すべての科目のすべての内容について同じ熱量で勉強するのではなく、過去問などを確認しながら、出題されやすいポイントを中心に効率よく勉強を行うことが重要になります。また、過去問を解く際には、実際の試験時間である1時間の時間制限の中で解けるよう、時間配分についても意識するようにしましょう。
保育士試験では実技試験もありますが、実技試験は筆記試験の約2カ月後に実施されるものです。実技試験は、音楽、造詣、言語に関する技術から2分野を選択する形式であり、いずれも、保育補助として働いている場合では、保育の場で実践できる課題となっています。実技試験の勉強については、保育士にも相談しながら、保育補助の仕事の中で身に付けられるように準備を進めるとよいでしょう。
まとめ
保育園では、保育士の資格がなくても保育補助として働くことができます。しかし、保育補助と保育士では、任せられる仕事の内容や待遇面にも違いがあります。そのため、保育補助としての経験を生かしながら、職場の保育士の資格取得を目指したいと考える方も少なくないのではないでしょうか。
保育補助から保育士資格を取得する場合、自治体などが費用面での支援を行っている場合もあります。働きながら保育士資格の取得を目指す場合には、保育士試験の受験が必要です。保育補助として勤務しながら資格試験の勉強をすることは簡単ではありませんが、保育士の資格を取得した暁には、より自信を持って子どもたちや保護者と向き合えるようになるでしょう。ご自身のライフプランに合った方法で保育士資格の取得を目指してみてはいかがでしょうか。
例えば、保育補助の経験はナニーの仕事に生かすこともできます。そしてナニーの仕事は、自分の予定に合わせて働けるため、保育士資格の勉強時間を確保したい方にもおすすめです。なにより、お子様のお世話に入ることで保育士試験の学びに繋がることもあるでしょう。働きながら通信教育などで保育士資格の合格を目指したい場合には、ナニーとして働くという選択肢も検討してみてください。ポピンズではナニーを募集しています。詳しくはこちらをご覧ください→

この記事を書いた人
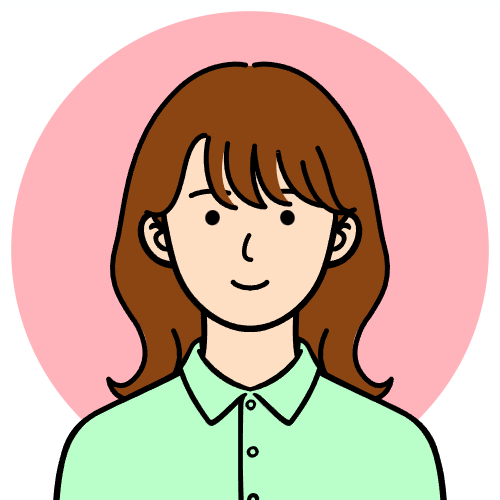
- 中川 恵理子
- 実家のサポートを得られない土地での子育てを経験し、「娘が小さかったときにナニーサービスを知りたかった!」と心から感じている中学生の母です。子育て中のお母様たちをサポートできる皆さんのお役に立てる情報を分かりやすくお伝えできるよう頑張ります。



 前の記事
前の記事 次の記事
次の記事

