看護師資格を持ちながら、病院やクリニックではなく、ナニーとして活躍する人が増えています。医療の現場を離れ、お子さまの成長に寄り添う仕事には、病棟や外来勤務とはまた違ったやりがいがあります。
ナニーの仕事は、ただお世話をするだけではありません。このお子さまやご家庭にとって、今どんな関わりが最適だろう?と常に考えながらサポートすることが求められます。この姿勢は、まさに看護の本質とも通じるものです。
今回は、看護師としての経験を活かしながらナニーとして働くことの魅力ややりがい、そして新しい働き方の選択肢としての「看護師ナニー」についてお伝えします。
ナニーになった時に感じる魅力とは?
お子さま一人ひとりと深く関わることができる
玄関のドアを開けると、小さな足音が弾むように近づいてきます。ナニーの姿を見つけると、お子さまがキラキラした目で見上げ、「一緒に遊ぼう!」と笑顔で手を伸ばします。ご家族は「今日はよろしくお願いします」と温かく迎え入れてくれました。
ナニー専用のエプロンに着替え、お世話内容の引継ぎを受けたら、お子さまの好きなおもちゃが並ぶ部屋へ。「今日は何をして遊ぼうかな?」と、お子さまの興味や気分に合わせて遊びを考えます。
病院や臨床の現場では、限られた時間の中で多くの患者さんに対応する必要があり、一人ひとりとじっくり向き合うのは難しいこともあります。一方、ナニーはご家庭に入り、お子さまと長期的に関わることができます。
たとえば、赤ちゃんの頃からお世話する場合、「首が座った」「ハイハイを始めた」「最初の一歩を踏み出した」といった成長の瞬間に立ち会えるのは、ナニーならではの醍醐味です。また、発達特性のあるお子さまの場合も、その子に合った関わり方を工夫しながら、少しずつできることが増えていく過程を見守ることができます。
「昨日できなかったことが、今日はできるようになった!」
そんな成長の喜びをお子さまと、そのご家族と一緒に分かち合えるのが、ナニーという仕事の魅力です。
子どもの生活環境を知ることで、新たな視点を得られる
病院では入院中や受診時の様子しか分かりませんが、ナニーとしてご家庭に入ると、お子さまが普段どんな環境で生活しているのかを知ることができます。
たとえば、「食が細い」と相談されるお子さまが、ご家庭では好きな食器や特定の環境でなら食べられることが分かることもあります。また、「落ち着きがない」と言われるお子さまが、実は静かな環境ではしっかり集中できるということもあります。また、保護者様の立場に立って考える機会が増えるため、「ご家族は何に困っているのか?」「どうすればより良い支援ができるのか?」といった、より実践的な視点を持つことができます。
このように、お子さまの生活環境や長所を深く理解した上での支援や、ご家族に寄り添ったサポートができることも、ナニーの魅力のひとつです。
自分の特技を活かした関わりができる
たとえば、
・楽器が得意な方:お子さまと一緒に歌ったり、簡単な楽器を作って演奏したりすることができるでしょう。
・運動が好きな方:外遊びを通じて体を動かす楽しさを伝えられます。忙しくてあまり公園遊びができないご家庭にとって、ナニーとしっかり外遊びができることはとてもありがたいものです。
・工作が得意な方:お子さまと一緒に製作遊びをすることで、「つくるって楽しい!」と感じていただくきっかけになり、お子様の表現力や想像力を養うことができるでしょう。
実際に、私が長く関わっているお子さまとごっこ遊びをしていたとき、「診察ごっこ」が始まりました。それをきっかけに、得意を活かして病院の道具や仕組みを説明すると、とても興味深そうに聞いてくれました。今では一緒に図鑑を見ながら、身体のしくみについて話すこともあります。
病棟では業務が優先されるため、こうした個別対応の時間はなかなか取れません。でも、ナニーなら「自分の得意なことを活かしながらお子さまと関われる」という新たなやりがいを感じることができます。
さまざまな特技を持ったナニーと一緒に遊ぶ経験は、そのお子さまの興味関心の幅を広げ、かけがえのない財産となるでしょう。
看護師経験を活かせるところ

観察力を活かした子どもの健康管理ができる
ポピンズのお仕事では「病児・病後児オーダー」と「感染症オーダー」があり、ナニーは、お子さまの症状に合わせたお世話をします。
お世話の際は看護師として培った観察力を活かし、お子さまの顔色や食欲、活動量の変化などを細かくチェックすることで、体調の変化をいち早く察知できます。
また、感染症が流行する時期には、手洗いや換気等、適切な予防策を取ることで、お子さまと家庭を守ることができます。看護師の経験があるからこそできる、健康管理の視点は、ナニーとしての強みの一つです。
ご家族が安心して病気のお子さまを預けられる「看護師ナニー」の存在は、訪問先のご家族からも好評いただいております。
心理的ケアや発達支援ができる
お子さまが不安を感じている時に寄り添ったり、発達特性に合わせた関わり方を考えたりと、ただの「お世話」ではなく、そのお子様に合ったケアができるのも看護師ナニーの強みです。
また、ご家族からは「ナニーさんに話を聞いてもらえただけで安心できた」「子どもを預けることに罪悪感があったけれど、帰ってきたときの楽しそうな様子を見て、頼ることも大切だと感じた」といった声をよくいただきます。
ナニーはお子さまだけでなく、ご家族の気持ちにも寄り添う仕事なのです。
看護師の新しい働き方としてのナニー

「今の職場に疲れてしまった」「看護師としての働き方を見直したい」と考えている方にとって、ナニーは新しい可能性を開く仕事です。
自分のペースで働ける
ナニーの仕事はシフト制ではなく、家庭ごとの依頼に応じて働くため、自分のペースで仕事を調整しやすいのが特徴です。例えば、フルタイムではなく、自分で決めたペースで働くことも可能ですし、短時間勤務や週数回の仕事も選べます。
また、ナニーとして働きながら、新たな資格取得に挑戦することもできます。私自身、ナニーの仕事を続けながら独学で保育士資格を取得しました。資格を取ることで、仕事の幅が広がり、より専門的に子どもの成長発達について学ぶことができました。また、「保育」という学問を歴史や制度の面から深く理解し、保育所保育指針がどのような願いを込めて編纂されたのかを知ることで、より意義のある関わりができるようになったと感じています。
ポピンズナニーサービスのナニーになると、日々の依頼件数が多いため、最寄駅周辺や通いやすい場所のお仕事を自分で選んで働くことが可能です。また、ご家庭でのお世話だけでなく、ポピンズナーサリースクールでの保育補助やホテル、イベント託児など、さまざまな現場で経験を積むこともできます。
このように、自分のペースで働きながら、新たな学びやスキルアップにも挑戦できるのがナニーという仕事の魅力のひとつです。
ブランクがあってもすぐに働ける
看護の現場を離れていた期間が長い場合や、臨床経験が短い場合、看護師としての復帰にはハードルを感じることがあります。しかし、ナニーの仕事には医療行為が含まれないため、その点の心配は不要です。
心身の負担が少ない
病棟勤務では夜勤があり、体力的にも精神的にも負担が大きくなりがちですが、ナニーは日中の仕事だけを選ぶことも可能です。生活リズムが安定し、無理なく働けるのも魅力です。
子どもの成長を見守るやりがいがある
病院での仕事は「治療」が中心ですが、ナニーの仕事は「成長」を見守ることがメインです。子どもが「できた!」と喜ぶ瞬間に立ち会えることは、大きなやりがいにつながります。
また、「ポピンズ居宅保育園」では複数人でチームを組み、お子さまを担当します。その際、ポピンズナニーサービスが大切にしている「エデュケア(教育的要素を含んだ保育)」に基づき、日々のお子さまのそれぞれの持つ個性と、豊かな感性や知力創造力を引き出す保育の実践を行います。居宅訪問支援事業に携わるナニーは研修を受けた後、ご希望のご家庭へ伺い、お子さまの担任の先生のような立場で関わることができます。
お子さまの成長に合わせた遊びやお世話を工夫するのが好きな方にとって、非常にやりがいのある仕事です。
相談できる人がすぐ近くにいる
子育て経験がない方や、現在の子育てが分からず不安だと感じる方含め、ナニー登録をした方全員にポピンズファミリーケアでは手厚い研修を実施しています。さらに、お世話中にトラブルや事故が発生した場合でも、24時間365日電話でのサポートがあるので、安心して相談できます。
ナニーは一人で働く仕事と思われがちですが、ポピンズファミリーケアではチームとなり、お子さまの安全と健康を支えています。またナニー同士の交流会も定期的に開催されており、お世話の際の工夫や、ご家族との円滑なコミュニケーションの方法について情報交換もできます。困ったときに支えてくれる仲間がいることは、大きな魅力の一つです。
おわりに
看護師資格を持ちながら、病院やクリニックとは異なるフィールドで活躍できる「ナニー」という仕事には、看護の知識と技術を活かしながら、一人ひとりのお子様に寄り添い、じっくり成長を見守ることができる魅力があります。
「今の職場での働き方に悩んでいる」「子どもと深く関わる仕事がしたい」と考えている方は、ナニーという選択肢を考えてみてはいかがでしょうか?詳しくはこちらをご覧ください→

この記事を書いた人
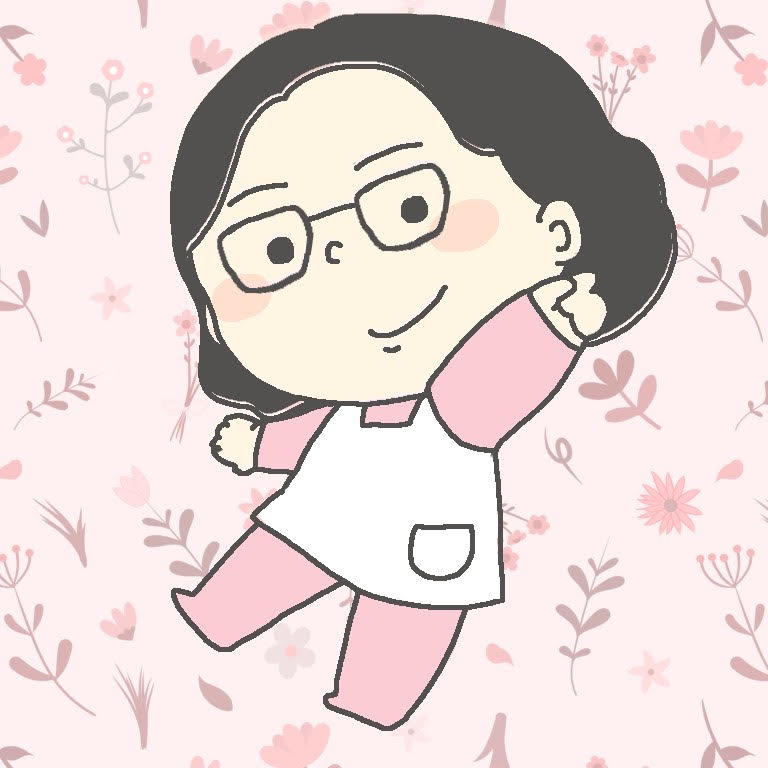
- Naoka
- 看護師、保育士、養護教諭の資格を持つナニーとして活動しています。これまで保育園や小学校、放課後デイサービスなど、さまざまな現場で経験を積んできました。現在ナニーのお仕事をしながら、療育施設にて自閉症スペクトラム症のお子さまたちの支援に取り組んでいます。



 前の記事
前の記事 次の記事
次の記事

