保育士として働く方の中には、保育士としてのスキルを高め、キャリアアップを目指す方もいらっしゃるでしょう。主任保育士は、保育士としてのキャリアを積んだ方が目指せるポジションです。では、主任保育士は具体的にどのような役割や業務を担うのでしょうか。
今回は、主任保育士の役割や仕事内容などについてご説明します。
主任保育士とは?役割を詳しく解説
主任保育士は、保育園における現場の最高責任者とも呼ぶべき重要なポジションです。主任保育士を目指すためには、主任保育士の役割について詳しく理解しておく必要があります。
主任保育士の役割
主任保育士は、保育士を束ねるリーダー的なポジションである一方で、園長のサポートをしながら施設の運営にも関与します。そのため、主任保育士が担任を持つことはありません。保育士全体の管理責任者であり、現場のマネジメントをしながら、園の運営を支える役割を担います。主任保育士には保育士の育成に関する知識や保育園の運営に関わる知識も求められるため、保育士として十分なキャリアを積んだ人が主任保育士のポジションに就くケースが多くなっています。
主任保育士の給与
主任保育士の給与は、園によって異なります。しかし、ほとんどの保育園では主任手当と呼ばれる役職手当を支給しており、マネジメントの役割も担う分、一般的な保育士より高い給与が支給されています。
こども家庭庁が公表している「令和6年度幼稚園・保育所・認定子ども園等の経営実態調査集計結果<速報>」によると、常勤で勤務する主任保育士の平均勤続年数は、私立保育園の場合は23年、公立保育園の場合は23.9年となっています。また、賞与込みの月平均賃金額は私立保育園の主任保育士が473,532円、公立保育園の主任保育士が564,357円です。同資料には、保育士の給与月額も記載されており、私立保育園の場合は348,119円、公立保育園の場合は、365,542円となっています。このデータを比べると、役職に就いていない保育士と主任保育士とでは、私立保育園の場合は約13万円、公立保育園の場合は約20万円もの差があることが分かります。(※1)
※1:こども家庭庁:令和6年度幼稚園・保育所・認定子ども園等の経営実態調査集計結果<速報>
一般的な主任保育士の仕事内容

主任保育士の仕事内容は、勤務する園によって若干の違いがあります。しかし一般的には、主任保育士は次のような業務を行っています。
施設の運営
保育園によって理念や保育方針は異なります。主任保育士は、園の理念や保育方針を十分理解した上で、理念や方針に沿った運営ができるよう、園長や副園長などと協力しながら園の運営に携わります。保育園で過ごす6年を通して、どのように子どもの成長をサポートするのか、年間ではなく、長期的な計画を作成することも主任保育士の仕事です。
また、運動会や生活発表会など、保育園の行事の企画や運営も主任保育士が行うケースが多くなっています。保育園によっては、保育士が担当するケースもありますが、その場合であっても主任保育士が全体を確認しながら、適切な指示を行うようになります。
園長のサポート
園長のサポートも主任保育士の大切な仕事です。園長や副園長は、地域の会議などに出席するケースも多く、不在にしている時間も少なくありません。そのような場合は、主任保育士が園長の代理として対応することになります。
そのほか、補助金の申請や報告書など、行政に提出する資料作成を補助するなど、園長のサポートも行います。
保育士の配置検討
保育士の配置検討も主任保育士の仕事です。多くの保育園では、クラス担任制を採用しており、保育士の個性や人柄を踏まえ、適切な配置を考えます。保育士の配置を検討する上では、担任と副担任の組み合わせや園児との関係性なども考慮しなければなりません。そのため、保育士の配置検討は、保育士と園児の特徴などをよく理解している主任保育士でなければできない仕事だともいえます。
また、保育園の開園時間は長いため、保育士は遅番と早番のシフト制で勤務しているケースがほとんどです。遅番と早番の偏りがないよう配慮しながら保育士の勤務シフトを作成することも、主任保育士の仕事となります。さらに、保育士のお休みや研修などによる不在なども考慮し、保育士の人数が不足することのないようシフトを組まなければならない点にも注意が必要です。
保護者対応
主任保育士は、保育士としての十分な経験と実績を持つ保育のプロです。そのため、保護者から子育てなどについての相談を受けるケースも少なくありません。また、クラス担任の対応などについて相談されるケースもあるでしょう。
保護者の主張にじっくりと耳を傾けながら、適切なアドバイスや対応を行うことも主任保育士の大切な仕事です。
保育士の相談対応
主任保育士は、保育現場の責任者でもあります。保育園では、さまざまな人間関係のトラブルが起きやすく、保育士から相談されることもあるでしょう。子どもとの信頼構築に悩むケースや、子どもたち同士のトラブルの解決方法に悩むケースなどでは、保育士としての経験を生かしたアドバイスが求められることもあります。また、保護者との関係性で悩む場合には、接し方についてのアドバイスをしたり、トラブルが拡大した場合には責任者として代わりに対応したりするケースもあるでしょう。
保育士が悩みを抱えたまま孤立してしまうと、退職につながる可能性もあります。そのため、一人ひとりの保育士の状況に目を配りながら、困ったときや悩んだときにはいつでも相談を受け付ける関係性を築くことも主任保育士の役割です。
保育実習への対応
保育士を目指す学生を受け入れる保育実習の対応も主任保育士の仕事です。主任保育士は、実習を通して保育士の仕事のやりがいや喜びを存分に感じてもらうことができるよう、指導計画を立て、実習生を受け入れるクラスなどの調整をします。
保育実習は、保育士を目指す学生にとって、学校で得た知識や技術を現場で試すよいチャンスです。また、実習を通じて子どもたちと実際にふれあうことで、子どもが興味を持ちやすいことに気づき、子どもとの接し方なども身に付けることができます。実習生にとって、保育実習が有意義な時間になるかどうかは、主任保育士の手腕によるともいえるのです。
主任保育士になるためのステップ
幅広い仕事を担当する主任保育士ですが、大きな責任を背負うもののその分大きなやりがいも得られるポジションです。そのため、保育士としてキャリアアップを目指す方にとって主任保育士は憧れのポジションになるでしょう。
では、主任保育士になるには、どのような準備が必要なのでしょうか。主任保育士になるためのステップについて解説します。
実務経験を積む
主任保育士になるためには、まず、保育士としての十分な実績が必要です。保育士としてのキャリアが少なければ、保育の現場を理解しにくいため、保育士をまとめることは難しくなります。経験が少ない分、保育士から相談を受けても適切なアドバイスができない可能性もあるでしょう。また、園長のサポートをしたり、園の運営に関わったりすることもできません。
前述のように、こども家庭庁が発表した資料によると、保育園の主任保育士の平均勤続年数は23年~23.9年です。このデータを見ても、主任保育士になるには十分な実務経験を積む必要があることが分かるでしょう。
必要なスキルを習得する
現場の最高責任者である主任保育士としての役割を十分に果たすためには、保育に関する深い知識とスキルが求められます。また、それだけでなく、組織をマネジメントするスキルも必要です。
各自治体では、保育士のキャリアアップ研修を開催しています。主任保育士を補佐する副主任保育士として処遇改善加算を受けるためには、キャリアアップ研修を修了しているか修了見込みでなければなりません。キャリアアップ研修にはマネジメントについて学べるものもあり、主任保育士を目指すのであれば、早めに研修を受講し、スキルを習得することも大切です。
リーダーや副主任保育士として経験を積む
保育士のキャリアアップ研修の創設に伴い、主任保育士以外にも、専門分野に精通した専門リーダーや特定分野の職務分野別リーダー、副主任保育士などのポジションが新たに登場しました。いきなり主任保育士を目指すのではなく、キャリアアップ研修などを受講しながら、段階的にリーダーシップやマネジメントスキルを身に付けることも大切です。
また、職務分野別リーダーや副主任保育士、専門リーダーに就任した場合、月々5千円または4万円の処遇改善手当の支給を受けることもできます。キャリアアップを目指す上で、賃金アップは大きな励みになります。保育士として忙しい日々を過ごす中で、研修を受けることは大変かもしれませんが研修を受ければ確実に知識が身に付きます。主任保育士を目指す場合には、日々の努力を積み重ねることが重要になります。
参考資料:こども家庭庁 処遇改善等加算IIの仕組み
まとめ
主任保育士は、現場の責任者として保育士をまとめるほか、園長のサポートをしながら園の運営にも携わる責任の大きなポジションです。保育士としてキャリアを重ねる上で、主任保育士を目指したいという方もいらっしゃるでしょう。保育士としての実績を十分に積んだ主任保育士が園の運営に関わることで、より保育士が働きやすい環境を整えることも可能です。さらに、主任保育士になると責任も重くなる分、給与も上がります。保育士としてキャリアアップを目指すのであれば、職務分野別リーダーや副主任保育士などのステップを踏みながら、主任保育士を目指してみてはいかがでしょうか。
保育士としてのキャリアも大切ですが、一人ひとりの子どもと真剣に向き合い、納得のいく保育を行いたいという方には、ナニーの仕事もおすすめです。ナニーは、保育園のように多くの子どもたちを預かることはないため、子どもの個性やペースに合わせた成長支援を行うことができます。また、自分の生活スタイルに合わせた働き方も可能です。保育の知識を生かしながら自分の理想の保育を実現したいという方は、ナニーの仕事も考えてみてはいかがでしょうか。現在ナニーを募集しています。詳しくはこちらをご覧ください→

この記事を書いた人
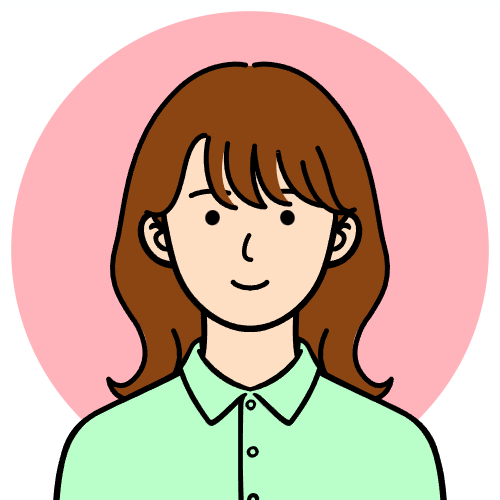
- 中川 恵理子
- 実家のサポートを得られない土地での子育てを経験し、「娘が小さかったときにナニーサービスを知りたかった!」と心から感じている中学生の母です。子育て中のお母様たちをサポートできる皆さんのお役に立てる情報を分かりやすくお伝えできるよう頑張ります。



 前の記事
前の記事 次の記事
次の記事

