ことばの発達は、親子のコミュニケーションや遊びの中で育まれるものです。お子様が「聞く力」と「わかる力」を身につけることで、より豊かなコミュニケーションが可能になり、感情の表現や思考力の基礎が形づくられていきます。
前回は、家庭で簡単にできる子どもの言葉を引き出し、コミュニケーションの土台をつくる具体的な方法をお伝えしましたが、今回の記事では、日常生活の中で楽しみながら「聞く力」と「わかる力」を伸ばすための方法を、具体的なアプローチとともにご紹介します。
また、今回は親子で試せる遊びや、コミュニケーションの方法を記載しています。全てを同時に試す必要はありません。その時々で、気になった方法を取り入れてみてくださいね。
contents
「聞く力」とは?
お子様が私たちの言葉を理解するためには、音の違いや言葉のリズムに気づくことが重要です。例えば、身近な環境音や会話の中で、異なる音を区別する力(音の弁別)が「聞く力」の土台となります。これが育つことで、お子様はコミュニケーションの基礎をより強化できます。
音の違いを楽しく体験する遊び

①「どんな音が聞こえる?」ゲーム:散歩やお出かけの際に、「鳥のさえずり」「救急車のサイレン」「遮断機が降りる時の音」など、周囲の音に耳を傾け、「何の音か」を当てる遊びをしてみましょう。親子で耳を澄ませることで、お子様は音の違いに注意を向け、音を聞き分ける力が自然と育まれます。
②「音の違い探し」:家の中でも、「ま」と「な」など似た音の違いを聞き分ける練習が効果的です。単語を少しずつ変えたり、お子様に発音を真似してもらうことで、発音と聴覚の連動が強まります。
随伴性を意識してみましょう

随伴性とは、親御さんがお子様の行動にすぐ反応することで、「自分の行動が親に影響を与えている」とお子様が感じることを指します。
例えば、お子様が声を出したり、笑顔を見せたりした時に、親御さんがその声や表情に反応して返すことで、「自分の行動に意味があるんだ!」という感覚が育ちます。この小さなやりとりを積み重ねることで、親子のコミュニケーションが豊かになり、お子様も関わり合う楽しさを感じるようになります。
画面よりも大切にしたい、親子間でのコミュニケーション
ある聞き分けに関する実験によると、子どもに直接人が話しかける方が、スクリーン越しに同じ内容の動画を見せる場合よりも、特に生後6か月以降の子どもにとって学習効果が高いことがわかっています。以下のコミュニケーション方法を参考にしながら、日々関わり合ってみると良いでしょう。
親の反応でお子様を支える方法
①表情や声で返す:お子様が「あっ!」と声を出したときや笑顔を見せたときには、親もその反応を返しましょう。声に出して「あっ!」と答えたり、笑顔で応えることで、親子の間に小さなやり取りが生まれます。
②行動へのリアクション:お子様が興味を持って見ているものや触れているものに対して、「何を見ているのかな?」と声をかけることで、気持ちや興味を共有できます。こうした小さなアプローチが、自然なコミュニケーション力を引き出します。
単語を理解するために「わかる力」を育む
「わかる力」を育てるためには、単語の切り出しが欠かせません。大人にとっては当たり前の単語の区切りも、お子様には連続した一つの音に聞こえることがあります。この切り出しを手助けすることで、言葉の意味や使い方を理解する力がスムーズに身についていきます。
単語の区切りを意識する工夫
①ゆっくりと話しかける:特に小さなお子様には、単語をひとつひとつ意識してゆっくり話すと効果的です。「これが りんご だよ」と区切りながら話すことで、単語の始まりと終わりがはっきりと認識され、言葉のリズムが自然に身についていきます。
②言葉と対象をリンクさせる:たとえば、絵本の読み聞かせの際に、イラストを指しながら「これは車だよ」と教えると、物と単語が一致しやすくなります。お子様が自然に「言葉が何を指しているか」を理解できる環境が生まれます。
②同じ言葉を何回も語りかける:繰り返し同じ言葉を聞くことで、お子様が意味のある単語の区切りに気がつくようになります。例えば、お母様が哺乳瓶を見せながら「ミルクだよ」「ミルク飲もうか」「ミルク美味しいね」と語りかけると、次第にお子様も「ミルク」という言葉に反応するようになります。
以上の方法を試すことで、赤ちゃんは言葉の貯金箱を増やすことができ、貯金箱が溢れることで言葉が出て来るようになります。毎日の生活の中でたくさん言葉をかけてあげましょう。
他にも楽しく実践できるアプローチ
これらのステップを日常に取り入れることで、「聞く力」「わかる力」を楽しみながら伸ばすことができます。
音楽や歌を使ったアクティビティ
①リズムに合わせて身体を動かす:親子で一緒に音楽を楽しむことも、言葉のリズムや音の区切りを学ぶ手助けになります。歌詞の一部を繰り返したり、リズムに合わせて体を動かすと、お子様は音や言葉を自然に体験できるでしょう。
②おもちゃや道具を使った音の再現:車のおもちゃで「ブー」という音を出したり、動物のぬいぐるみで「モー」と声を出したり、遊びの中で言葉と音をリンクさせましょう。これにより、お子様は言葉の意味とその対象がつながっていることに気づけます。
わかる力はどう伸びていくか

わかる力とは、例えば「くるま」という言葉が、ご自宅のおもちゃの車だけでなく、道を走る車や絵本の車など、さまざまなものに共通していると理解できるようになることです。このように、お子様が「くるま」と聞いてイメージを思い浮かべられるようになることで、言葉を正しく理解していきます。遊びの中で、こうしたイメージする力を育むことは、言葉の発達にも非常に重要です。
イメージする力を育てる遊び
赤ちゃんの頃の「感覚遊び」を卒業し、少しずつ物を他のものに見立てて遊べるようになってきたら、イメージを膨らませる「ごっこ遊び」や「見立て遊び」に挑戦してみましょう。例えば、積み木を車に見立てたり、ぬいぐるみにごはんをあげたりする遊びです。こうした遊びを通して、お子様は「他の人と一緒に遊ぶ楽しさ」や「関わる力」を少しずつ育てていきます。
「聞く力」と「わかる力」を伸ばしていくために大事なこと
まずはお子さまの様子、特に視線の方向をよく見て、何に興味関心があるのかを探り、お子さまが楽しいと実感できるような関わり方をしましょう。語りかける際は、お子さまが理解しやすく、取り入れやすい言葉で話しかけましょう。また、一緒に遊ぶ中で、周りの人への関心を高め、やりとりを増やしていきましょう。
まとめ

お子様の「聞く力」と「わかる力」は、親子の楽しいやり取りの中で自然と育っていきます。親御さんが楽しみながら音や言葉に意識を向けることで、お子様も楽しみながら学んでいけるでしょう。

この記事を書いた人
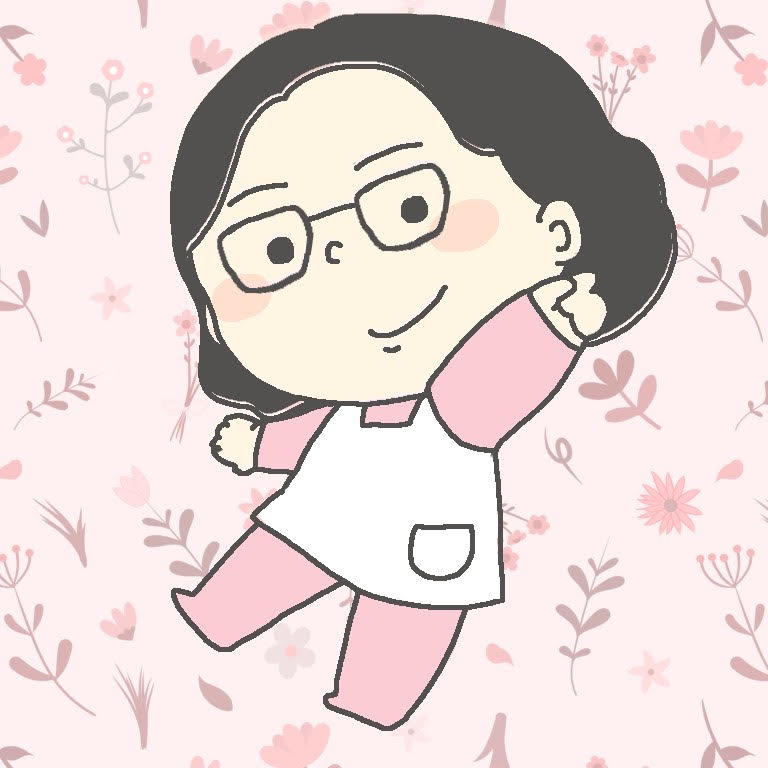
- Naoka
- 看護師、保育士、養護教諭の資格を持つナニーとして活動しています。これまで保育園や小学校、放課後デイサービスなど、さまざまな現場で経験を積んできました。現在ナニーのお仕事をしながら、療育施設にて自閉症スペクトラム症のお子さまたちの支援に取り組んでいます。



 前の記事
前の記事 次の記事
次の記事

