監修:医学博士、東京都市大学人間科学部特任教授
元聖路加国際病院小児科医長 草川 功先生
手足口病ってどんな病気?
「手足口病って、うつる?」「いつから登園していいの?」「下の子にもうつるの?」
そんな不安や疑問の声が、毎年夏になると聞こえてきます。
手足口病は、乳幼児のあいだで特に流行しやすいウイルス性の感染症。症状そのものは比較的軽いことが多いものの、登園停止の扱いや感染予防の工夫など、保護者にとっては判断に迷う場面も少なくありません。
本記事では、現役の看護師ナニーの視点から、手足口病に関する「よくある質問」にお答えしながら、登園の目安やご家庭でできる対応についてわかりやすく解説します。
手足口病の主な原因は「コクサッキーウイルスA型」や「エンテロウイルス71型(EV71)」などのエンテロウイルス属のウイルスです。毎年、夏に流行することが多く、特に0〜4歳の未就学児を中心に多くみられます。中でも2歳以下が半数以上を占めています。
主な症状と経過:感染から3〜5日後、以下のような症状が見られることが多いです。
手のひら・足の裏・口の中などに小さな水疱(ぶつぶつ):通常はかゆみや痛みを伴わず、かさぶたにならずに1週間ほどで自然に消えていきます。ただし、口の中の水疱が潰れると強い痛みを感じることがあり、食欲不振や機嫌の悪さにつながることもあります。
発熱:38℃未満のことが多く、高熱が続くケースはまれです。発熱が見られない場合もあります。
その他:よだれの増加、機嫌が悪い、食欲の低下なども、初期のサインになることがあります。一部の子どもでは、下痢・嘔吐・頭痛などの消化器・神経系症状を伴うことがありますが、多くは一過性です。
感染経路は、飛沫感染(咳やくしゃみ)、接触感染(水疱に触れる、おもちゃ・タオルなどの共有)、糞口感染(オムツ替えや排泄後、手指から口へのウイルス侵入)です。ウイルスは発症前から排出され、治ったあとも2〜4週間便に含まれるため、完全に防ぐことは難しいですが、手洗い、おもちゃの消毒やタオルの使い分けなどで予防は可能です。
手足口病には、特効薬やワクチンはなく、対症療法が基本です。発熱や痛みに対しては解熱剤の使用、口の痛みに配慮した食事(※後述)など、子どもが快適に過ごせる環境づくりが重要です。
子どもの手足口病に関するよくある質問

Q.登園の目安は?いつから保育園に行っていい?
A:発熱や口内の痛みなど、全身状態が落ち着いていれば登園OK。
手足口病は学校保健安全法の「登校停止疾患」には該当しないため、登園停止の明確な規定はありません。ただし、園によって独自の判断基準を設けている場合があるため、必ず園に確認を。
Q.ぶつぶつ(水疱)が残っていても登園できる?
A:水疱や発疹があっても、かさぶた状・乾いていればOK。
感染力は発症初期にもっとも強く、発疹そのものがうつる原因ではありません。ただし、ひっかいて破れている場合などは注意が必要です。
Q.口の中を痛がる時は何を食べたらいい?
口の中に水疱ができると、しみたり痛んだりして、いつも通りの食事や水分がとりづらくなります。特に食べたり飲んだりするたびに痛みがあると、子どもは食事を拒んでしまうことも。脱水を防ぐためにも、まずは無理のない範囲でこまめに水分をとらせてあげることが大切です。
おすすめは、喉越しがよく、冷たくてしみない食べ物です。ゼリー、プリン、ヨーグルト(プレーンタイプや加糖のなめらかタイプ)、アイスクリーム、アイスミルク(少量ずつ)、経口補水液などのイオン飲料がおすすめです。
少し食欲が戻ってきたら、おかゆや軟飯、茶碗蒸し、野菜スープやコンソメスープ(冷まして)、うどん(柔らかく煮て、冷ましてから)、マッシュポテト(塩味やバターは控えめに)などが食べやすいでしょう。
味付けはできるだけ薄く、刺激が少ないものを選びましょう。柑橘系やトマトなどの酸味の強いもの、塩気や香辛料のある食材は避けたほうが無難です。熱すぎるものも痛みを誘発するため、冷たいか常温程度で。「少しでも口に入れられたらOK」くらいの気持ちで、無理をさせず、お子さんのペースに合わせてあげてくださいね。
Q.お風呂は入って良いですか?
元気がなかったり、ぐったりしているときは無理にお風呂に入れず、濡らしたタオルでやさしく体を拭いてあげましょう。拭く際は、水疱をつぶさないように気をつけて、肌への刺激をできるだけ避けることが大切です。
手足口病のウイルスは、唾液や鼻水のほか、水疱の中にも含まれています。お風呂に入ると皮膚が柔らかくなり、体を洗うときの摩擦などで水疱が破れやすくなることも。また、浴槽のお湯を介して感染が広がる可能性もゼロではありません。
入浴させる場合は、湯温をぬるめに設定し、湯船は家族の最後に。長湯は避け、さっと短時間で済ませるのが安心です。体調や機嫌を見ながら、シャワーで軽く流す程度でも十分清潔に保てます。
Q.家族にうつることはある?
A:あります。特に0〜1歳の兄弟や、免疫が弱い大人は注意。親もかかることがあります。大人は症状が強く出やすく、関節痛や発熱、口内炎などで辛くなることも。
予防のポイント
- 排泄物の処理後はしっかり手洗いをする
- おもちゃやタオルの共有は避ける
- 便にウイルスが2〜4週間出続けることもあるので、トイレ後も手洗い徹底する
Q.医療機関は受診すべき?
A:症状が軽ければ自宅ケアでOK。
ただし、次のような場合は受診をおすすめします。
- 高熱が続く(2〜3日以上)
- 食事・水分がとれない(脱水の兆候あり)
- 頭痛や嘔吐が続く
- 機嫌が悪く、ずっと泣いている・ぐったりしている
- 呼びかけに反応をしない
- 発疹が化膿している
合併症について(まれですが注意しましょう)
ほとんどのケースは3〜7日で自然に回復しますが、まれに以下のような重篤な合併症が報告されています。
・髄膜炎、脳炎、小脳失調症(ふらつき、歩行困難など)
・心筋炎
・急性弛緩性麻痺(手足が動かしづらくなる)
・神経原性肺水腫 など
多くの場合は軽症で済みますが、いつもと違う泣き方、呼びかけに反応しない、手足の動きがおかしい、嘔吐が続くなどの症状がある場合は、早めの受診が必要です。
Q.ナニーサービスの病児保育は利用できる?
A:はい、可能です。体調に配慮した個別対応ができます。
まだ完全に元気ではないけれど家庭でのケアが難しい…というときには、ナニーの活用もおすすめです。発熱している時は「病児対応」として、お熱が下がり、普段通りのお食事が召し上がれるまで回復されたら「通常のお世話」としてお世話にあたります。
ナニーは以下のような対応が可能です
- 保育中のご様子の観察
- お子さまの症状に応じたケア
- 家庭内の感染対策
なお、ポピンズナニーサービスでは、手足等に水疱がつぶれてしまっている部位がある場合、ガーゼ等で被覆していただくようにお願いしております。ご理解・ご協力お願いいたします。
ポピンズナニーサービスの病児・感染症対応について詳しく知りたい方は、合わせてご参照ください。
急な発熱も安心、 看護師ナニーが解説!ポピンズナニーサービスの「病児・感染症対応」とは?
おわりに:慌てず、孤立せず、チームで乗り越える

保育園に通い始めると、避けられない感染症のひとつが手足口病。
保育園からの度重なるお迎え要請に落ち込む日もあるかもしれませんが、これは子どもが免疫を育てるための“通過儀礼”のようなものです。
体調を崩したときは、無理をせず、必要に応じて医療機関やナニーサービスも活用してください。家庭の中に、“第三のチームメンバー”がいることで、育児の安心感がぐっと広がります。
あなたもナニーとして活躍してみませんか?詳しくはこちらでご紹介しています→

<参照>
厚生労働省『手足口病』
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/hfmd.html
JIHS 国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト
https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ta/hfmd/010/hfmd.html
この記事を書いた人
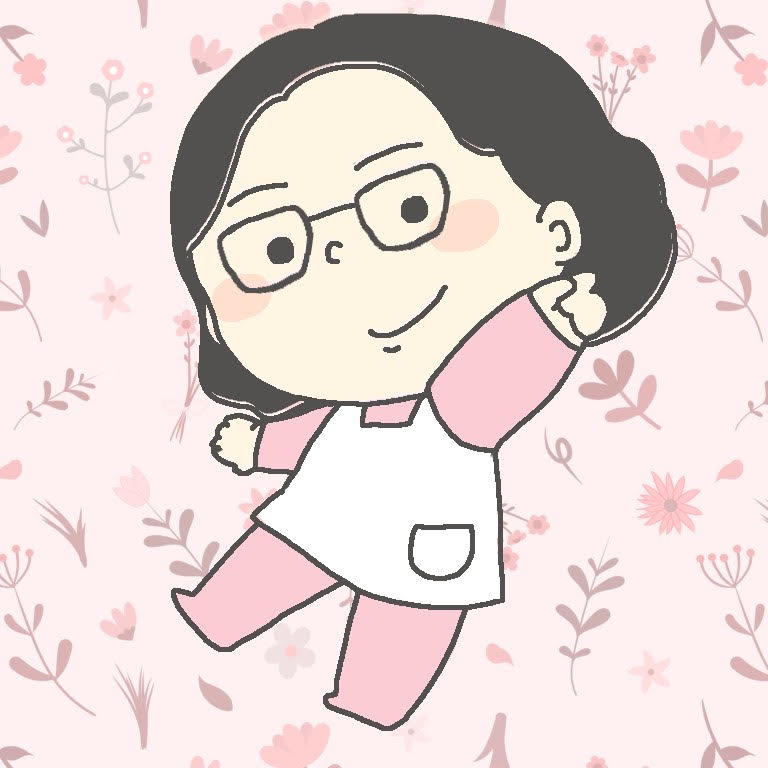
- Naoka
- 看護師、保育士、養護教諭の資格を持つナニーとして活動しています。これまで保育園や小学校、放課後デイサービスなど、さまざまな現場で経験を積んできました。現在ナニーのお仕事をしながら、療育施設にて自閉症スペクトラム症のお子さまたちの支援に取り組んでいます。



 前の記事
前の記事 次の記事
次の記事

