監修:医学博士、東京都市大学人間科学部特任教授
元聖路加国際病院小児科医長 草川 功先生
夏に流行る「ヘルパンギーナ」ってどんな病気?
梅雨から夏にかけて増えてくる、夏の三大感染症のひとつが「ヘルパンギーナ」というウイルス感染症です。名前だけは聞いたことがあっても、「手足口病とはどう違うの?」「家庭では何に気をつけたらいいの?」といった具体的な症状やケアの仕方までは、あまり知られていないことも多いでしょう。
ヘルパンギーナは突然の高熱と強いのどの痛みが特徴の、いわゆる夏風邪の一種です。特に5歳以下の子どもに多く、感染症発生動向調査では全体の90%が5歳以下とも報告されています。また、夏は暑さで体力や免疫力が落ちやすい時期でもあり、こうした感染症にかかりやすくなります。
この記事では、看護師資格を持つナニーの視点から、ヘルパンギーナについてご家族からよく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。
「ただの夏風邪でしょ」と軽く見ずに、正しい知識を持って慌てず対応できるよう、ぜひお役立てください。
Q1. ヘルパンギーナってどんな病気?
ヘルパンギーナは、コクサッキーウイルスなどのエンテロウイルス属による夏に多い感染症です。
主な症状
- 突然の高熱(38〜40℃)
- 強いのどの痛み
- 口の中(上あごやのどの奥)に小さな水疱や赤くただれた潰瘍
- 食欲不振、機嫌の悪さ、よだれが増える
2〜4日の潜伏期を経て、急に発熱と喉の痛みが出てきます。のどの粘膜にできた小さなブツブツ(水疱)が破れて痛みを感じ、食事や水分を嫌がる子どもも多いです。多くは2〜4日で熱が下がり、痛みも落ち着きます。
ただ、小さいお子さま、とくに乳児は自分で症状をうまく伝えられず、急に飲まなくなったりグズグズしたりすることも。いつも好んで飲み食べするものを「食べられない」「飲めない」ことで脱水になる可能性があります。
稀に熱性けいれんや脱水、さらに無菌性髄膜炎や心筋症といった合併症を起こすこともありますが、ほとんどは対症療法(つらい症状を和らげながら回復を待つ)で治ります。
Q2. どんなときに受診すればいいの?
基本的には自宅で安静に過ごせますが、次のようなときは医療機関の受診をおすすめします。
- 高熱が3日以上続く
- 水分が取れず、尿の回数が減っている/脱水症状が疑われる
- ぐったりしていて反応が鈍い、元気がない
- 嘔吐や下痢、頭痛などの他の症状が強い
- 呼吸が苦しそう、ゼーゼーしている
「いつもと違う」と感じたら受診をお勧めします。発熱時の受診の目安についてはこちらの記事でも解説しています→
Q3. お風呂に入ってもいい?
熱があったり、ぐったりしているときはお風呂は控えましょう。元気が戻ってきたら、ぬるめのシャワーでさっと汗を流す程度がおすすめです。
口の中の水疱や潰瘍が熱いお湯や湯気で刺激されて痛がることもあります。その場合は、清潔なタオルで優しく体を拭いてあげるだけでも十分です。
Q4. 口の中が痛そう…何を食べさせたらいい?
「食べない」「飲めない」は、ご家族にとって一番心配ですよね。痛くて嫌がるときは無理に食べさせず、水分補給を最優先にしましょう。
何を選ぶか迷ったら「自分が口内炎のとき、何を食べたいか」で考えてみてください。まずは冷たくて、のどごしの良いものを少量ずつ与えてみましょう。特に病気の時こそ栄養価の高い果物を食べてもらいたいかもしれませんが、痛みを助長させてしまう可能性があるので、避けるのが無難です。
例)
・ゼリー、プリン、アイスクリーム(バニラがおすすめです)
・ポカリスエットや経口補水液(OS-1)、麦茶、白湯
・冷ましたおかゆや、くたくたに煮たうどん
酸味のある果物や熱いもの、塩分や酸味が強いもの、固いものは避けましょう。
Q5. 兄弟や家族にうつりますか?
ヘルパンギーナは飛沫(くしゃみ・咳)や便から手指を介しての接触でうつります。家庭内でも広がりやすいので、特に小さい兄弟がいる場合は注意が必要です。
- こまめな手洗い(石けん+流水)
- トイレやおむつ交換後の手洗い
- うがい
- おもちゃやドアノブの消毒
発症から1週間程度は感染力があり、便には2〜4週間ウイルスが残ることがあります。特にトイレの後の手洗いはしっかりと行いましょう。
Q6. 登園の目安は?いつから保育園に行ける?
ヘルパンギーナは学校保健安全法の「第三種学校感染病」に分類されており、インフルエンザのような出席停止期間は存在しません。ただし園によっては医師の診断書や登園許可証が求められることもあります。園ごとに異なるため、事前に確認しましょう。
全身状態が回復し、普段通り食べたり遊んだりできるようになったら登園をしましょう。
なお、登園の目安は、発熱や喉の痛みといった症状がおさまり、全身状態が回復していることです。具体的には食事や水分がしっかりと取れ、機嫌良く過ごせるようになった頃が目安になります。
看護師ナニーより:家庭でのケアと頼れるサポートについて

ヘルパンギーナは子どもによく見られる夏の感染症ですが、突然の高熱やぐったりした様子に不安になるご家族も多いでしょう。特に乳児では食べたり飲んだりしないことが続くと不安はさらに大きくなります。
“夏風邪の波が来てから”ではなく、“波が来る前”に、ご家庭のスタイルに合った支援を検討しておくのがおすすめです。
なかでも、自宅で安心してお子さまを預けられるポピンズナニーサービスは、心強い選択肢のひとつです。ポピンズナニーサービスでは、病児ケアについて看護師や救急対応の専門家から直接学べる研修を用意しています。だからこそ、お子様の急な発熱や不調にも落ち着いて対応し、ご家庭をしっかりと支えることができるのです。
ヘルパンギーナの際には、病児対応としてお子様をお世話しながら、安心して回復を待てる環境を整えます。ご家族に代わりお子さまのそばで寄り添い、また万が一のときには会社と連携して迅速かつ冷静に判断を行うため、ご家族にとっても心強い存在となるでしょう。
ポピンズナニーサービスの病児・感染症対応サービスの詳細やご利用の流れについては、以下の記事もぜひご覧ください→
ナニーはお子さまの様子を見ながら、ご家庭に寄り添ったケアをご提供します。一人で抱え込まず、「頼れる選択肢」を増やしておきましょう。
お子さまに関わる仕事「ナニー」にご興味はありませんか?現在ナニーを募集しています。詳しくはこちらをご覧ください→

<参考>
この記事を書いた人
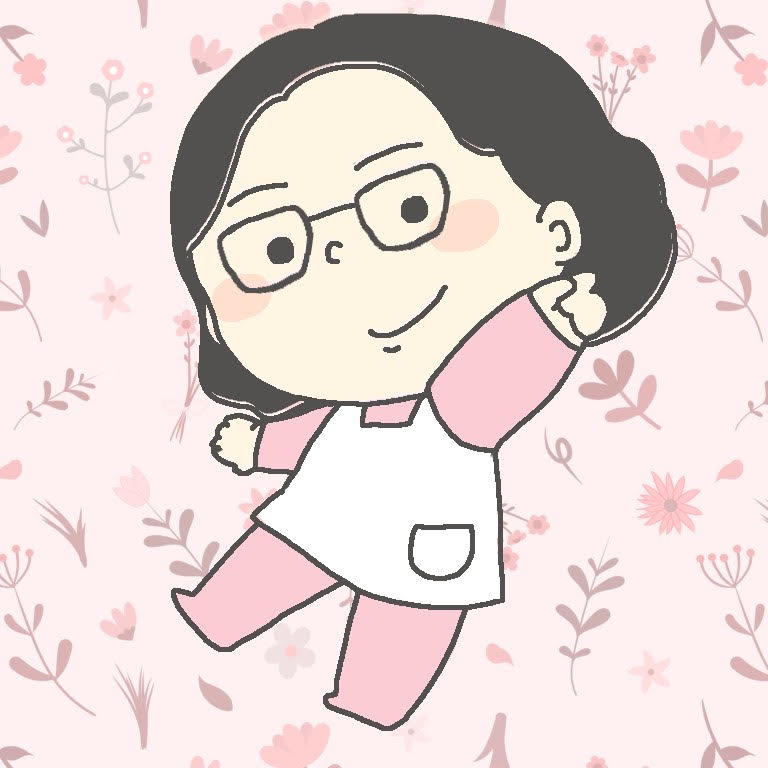
- Naoka
- 看護師、保育士、養護教諭の資格を持つナニーとして活動しています。これまで保育園や小学校、放課後デイサービスなど、さまざまな現場で経験を積んできました。現在ナニーのお仕事をしながら、療育施設にて自閉症スペクトラム症のお子さまたちの支援に取り組んでいます。



 前の記事
前の記事 次の記事
次の記事

