あれもイヤ!これもイヤ!
そういう時期だと分かってはいても、お子様の気持ちに寄り添うのは大変ですよね。数々発せられる「イヤイヤ」を叱りすぎては後悔し、許しすぎては「このままでいいのか」と悶々としているのではないでしょうか。
イヤイヤ期は一般的に1歳前後から始まり、2歳頃にピークを迎え、3〜4歳にかけてだんだん落ち着いてくるといわれています。私もナニーとしてイヤイヤ期のお子様にたくさん接して参りました。何でも自分でやりたくなりますが、思ったように出来ないジレンマから、泣いたり、目の前のことは何でも「イヤだ!」と拒否したりします。
そんな時、イヤイヤ期のお子様にナニーとしてどんなお声かけをしているのか、そして心掛けていることをお伝えします。
「いけない」と伝える必要性
やっていいこと、いけないことを伝える必要がある
子どもは年齢が低いほど、やっていいことといけないことの区別がつきません。例えば興味本位でやったことで、結果として人に迷惑をかけたときに、それはやってはいけないんだよ、ということを伝えていかなければ、子どもはやっていいことといけないことのけじめがつかなくなってしまいます。間髪入れずに「それはいけないことなんだよ」と伝えることが「叱る」ということであり、しつけです。ただし、ねちねちとしつこく叱るのではなく、必要な時に簡潔にきちんと伝えることが大切です。
ナニーと、ふざけっこをしている時、お子様が興奮してナニーの背中や頭を笑いながら叩くことがあります。その時ナニーは「痛かったなー」と伝えます。お子様は「叩く」ことも遊びの一つとしてされるのですが、叩かれた人は「痛いこと」、「嫌な思いをしている」ということを理解してもらいます。人を叩くという行為は、やってはいけないことであり、相手が嫌なことをしたら「ごめんなさい」と謝ることを優しく伝えます。
大切なことを伝えるために叱る
「叱る」ということは、世の中のルールや規則、何が大切なのかという価値についてしっかり伝えるということです。「叱られる」ことのない子どもは学ぶことが出来ません。ただし、叱るときに力で押さえつけたり怒鳴ることはせず、子どもが納得できるようにわかりやすい言葉で伝えることが大切です。「叱る」と「怒る」は違います。「怒る」は自分のために、感情を発散する行為です。「怒られるからやめる」のではなく、自分で良い悪いを考えて行動出来るように伝えましょう。
子どもを叱るべき場面と具体例
身の危険がある時
- 道路に飛び出す
- 料理中の鍋に触る
人を傷つける恐れがある時
- お友達を叩く、噛む
- 人を傷つける言葉を言う
家や社会のルールに反する時
- 病院で騒ぐ
- 「いただきます」を言わずにご飯を食べ始める
お子様に正しいことをお伝えするのもナニーの大切な仕事です。いつも笑顔のナニーが毅然とした態度で注意したり、叱る意図をお伝えしたりすることで、お子様も真剣な顔で受け止めて下さることが多いです。
イヤイヤ期の子どもに伝わる年齢別叱り方のポイント
0〜1歳半頃
叱るときの言葉は一語二語
「いたいいたい」「いけないよ」という言葉をその場で伝えたり、「えーんえんしちゃうよ」などの擬態語や擬声語を使ったりすると伝わりやすいです。
私はジェスチャーを交えながら、わかりやすく伝わるよう心掛けております。
1歳半〜2歳頃
叱るときの言葉は二語文、三語文
叱るときは、短い文章にすると伝わりやすいです。
例えば、友達のおもちゃを取り上げてしまったときには、
「これはお友達の。返そうね。」というように短い文章で伝えましょう。また、この時期になると子どもには自我が芽生え、自分の思いが強くなります。一回でいうことをきかせようと思わずに、根気よく伝えましょう。子どもが親のいうことをきくようになるには、子ども自身の理解力も必要です。また同じことで叱っていると悩む必要もないのです。この時期の子どもは、ぐんぐん成長するので長い目で成長を見守ります。
3歳頃
子どもがイメージできるよう具体的に叱る
個人差はありますが、言葉が指すものや物の性質が理解出来るようになっているため、子どもがイメージできるように具体的に伝えてあげましょう。
例えば、お砂場遊びでシャベルで砂をすくい、砂を投げてしまう事があります。お子様は砂が舞い散るのが面白くてやるようです。しかし、それは砂が目に入り痛くなる危険な行為であることを伝えなければいけません。お声かけとして「投げると砂が目に入って痛くなるからやめようね」
「投げたお砂が周りのお友達にかかって嫌だと思うよ」となぜダメなのか、理由をわかりやすく伝えるようにしております。
子どもに叱ったことが伝わっているかを見極めるポイント

子どもの仕草や表情を見てください。叱った後に「ごめんなさい」と言葉では言えないけれど
- ちょっと手を止めている
- ちょっと下を向いている
- 笑っているけれどチラチラとママの様子を伺うようにする
というように、子どもの態度の変化を見てください。子どもをよく見て叱ったことが伝わっているのかを見極めましょう。叱った後に、必ずしも「ごめんなさい」と言わせる必要はなく、心の変化があるかどうかが大切です。
NGな叱り方とは
叱ることは子どもにとってメリットがある一方、叱り方によっては将来に渡って悪影響を及ぼす恐れもあります。
暴力を用いる
叱る際に暴力を使うのは許されることではありません。
また、幼児期に体罰を受けた子どもは精神的な問題を持ったり、攻撃性が高くなったりするリスクがあると指摘されています。このように暴力を使って叱ることは、デメリットしかないのです。
無視する
子どもが失敗した際に無視する方法にも問題があります。
親に無視された子どもは、自分自身も親や友達を無視したり、他人の顔色をうかがったりするようになる可能性があるからです。
人格を否定する
人格を否定する叱り方とは、「あなたはいつも失敗するわね」「ばかじゃないの」など、子ども自身の人間性を否定する叱り方のことです。このような叱り方は子どもの自己肯定感を下げる原因となり、自信ややる気を奪う原因となってしまいます。叱る対象は子どもの行動に限定し、子ども自身を叱らないようにしましょう。
脅す
「いい子にしてないとおやつあげないよ」と言ったり、鬼や怖い人から電話がかかってくるアプリを利用したりするなど、脅しで子どもを従わせる叱り方も、おすすめできません。「怖いから」という理由で指示に従ってやり過ごしているだけです。叱られている理由は分からないままになってしまいます。また恐怖心で押さえつけることで、子どもの健全な成長や自立の機会を奪うことにもつながります。叱る際は脅すのではなく、叱っている理由をきちんと伝えましょう。
お世話中にしているナニーのお声がけ

ナニーとしてお世話をしている時にもお子様に「いけないよ」と伝えなければいけないシーンは度々あります。その時、一番大切にしているのは、まずお子様の気持ちを受け止め、寄り添うことです。お子様の気持ちを否定せず、なぜそうしたのか行動の理由を考えます。
例えば「お友達を叩いたのは一緒に遊んで欲しかったから」「ガラスの破片を触ろうとしたのは、キラキラしていて綺麗だったから」など子どもの行動にも理由があるものです。注意する前に「一緒に遊びたかったんだね」「綺麗だから触りたかったんだね」と、まずは子どもの気持ちを肯定するよう心掛けています。その後で「叩くとお友達がケガしちゃうよ」「ガラスの破片は手を切るから危ないんだよ」などと伝えます。
先に気持ちを肯定するとお子様にその後の話が伝わりやすくなります。そして、その時は必ず目線を合わせ、お子様の目を見てどれだけ大切なことを伝えているか知らせます。そして、その後にお子様が改善できた場合は必ず褒めます。褒めることで、お子様は自信をつけ、「次もやろう!」という意欲を持てるからです。「叱る」と「褒める」を組み合わせることで、さらなる効果を発揮するのです。
一人ひとりに個性があり、その子に合った叱り方があります。本質は同じですが一人ひとりの個性を丁寧に見極めて寄り添い、ご成長を感じる時がナニーの仕事の大きな喜びです。
一人ひとりのお子様に丁寧に関わることが出来るナニーのお仕事を始めてみませんか。興味を持たれた方はこちらをご覧ください→

この記事を書いた人
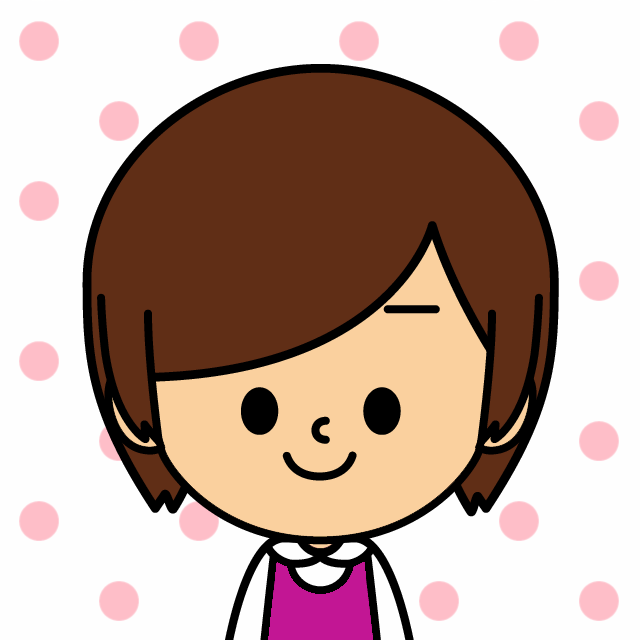
- ハタノケイコ
- 大学にて幼児教育を学び幼稚園教諭ニ種取得。 卒業後は大手百貨店に就職し接客について学ぶ。 児童館での読み聞かせボランティアをきっかけに再び保育の仕事へ。 40代でポピンズに入社し様々な保育現場で仕事をしながら保育士資格取得。 10年の経験と自身の子育てから感じた事を記事に書いて発信中。



 前の記事
前の記事 次の記事
次の記事

