冬が近づき、インフルエンザの季節がやってきます。「どうしたら子どもをインフルエンザから守れるのか」「もし感染してしまったら…」と不安を感じている方も多いでしょう。この記事では、インフルエンザの予防と対策について、看護師ナニーが知っておくべき大切なポイントをご紹介します。
contents
インフルエンザってどんな病気?
インフルエンザは、インフルエンザウイルスが原因の感染症です。ウイルスにはA型とB型があり、その年によって流行が変わります。一度インフルエンザにかかっても、免疫がつくことはないので、何度でもかかってしまいます。
一般的な風邪よりも症状が強く、特に小さなお子さまの場合、発熱やだるさ、食欲不振など、つらい症状が出やすいのが特徴です。
また、感染力も非常に強いため、学校や会社など集団単位であっという間に感染が広がるのが特徴です。
どんな症状が出るの?
主な症状としては、まず38度以上の発熱、関節や筋肉の痛み、だるさと頭痛があります。やや遅れて咳や鼻水、場合によっては下痢があらわれます。他の風邪よりも強く全身症状があらわれます。症状は2〜3日で落ち着きますが、場合によっては1週間近く長引くこともあります。
中耳炎や気管支炎、肺炎を引き起こすケースもありますので、咳が悪化したり、発熱が持続したりする場合は気をつけましょう。もしお子さまがぐったりとしていたり、いつもより元気がなかったり、意識が朦朧としているようでしたら、無理せず医療機関の受診を検討しましょう。
「熱せん妄」が出る場合があります
発熱をしている期間はお子さまを一人にせず、大人が見守りをするようにしましょう。なぜならば、お子さまには高熱が出た際に、一時的に異常な行動や言動が見られる場合があるからです。ほとんどが短時間で収まりますが、万が一長時間そのような状態が続いたり、痙攣を起こすようなことがあればすぐに医療機関の受診をしましょう。
今年のインフルエンザの流行状況が知りたい
国立感染症研究所が随時、インフルエンザの発生動向に関して発表をしています。詳しくはホームページでご確認ください。
インフルエンザを防ぐためにできること
予防策をしっかり知っておけば、いざというときに落ち着いて対応できるかもしれません。インフルエンザの感染は、飛沫感染と接触感染が主な経路です。お子さまに優しく教えて、一緒に予防策を習慣化できると良いでしょう。
飛沫感染:患者のくしゃみや咳などで唾液や鼻水が小さな水滴となって飛び散り、それを吸い込むことによって感染します。
接触感染:患者がウイルスのついた手でドアノブや吊り革に触れると、ウイルスが付着し、そこに他人が触れ、その手で自分の口や鼻に触ることで感染します。
①手洗いやうがいをこまめに、外から家庭内にウイルスを持ちこまない
特に外出から帰ったときは、石けんでしっかり手を洗い、うがいをする習慣をつけましょう。小さなお子さまには楽しい歌を歌いながら手洗いをすると、忘れずにできることが多いです。
②マスクと加湿、換気でウイルス対策
手洗いに加えて、マスクの着用も感染予防に効果的です。人混みに出かけるときは、マスクをしっかり着用し、感染を防ぎましょう。
また、インフルエンザウイルスは高温多湿な環境が苦手です。室内の湿度を50〜60%に保つために、加湿器を使うのがおすすめです。ご自宅に加湿器がない場合は、濡れタオルを置くなどの工夫でも十分効果があります。
さらに、ウイルス対策にはこまめな換気が欠かせません。厚生労働省では、換気の目安として「30分に1回以上、数分程度窓を全開にする」や「二方向の窓を開けて風通しを良くする」といった方法を推奨しています。ただし、インフルエンザの流行時期は冬で、窓を開けると寒さを感じることもありますよね。そこで、午前と午後に1回ずつ換気する、わずかに窓を開けて常に空気を入れ替える、といった方法もおすすめです。
③規則正しい生活リズムを心がけましょう
不規則な生活リズムによって体力が落ちていたり、疲れていると免疫力が低下し、インフルエンザにかかりやすくなります。規則正しい生活リズムを心がけ、栄養バランスの取れた食事と十分な睡眠をとりましょう。
予防接種で感染と重症化を防ぐ

インフルエンザの予防接種は、感染と重症化を防ぐための大切な手段です。「ワクチンを打つと本当に効果があるの?」と疑問を持つ方もいるかもしれませんが、接種によって感染リスクが減り、万が一かかっても症状が軽く済むケースが多く、重症化を予防できます。
お子さま向けの接種スケジュール
インフルエンザの予防接種は、10月から11月にかけて受けるのが理想的です。個人差はありますが、ワクチンは接種後2週間以上経過してから効果が発揮されるため、インフルエンザが流行し始める12月ごろから逆算して、11月中には1回目の接種を済ませておきましょう。
生後6か月から12歳までのお子さまは原則2回接種が必要で、1回目と2回目の間隔を4週間あけることが推奨されています。13歳以上は1〜2回とされています。接種から効果が出るまで2週間ほどかかるため、できるだけ早めに予定を立てましょう。
2024年現在では、医師が必要と認めた場合には、他のワクチンと同時に摂取をすることができます。
乳児のいる家庭では、親や兄弟が接種をすることで、乳児への感染のリスクを下げることができます。
接種適応年齢
厚生労働省並びに日本小児科学会は、生後6ヶ月以降の摂取を推奨しています。免疫は生後6ヶ月以降落ちるからです。兄弟児がいる場合は、幼稚園・保育園・学校でもらってくるケースが多く、0歳より保育園に在籍している乳幼児は集団感染のリスクが高くあります。また、6ヶ月より前に感染をすると、うまく抗体を作れないことから、重症化のリスクもあるためです。
接種費用と助成制度について
予防接種は通常、1回2,000~4,000円程度の自費負担が必要ですが、自治体によっては子どもへの費用助成がある場合もあります。お住まいの自治体のホームページや保健センターで、助成制度がないか確認してみてください。
もしお子さまがインフルエンザにかかってしまったら
インフルエンザにかかってしまった場合、「子どもがつらそうで、どうしてあげればいいのかわからない…」と不安になってしまうこともあると思います。まずは、できるだけ安静にさせて、少しでもお子さまが楽に過ごせるようなケアを心がけましょう。
看護師ナニーとしてのケアのポイント
①安静と水分補給
インフルエンザにかかると体がだるく、食欲も落ちやすいです。脱水症状を防ぐためにも、こまめに水分をとらせてあげてください。無理に食べさせる必要はありませんが、少しずつでも水分を摂れるようにしましょう。おしっこが半日以上でない場合は脱水症を起こしている場合がありますので、医療機関を受診しましょう。
病院で内服薬が処方された場合は、用法・用量を守り、適切に使用をしましょう。
②部屋の換気と湿度管理
部屋の空気が乾燥すると、呼吸がしづらくなります。加湿器や濡れタオルなどを使って湿度を保ち、時々換気して、空気を入れ替えましょう。
③医療機関に相談するタイミング
高熱が続く場合や、呼吸が苦しそうな様子が見られるときは、早めに医療機関を受診するようにしましょう。特に、小さなお子さまは症状が急激に悪化することもあるため、「いつもと違うな」と感じたら、かかりつけ医に相談することをおすすめします。
インフルエンザが治った後も気をつけてあげてください
インフルエンザから回復しても、しばらくは体力が落ちていることがあります。しっかりと休養を取り、日常生活に無理なく戻るようサポートしましょう。
元気になった後の注意点
①再感染に注意
インフルエンザには複数の型があるため、流行期が終わるまでは引き続き予防を心がけましょう。
②ゆっくり元の生活に戻す
体が完全に回復するまで、少しずつ普段の生活リズムに戻るようにしましょう。特に無理をしてしまうと体力が落ち、再び体調を崩しやすくなります。
登園の目安
・熱が出てから5日間が経過していること
・熱が下がって2日(乳幼児は3日)が経過していること
この二点をクリアしていたら登園可能です。登園許可書が必要な場合はかかりつけ医でもらいましょう。
「経鼻弱毒生インフルエンザワクチン」が始まりました
2024年から、2歳以上19歳未満のお子様を対象に、経鼻弱毒生インフルエンザワクチンが利用できるようになりました。このワクチンは従来の注射とは異なり、鼻の中にスプレーを吹きかけるだけで接種が完了するため、痛みがありません。さらに、1シーズンに1回の接種で済むのも特徴です。
現在のところ、従来の注射型ワクチンと経鼻ワクチンの間で、安全性や有効性に大きな違いはないと報告されています。ただし、費用は自己負担となり、8,000〜9,000円程度かかる場合があります。自治体や加入している保険組合によっては助成や補助金が適用される場合もありますので、事前に確認することをおすすめします。
また、このワクチンはすべての小児科で取り扱われているわけではありません。接種を希望される場合は、まずかかりつけの小児科に相談してみてください。
まとめ

インフルエンザは、子どもにとっても親にとっても心配な病気です。ですが、日頃から手洗い・うがい、予防接種、家庭での換気や湿度管理をしっかり行うことで、リスクを少しでも減らすことができます。お子さまがインフルエンザにかかったときには、不安な気持ちを抱えながらも、できるだけそばで見守り、安心して過ごせるようにサポートしてあげましょう。
「子どもが少しでも楽になるように」と心を込めてケアをすることが、お子さまの安心感にもつながります。ぜひこの冬を乗り越えるために、できることから始めてみてくださいね。

この記事を書いた人
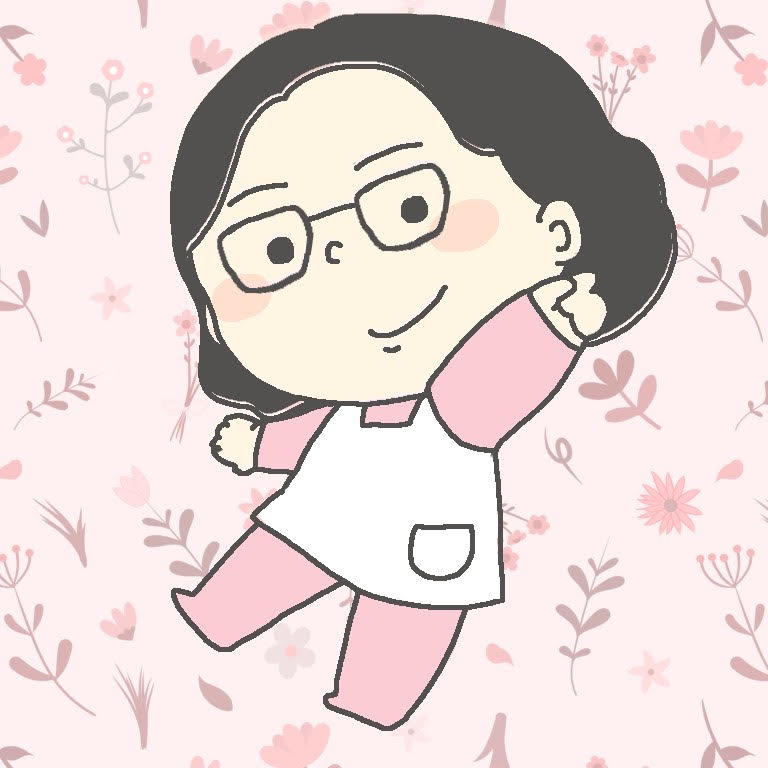
- Naoka
- 看護師、保育士、養護教諭の資格を持つナニーとして活動しています。これまで保育園や小学校、放課後デイサービスなど、さまざまな現場で経験を積んできました。現在ナニーのお仕事をしながら、療育施設にて自閉症スペクトラム症のお子さまたちの支援に取り組んでいます。



 前の記事
前の記事 次の記事
次の記事

