子どもは日々の生活の中で、親子のやりとりを通して言葉を学びます。今回の記事では、家庭で簡単にできる子どもの言葉を引き出し、コミュニケーションの土台をつくる具体的な方法をお伝えします。
コミュニケーションの基礎を築く意義
親子の対話は、生まれてすぐに始まります。泣き声に応える親の反応を通して、子どもは「自分の声が他者に影響を与える」という経験をします。これが、表情、声のトーン、ジェスチャー、そして言葉へと発展していくのです。
子どもが日常で興味を示したことについて、親が意識的に言葉をかけると、自然にコミュニケーションの芽が育ちます。お子様が話したいことを尊重する姿勢が、豊かなコミュニケーション力を育む鍵です。
親子の対話を引き出すための具体的なアプローチ
(1) 早期からの話しかけの重要性
赤ちゃんの頃から話しかけることは、親子の対話を深める第一歩です。おむつ替えや授乳のとき、散歩中に見かけるものについて話すなど、日常生活にコミュニケーションの機会はたくさんあります。お子様の視線や反応に合わせて、丁寧に話しかけてみましょう。
また、質問を投げかけることで、子どもが自分の知っていることや感じたことを伝える意欲が高まります。「これ、何かな?」と問いかけることで、考える力も養われます。
(2) 身振り手振りと一緒に伝える
言葉だけでなく、ジェスチャーを使って伝えることで、子どもの理解が深まります。指差しや視線を交わしながら「これを見てみて」と伝えると、子どもが理解しやすくなるだけでなく、コミュニケーションへの興味も引き出されます。
(3) コミュニケーションの基礎となる「社会的随伴性」「アイコンタクト」「共同注意」
コミュニケーションの発達には、ことばを学ぶ以前に、目を合わせたり、相手の反応を感じ取ったりする「社会的随伴性」が非常に大切です。これには、「アイコンタクト( 視線への反応)」や「共同注意」が大きく関わっています。
社会的随伴性:親が子どもの行動や発話に反応することで、子どもは「自分の行動が他者に影響を与える」という経験を通じて、コミュニケーションの基本を学びます。たとえば、子どもが笑うと親が笑い返す、子どもが声を出すと親が応じることが重要です。
アイコンタクト(視線への反応):親が子どもと目を合わせることで、子どもはコミュニケーションのやり取りが始まることを理解します。赤ちゃんが親の目をじっと見つめ、親が笑顔で応えることで、お互いの反応に基づいたやり取りが成立します。
共同注意:大人と子どもが同じ対象物(物)に注意(視線)を向け、その対象についてやり取りをすることで、子どもが言語や概念を学ぶプロセスです。
赤ちゃんは生後2ヶ月頃から、自分と相手、自分と物という二項関係を理解します。そして9~10ヶ月頃になると、赤ちゃんは人と物のどちらにも注目できるようになります。たとえば、子どもが指差したものを親が一緒に見て「あれは○○だね」と言葉で説明することで、子どもは物事とことばを関連付けて理解します。このように、親と子どもが共通の話題に注目することが、言葉の習得に繋がります。
たとえば、公園を歩いているときに母親が犬を見つけ、「わんわんだね」と言いながらその犬を見つめます。すると、子どもは母親の視線の先に犬がいることに気づき、その犬が「わんわん」と呼ばれていることを理解します。この一連のやり取りの中で、子どもは「わんわん」という言葉が犬を指す名前であることを学びます。
このプロセスでは、単に言葉を聞くだけではなく、母親の視線や表情、言葉の意味を一緒に読み取ることが重要です。母親が犬を見ていることに気づき、その対象に興味を持つことで、子どもは「わんわん」という言葉とその意味を結びつけ、理解を深めます。このように、言語発達の土台となる「共同注意」は、親子の視線の共有や心のやり取りを通して成り立ち、言葉を学ぶきっかけを生み出します。
このような日常の何気ない瞬間が、実はお子様の言語やコミュニケーションの発達にとって非常に重要な役割を果たしているのです。
(4)「待つ」ことの大切さ
話しかけた後、お子様が考える時間を「待つ」ことも大切です。すぐに答えを促すのではなく、子どもが自分の思いを言葉にする時間を大切にすることで、考える力が育まれます。
親子の対話で気をつけたいポイント

(1) ポジティブなフィードバックを与える
子どもが話そうとしたときには、その努力を認め、「よく話せたね」「上手に伝えられたね」といった肯定的なフィードバックを与えましょう。肯定されることで、お子様はさらに積極的に言葉で表現しようとするようになります。
(2) 新しい表現へのチャレンジ
少し難しい表現や新しい単語を使って話しかけることで、お子様の表現力を自然に引き出すことができます。たとえば、「くるまだね」から「赤いくるまだね」と表現を増やしてみましょう。
(3) スクリーンタイムに気をつける
テレビやスマートフォンを見る機会が多い現代ですが、親子で対話を楽しむことが、言葉の習得にはより効果的です。できる限り一緒に話をする時間を大切にしてみましょう。
親子の対話を支える家庭環境づくり
家庭内で自由に会話ができる環境は、子どもが安心して気持ちを表現できる場になります。日々の忙しい時間の中でも、少しの時間で構いませんので、家族で一緒に話をする時間を意識的に作るようにしてみましょう。
まとめ

お子様のコミュニケーションの発達は、日々の親子のやり取りを通じて少しずつ育まれます。親が意識的にお子様の関心に応え、日常の何気ない瞬間を通して、アイコンタクトや社会的随伴性、共同注意といったやり取りの基礎を築いていくことが、豊かな対話力の基礎となります。
日常の関わりを通じて、親子の絆が深まり、お子様が自分の言葉で世界を表現する力が育まれることでしょう。次回は「聞く力」を育むための方法についてお伝えしますので、どうぞお楽しみに。

この記事を書いた人
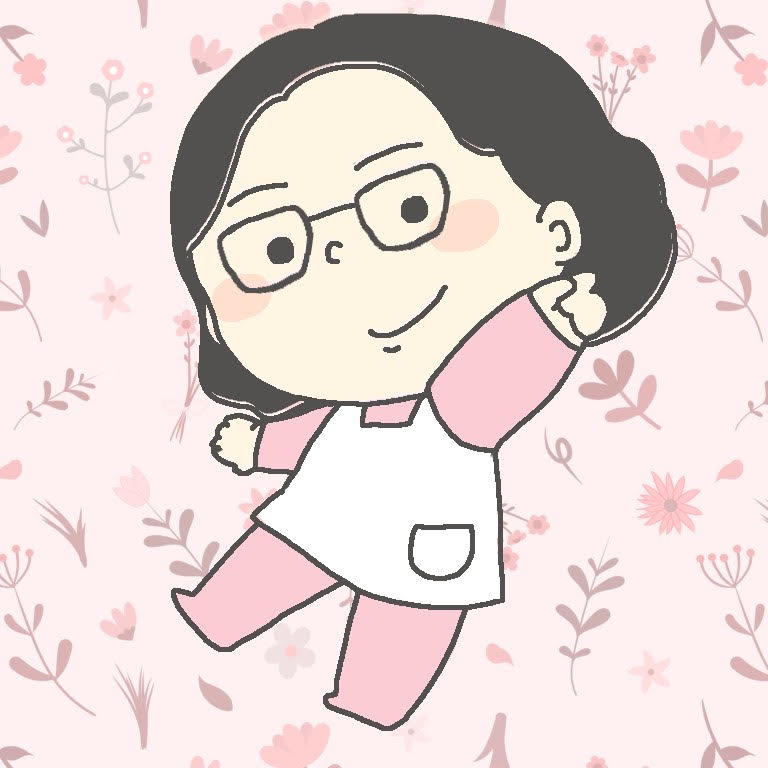
- Naoka
- 看護師、保育士、養護教諭の資格を持つナニーとして活動しています。これまで保育園や小学校、放課後デイサービスなど、さまざまな現場で経験を積んできました。現在ナニーのお仕事をしながら、療育施設にて自閉症スペクトラム症のお子さまたちの支援に取り組んでいます。



 前の記事
前の記事 次の記事
次の記事

