1歳から5歳までの幼児期は、体の成長はもちろん、脳や味覚も発達し、将来の食習慣を決めるとても大切な時期です。
ある程度の固さのものを食べられるようになってきたら離乳食は卒業して幼児食をスタートしましょう!
子どもの成長に合わせた幼児食で、噛む力や味覚、食への興味を育てよう
1歳6ヶ月頃になって、肉だんごくらいの固さのものを、もぐもぐと口を動かして食べられるようになれば、幼児食を始めても良い時期です。とは言っても大人と比べると、噛む力は、まだ弱く、消化器官も未発達です。大人と同じでは、噛む力が育ちにくく、まる飲みするなど悪習慣がついてしまうことが懸念されます。よく噛んで食べられるように、食材の切り方や調理法を工夫して、5歳くらいまでは歯や体の発達に合わせた幼児食を与えましょう。
また、この頃は味覚のベースをつくる大切な時期です。大人と同じ味つけにすると、濃い味に慣れてしまい味覚が正しく育たない、塩分が多く消化器官に負担がかかるなどの心配もあります。ナニーとして食事介助をする時も、なかなか食が進まないお子様もいらっしゃいます。お母様のご指示のもと、市販のケチャップやマヨネーズを添えると食は進みますが習慣にならないようアクセント程度に抑えるのがおすすめです。
1歳児の幼児食
歯ぐきで押しつぶせるくらいの大きさ、固さのメニューで、噛む練習を始めましょう。個人差はありますが、上下の前歯8本が生える時期です。初めは前歯でかじり取り、歯ぐきで押しつぶせるくらいの大きさ、固さの食べ物にしましょう。
繊維質が多い肉や野菜(芋類、青菜類など)は、噛み切れずに喉に詰まることがあるので、細かく切ったり煮込んだりして、食べやすいように調理しましょう。
<調理の工夫>
- 魚類 切り身は骨や皮を取り除く。片栗粉や小麦粉をまぶしてフライパンでソテーすると身がふっくら、やわらかく焼けます。
- 肉類 固くならないよう、ひき肉料理は卵やパン粉などのつなぎを多めに使う。薄切り肉は1㎝幅くらいの細切りや角切りに。
- 野菜 葉野菜は1〜2㎝幅。根菜は5㎝くらいのスティック状に。
<ストレスなく進めるコツと注意点>
「自分でやりたい!」という自我が芽生える時期です。親子でストレスなく過ごせるよう手づかみ食べしやすいメニューを選び、子どもの気持ちを尊重しましょう。噛む力や消化力は個人差があるので、まる飲みしていないか、一口の量が多すぎないか見守りましょう。
●手づかみ食べが子どもの成長に与えるメリット
手づかみ食べは、目、手、口の協調運動を促し、自分で上手に食べられるようになるまでの大切なプロセスです。子どもの意欲を引き出して、楽しく食べることにも繋がります。食べものを手で口に運ぶ練習を重ねることで、手指の動きや握り方のコントロールが上手になり、スプーンやフォーク、箸などをスムーズに使えるようになるほか、一口量を覚えることで詰め込み過ぎや、丸のみの予防にもなります。
2歳児の幼児食
奥歯が徐々に生えそろう時期。食感の異なる食材で、噛む力を育てましょう。個人差はありますが第2乳臼歯が生え始め、2歳のうちにすべての乳歯がほぼ生えそろう時期です。噛む力が強くなり、食べられるものの種類がぐんと広がります。とはいえ、まだ口が小さく、消化器官も完全ではないので、大人と同じ切り方や加熱具合では食べづらいこともあります。もう食べられると思って無理に与えると好き嫌いの原因になることもあるので注意が必要です。
<調理の工夫>
- 魚類 魚の切り身は骨や皮を取り除く。2~3㎝の厚さの削ぎ切りにしてあげると、フォークで刺して食べやすくなります。
- 肉類 薄切り肉は繊維を断ち切るように、1~2㎝の細切りに。
- 野菜 葉野菜は、葉の部分は3㎝ぐらい、茎の部分は2㎝くらいの細切りに。根菜はやわらかく加熱すれば乱切りなどでも大丈夫です。
<ストレスなく進めるコツと注意点>
手づかみ食べと並行して、スプーン、フォークを使って食べられるようになります。うまく食べれない時は大人がサポートしてあげましょう。自我の発達にともない、食事中に立ち歩いたり、食べ物で遊んだり、なかなか大人のペースで食事をしてくれないことが増える時期でもあります。そんな時は、いったん食事を切り上げる、遊びに区切りがつきそうなところで食事に誘うなど食事と遊びのけじめをつけられる工夫を取り入れてみましょう。
●スプーン、フォーク食べが子どもの成長に与えるメリット
手づかみ食べ同様、自分で上手に、楽しく食べる力を育みます。スプーンですくうことはテクニックが必要で、始めは上手に出来ないので、練習する必要があります。フォークはさしたり、麺類をひっかけたりする際に使うので、スプーンと一緒に用意しておき、メニューによって使い分けて練習しましょう。スプーンもフォークもお箸を上手に持つために必要な手の動きの発達を促します。
3〜5歳児の幼児食
乳歯が生えそろい、ほぼ大人と同じものが食べられるようになります。ただし食材の大きさ、固さに気をつけましょう。この頃になると、多くのお子さんが20本の乳歯が生えそろいます。「もう何でも食べられるかな?」と思いがちですが、大人の歯と比べて面積が小さく、本数も少ないので、大人と同じように噛むのはまだまだ難しい時期です。子どもの食べる様子を見ながら、食材の切り方、加熱具合、固さなどを調節しましょう。
<調理の工夫>
- 魚類 焼き魚など、たいていのものは食べられるようになります。いか、たこなど弾力のあるものは食べやすく刻みましょう。生食や塩分の多いものは避けましょう。
- 肉類 固まり肉も食べられるようになります。鶏肉なら3㎝角くらい。豚肉、牛肉などは加熱後に薄く切りましょう。
- 野菜 葉野菜は、やわらかく加熱すれば、茎も葉も3㎝幅でよいでしょう。根菜は、短冊切り、せん切りなどいろいろな大きさにしてみましょう。
<ストレスなく進めるコツと注意点>
スプーンやフォークで食べるのが上手になってきたら、様子を見てお箸デビューです。子ども用の矯正箸を使ってみましょう。お気に入りのデザインなら、やる気もアップします!お箸を上手く使えないと嫌がるお子様もいますが、出来た時にほめると使うのが楽しくなるでしょう。
●お箸の練習の目安
お箸は手指の高度な動きが必要となるので、スプーン、フォークが上手に使えて、鉛筆で線などを書けるようになってから使い始めます。個人差がありますが、上手に使えるようになるのはおおむね4、5歳ごろ。小学校に入学するまでに完成することが目標なので、焦らずゆっくり進めましょう。

年齢別 食べないお悩み解決策
- 0〜1歳 固さや大きさを変えると食べるお子様も多いです。離乳食の時期には食べられない場合はあまり悩みすぎず、時間をおいて再挑戦するのもおすすめです。
- 2歳〜3歳 食事が作られる過程を見ること、材料を知ることによって食への興味につながります。買い物や絵本で材料を見るのも良いでしょう。
- どの年齢にも共通してナニーがやっていること
ナニーが「カミカミ」「アムアム」とリズミカルに声に出して伝えます。
「あー、おいしいね!」とお話しします。そうすると一緒にお口に食べものを運び、
お口を動かして食べてくれることがあります。
まとめ
スプーンやフォーク、お箸を上手に使えるようになることは、食事をきれいに食べるうえでとても大切です。とはいえ、焦ってやらせようとすると親子ともストレスがたまります。まずは子どもが「食事が楽しい」「食べることが好き」と感じることが大切です。
手づかみ食べも、スプーン、フォーク食べ、お箸の練習も、子どもが達成感を味わえるように、最初はお皿に少しずつ盛って「できた!」の喜びをたくさん経験させてあげましょう。子どもが上手にできたら、たくさん褒めてあげてください。自分の力で楽しく食べられる土台を作ってあげることは、その後の偏食予防にもつながります。
せっかく作った料理を食べてくれないと、がっかりしてしまいますが、ほんの少しやり方を変えるだけで食が進むお子様は多いです。ナニーがお食事をさしあげると、いつも食が細いお子様も完食されることにお母様は驚かれます。
是非参考にして、ストレスなく幼児食を進めてみてください。

この記事を書いた人
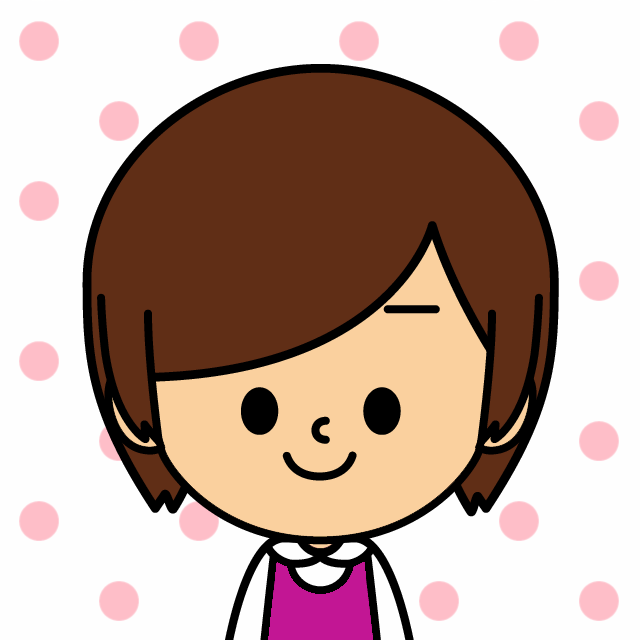
- ハタノケイコ
- 大学にて幼児教育を学び幼稚園教諭ニ種取得。 卒業後は大手百貨店に就職し接客について学ぶ。 児童館での読み聞かせボランティアをきっかけに再び保育の仕事へ。 40代でポピンズに入社し様々な保育現場で仕事をしながら保育士資格取得。 10年の経験と自身の子育てから感じた事を記事に書いて発信中。



 前の記事
前の記事 次の記事
次の記事

