子どもの突然の嘔吐…「どうしよう!」
子どもの突然の嘔吐。そんな場面に直面すると、驚きと不安で頭が真っ白になってしまうこともあるでしょう。慌ててしまうのは当然のことです。でも、あらかじめ対処法を知り、準備をしておけば、少しでも落ち着いて対応できるようになります。
この記事では、病児対応を多く経験してきた看護師ナニーの視点から、嘔吐時の具体的な対処法と、いざというときに備えた準備のポイントをお伝えします。
嘔吐時の対応の基本
お子様の安全を最優先に
嘔吐中や直後は、「横向き安静」の姿勢を保ち、吐しゃ物による窒息を防ぎます。汚れた衣服は早めに着替えさせ、肌を清潔に保ちましょう。
吐しゃ物の処理方法
嘔吐物にはウイルスが大量に含まれているため、慎重に処理することが大切です。
準備するもの:
- 手袋
- マスク
- エプロン
- ペーパータオル
- ビニール袋
- 希釈した塩素系漂白剤
嘔吐時の感染防止対策:適切な手順と根拠
嘔吐物の処理は、感染拡大を防ぐために適切な手順を踏むことが重要です。特にノロウイルスなどの感染力が強い病原体が含まれている可能性があるため、慎重な対応が求められます。以下の手順を参考に、安全に処理を行いましょう。
防護具を着用し、自身を守る
まずは、対応する大人が適切な感染防止策を講じることで、二次感染のリスクを減らします。
<身につけるもの>
- 使い捨て手袋(二重推奨、処理後は必ず破棄)
- マスク
- エプロン
- 足カバー(なければビニール袋で代用)
ポイント!
- 時計や指輪は外し、手袋を装着(小さな穴が開いている可能性があるため二重推奨)。
- 髪の長い方は束ねることで、顔や手元に触れるリスクを軽減。
- 足カバーがない場合は、ビニール袋を靴の上から被せ、輪ゴムで固定すると飛沫防止に役立ちます。
吐しゃ物をペーパータオルや新聞紙で拭き取り、密閉処理
吐しゃ物にはウイルスが含まれている可能性があるため、適切な処理を行います。
<処理方法>
- 外側から中心に向かって慎重に拭き取る(広げないように注意)。
- ペーパータオルや新聞紙に包み、ビニール袋に入れて口をしっかり縛る。
- あらかじめビニール袋をかぶせたバケツに入れ、密閉することで、さらなる飛散を防ぐ。
床や周囲を塩素系漂白剤で消毒
嘔吐物を拭き取った後も、床や周囲にはウイルスが残っている可能性があるため、適切な消毒が必要です。
< 消毒方法>
- 吐しゃ物があった場所に新しいペーパータオルを被せる。
- その上から100倍に薄めた塩素系漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)を静かにかける。
100倍希釈の作り方:水の入った500mlのペットボトルにキャップ1杯分(約5ml)の塩素系漂白剤を加える。
- 消毒液を十分に浸透させた後、拭き取る。
ポイント!
塩素系漂白剤をかける際は広げずに、静かにかけることが重要。
- 手袋を着用したまま、しっかり拭き取ることで、残留ウイルスを減らす。
使用した防護具を適切に廃棄
感染拡大を防ぐために、使用した防護具の廃棄も慎重に行います。
<廃棄方法>
- 手袋は必ず捨てる(使い回すと、ウイルスが付着したまま広がるリスクがあるため)。
- 使用した手袋、マスク、エプロンは、中表にして外し、ビニール袋に入れる。
中表にする理由:手袋の外側にはウイルスが付着しているため、そのまま外すと手や衣服に触れる可能性があります。
正しい外し方:片方の手袋をもう片方の手で引き抜き、その手袋を持ったまま、もう片方の手袋の内側に指を入れ、裏返すようにして脱ぐことで、ウイルスが外側に触れないようにできます。
- ビニール袋を二重にすることで、さらなる感染予防に。
- 袋の口をしっかり縛り、密閉して処分する。
最後に、しっかり手洗いをする
処理後は、石鹸を使って流水で30秒以上の手洗いを行い、感染リスクを最小限に抑えます。
<手洗いのポイント>
- 指の間、爪の周り、手首までしっかり洗う。
- ペーパータオルや清潔なタオルで手を拭く。
嘔吐物の処理は、適切な防護・処理・消毒・手洗いを徹底することが重要です。特にノロウイルスは少量でも感染力が高いため、「拡げない」「触れない」「しっかり消毒」を意識して対応しましょう。
事前準備で慌てず対応

突然の嘔吐に備えて、ご家庭に以下のセットを用意しておきましょう。
嘔吐処理セットを用意する
嘔吐処理セット(1回分)
- バケツ
- 使い捨て手袋(2組)
- マスク
- 塩素系漂白剤と水の入った500mlペットボトル1本
- ペーパータオル(1ロール)
- ビニール袋(密閉できるものを大2枚、小1枚)
お子様が嘔吐した時に、「塩素系漂白剤」と「消毒用アルコール」のどちらを使用するか迷うことがあると思います。感染性胃腸炎を引き起こすノロウイルスやロタウイルスには塩素系漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)が有効です。他、風邪のウイルスとして一般的なアデノウイルスなどにも有効ですので普段から、そちらを用意しておくと安心かもしれません。
次亜塩素酸ナトリウムを含む塩素系漂白剤は、ハイター、キッチンハイターやブリーチです。必ず水で薄めて使用しましょう。また、消毒液の作り置きは、効果の面からもできません。使用期限1日を目安に新しいものを用意しましょう。
着替えセット
- 前開きシャツ
- 締め付けの少ないズボン
ボタンのないシャツを着ると、再び吐いたとき、脱ぐタイミングで吐しゃ物が顔や髪の毛に広がってしまいます。できれば前開きボタンのものを推奨します。
その他用意したい物
- 経口補水液(OS-1やアクアライトORSなど)
- 子ども用体温計
家族で役割分担を決めておく
お子様が突然嘔吐したとき、誰がどのように動くかを事前に決めておくとスムーズです。
例:家族の役割分担
| 役割 | 具体的な対応内容 |
| 吐しゃ物処理役(例:パパ) | 嘔吐物の処理、着替え補助、シャワー浴のサポート |
| 補助役(例:ママ) | 処理セットの準備、換気、他の子どものケア、ペットの誤食防止、医師への連絡 |
<対応時のポイント>
- 感染拡大のリスクを最小限にすることが重要
- 家族でシミュレーションを行い、役割を決めておくと安心
- 誰もが冷静に動けるよう、具体的な流れを共有しておく
緊急時の連絡先や持ち物を確認
- かかりつけ医や夜間救急の連絡先を確認
- マイナンバーカードや健康保険証、お薬手帳は、すぐに持ち出せる場所に準備をしておくと安心です。
かかりつけ医は何時まで対応ができるのか、また受付対応時間外の場合、対応可能な夜間救急はどこかを確認しておきましょう。これは、どのような緊急事態においても役に立つので、ぜひ今一度確認をしておきましょう。
看護師ナニーが実践している嘔吐時の対応

最後に、病児対応を多く経験してきた看護師ナニーである筆者が、ナニーとしてお子様のケアに入る際に心がけている点を共有します。
ナニーが感染症オーダーのお世話に入る際の準備
感染症のお子様をケアする場合、ナニー自身が感染しないこと、また他の家庭にウイルスを持ち込まないことが重要です。
※ポピンズのナニーは感染症対応の場合には手当がつき、翌日は別のご家庭のお世話には入らないなどの感染予防策をとっています。
<持参すると良いもの>
- 汚れてもよい衣服(嘔吐物や消毒液が付着してもよい服を用意)
例:ナイロン製やポリエステル素材の服は消毒しやすく、洗濯時も乾きやすい - 綿素材は吸水性が高いため、汚染リスクがある場合は避けるのがベター
- 替えの靴や靴下(汚染された場合の着替え用)
- ビニール袋(汚れた衣服を入れる用)
- 使い捨てのエプロン・手袋・マスク(防護対策のため)
- アルコールスプレーや消毒液(ナニー自身の手や持ち物の消毒用)
ポピンズのナニーは普段からお世話に入る際には髪の長いナニーは束ねる、時計やアクセサリーは外すことを徹底しているため、汚染を防ぐ観点からも望ましいといえるでしょう。
ナニーが帰宅時に気を付けるべきこと
ナニー自身が感染症を持ち帰らないよう、帰宅後の行動をルーティン化すると安心です。
< 帰宅後のポイント>
- 玄関で手洗い・消毒を徹底(持ち込まない意識を持つ)
- 着替えをすぐに行い、衣服は分けて洗濯(汚染リスクのある服は他の衣類と一緒にしない)
- 靴底も消毒(床を介した感染拡大を防ぐため)
- スマホ・バッグ・鍵なども消毒(手指以外の接触感染対策として)
- シャワーを浴びるとより安心(特にノロウイルスの場合は、皮膚に付着したウイルスを洗い流すことが大切)
最後に
突然の嘔吐は心配が尽きないものです。この記事を参考に事前に準備を整え、正しい対応を心がけることで、慌てずにお子様をケアしてあげましょう。
看護師や保育士の資格を活かして働いてみませんか?ポピンズナニーサービスでは、ナニーを募集しています。詳しくはこちらをご覧ください→

この記事を書いた人
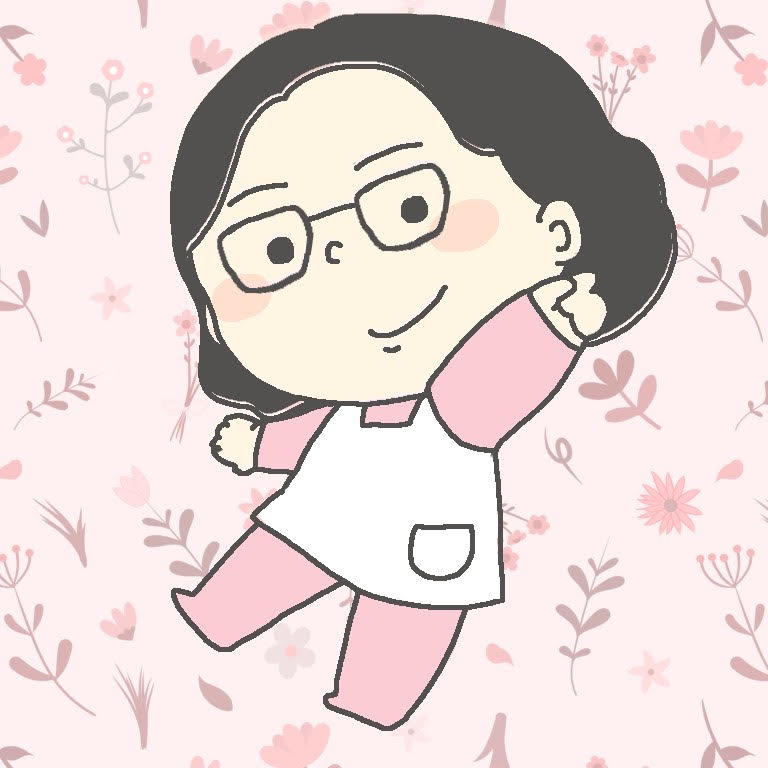
- Naoka
- 看護師、保育士、養護教諭の資格を持つナニーとして活動しています。これまで保育園や小学校、放課後デイサービスなど、さまざまな現場で経験を積んできました。現在ナニーのお仕事をしながら、療育施設にて自閉症スペクトラム症のお子さまたちの支援に取り組んでいます。



 前の記事
前の記事 次の記事
次の記事

