監修:医学博士、東京都市大学人間科学部特任教授
元聖路加国際病院小児科医長 草川 功先生
contents
なぜ子どもはすぐに熱を出すのか
「また呼び出し…」「今月は何日登園できたかな?」
保育園に通い始めたお子さまが、次々と熱を出す姿に戸惑うパパママは少なくありません。SNSでもよく見かける「保育園の洗礼」という言葉は決して大げさではないかもしれません。
しかし、子どもが発熱しやすいのには、ちゃんと理由があります。この記事では、看護師ナニーの視点から「なぜ子どもはすぐ熱を出すのか?」を解説するとともに、パパママの負担を減らすためのヒントをご紹介します。
「すぐ熱を出す」は“当たり前の成長”でもある
子どもは「すぐ熱を出す」と感じるかもしれませんが、それにはちゃんと理由があります。
乳幼児期の発熱は、体がまだ未熟だからだけではなく、免疫を育てていくための大切なプロセスでもあるのです。
では、なぜ子どもは発熱しやすいのでしょうか?
子どもが熱を出しやすい3つの理由
- 感染症との“はじめまして”が多いから
保育園にはたくさんの子どもが集まります。鼻水や咳がある子とも同じ空間で過ごすことで、まだ体験したことのないウイルスや細菌をたくさんもらってきます。 - 免疫システムが未熟だから
大人なら軽く済む感染症でも、子どもには大きな反応として現れることがあります。特に1~2歳ごろまでは、まだ“自分でつくった免疫”が十分ではありません。 - 体温調節がうまくできないから
子どもの身体はまだ体温調節機能が未発達のため、 暑さや寒さ、活動量の変化など、ちょっとした刺激にも体温が大きく変化してしまいます。特に多いのが
・活動的に遊んだあと体温が一時的に上がる
・夏場の外遊びの後や、冬の厚着、暖房によって体に熱がこもる
こうした一時的な体温上昇(うつ熱)は、感染症でなくても「発熱」として現れるため、園から 呼び出しの連絡が来ることも。けれどもこれは、体温調整を覚える途中の子どもにとってはよく あることです。
子どもの発熱=すべて感染症?
子どもの発熱の原因にはいくつかのタイプがあります:
・生理的:運動の後、食事の後、午睡前などにみられるが、その多くは一時的なものです。
・感染症:ウイルスや細菌に感染した際の自然な防御反応。体内の異物をやっつけるために熱が出ます。
・うつ熱(環境性の発熱):体に熱がこもり、外に逃がせないことで体温が上がる状態。
・まれにアレルギー性疾患や悪性腫瘍が原因のこともありますが、こちらは繰り返す、長引く発熱など、経過や症状に特徴があります。
発熱を繰り返すことで、子どもは少しずつ様々なウイルスに対して抗体をつくっていきます。「また熱…」と落ち込む気持ちになることもありますが、それは免疫力を育てている証拠。「すぐ熱を出す=弱い子」ではなく、強くなる準備をしている最中なのです。
そう思うと、少しだけ見え方が変わるかもしれません。
子どもの発熱に関する、よくあるご質問にお答えします

Q1:熱が出たら、すぐ病院に行ったほうがいいですか?
A:必ずしも“すぐ”受診しなくても大丈夫です。
38.5℃前後の発熱でも、元気があって水分がしっかりとれていれば、慌てて受診する必要はありません。まずは自宅で様子を見て大丈夫です。気になることがあれば、落ち着いてかかりつけの小児科に相談してみましょう。ただし、以下のような変化があった場合は、救急病院に電話をし、指示を仰いでください。
・生後3か月未満で38℃以上の熱がある
・熱が3日以上続く
・呼吸が苦しそう、顔色が悪い
・ぐったりして反応が鈍い、嘔吐が続く、けいれんがある など
受診の判断に迷ったときは、#8000(小児救急電話相談)なども活用できます。
Q2:風邪って、どれくらいで治るんですか?
A:実は「1〜2週間かかる」のが普通です。
子どもの風邪は、発熱が数日で下がっても、そのあとに咳や鼻水が長引くことがよくあります。特に咳は2〜3週間残ることもあり、元気そうに見えても完治には時間がかかります。俗に言う「風邪=3日で治る」は、子どもには当てはまりません。
Q3:お薬がなくても大丈夫?解熱剤は使った方がいい?
A:熱の高さより、子どもの“しんどさ”で判断します。
解熱剤(座薬やシロップ)は、「熱を下げる」ためではなく、「楽に過ごす」ために使うものです。遊べる・笑える・ごはんが食べられるようなら、薬を使わずに見守るのもOK。
逆に、眠れない・ぐったりしているようなら、解熱剤で楽にしてあげると回復が早くなることもあります。必ずお医者さんに処方してもらい、指示に従いましょう。
Q4:看病のとき、何を大事にすればいいですか?
A:「食べさせなきゃ」より、「休ませる」ことが大切です。
子どもにとって一番の休養は、家でゆっくり過ごすこと。食事よりも、水分がとれて、よく眠れることを優先してください。
また、熱が下がったあとも体力が回復するまでに数日かかるため、無理にすぐ登園せず、数時間早くお迎えに行く、習い事をお休みするなど、少しゆっくりする時間を持つのもおすすめです。
Q5:よくある“季節の風邪”って、どんなもの?
A:症状や流行の時期を知っておくと、心構えができます。ただし、最近は、疾患、地域によっては季節性が無くなりつつあります。必ず、感染情報センターなどで流行状況を確認しましょう。
代表的なものは以下です。
・RSウイルス(秋〜冬):咳と鼻水、乳児は呼吸が苦しくなることも。乳幼児の肺炎による入院の20〜25%を占めています。
・ヒトメタニューモウイルス(春〜初夏):発熱と咳、鼻水が長引く。特に1歳未満の乳児では症状が強く、気管支炎や肺炎を引き起こす傾向にあります。
・アデノウイルス(通年):高熱、目やに、のどの痛みが特徴(プール熱とも)
・手足口病・ヘルパンギーナ(夏):口の中、手のひら、足底や足背などに水疱性発疹が出ます。典型的な症状が見られずに重症になることもあります
・インフルエンザ(冬):高熱、関節痛、倦怠感など多様な症状
すべてに共通して、「焦らず・観察しながら・必要に応じて受診」が基本です。
発熱のたびに仕事を抜ける… つらいのは「パパママ」も一緒
とはいえ、仕事を休んだり、呼び出しに応じたりする負担はとても大きいもの。
特に共働き家庭では、シフトの調整や代替保育の確保に頭を悩ませることも少なくありません。
そこで、こんな時に頼れる「サポート」をあらかじめ知っておくことが大切です。
病児・病後児保育、ポピンズナニーも“チームの一員”
保育園に通うことは「家庭だけで子育てしない」という第一歩。それと同じように、お子さまが熱を出したときも、ご家庭だけで抱え込まず、外部のサポートを上手に活用していくことが大切です。
たとえば
・自治体の病児、病後児保育施設(※事前登録や予約が必要な場合があります。また、定員人数や状態によってはお預かり不可な場合があります。)
・企業や民間の訪問型の病児サービス、ベビーシッター会社による病児保育
・かかりつけ医のオンライン診療や電話相談
これらのサポートを事前にリサーチ、準備をしておくことで、急な発熱にも慌てず落ち着いて対応できます。特に春は「保育園の洗礼」とも呼ばれるほど病気が多く、夏にかけては手足口病やRSウイルスといった流行も続きます。
“波が来てから”ではなく、“波が来る前”に、ご家庭のスタイルに合った支援を検討しておくのがおすすめです。なかでも、自宅で安心してお子さまを預けられるポピンズナニーサービスは、心強い選択肢のひとつです。ご家族に代わってお子さまのそばで寄り添いながら、安心して回復を待てる環境を整えます。万が一のときにも、会社と連携して迅速かつ冷静に判断を行うため、ご家族にとっても心強い存在となるでしょう。
ポピンズナニーサービスの病児・感染症対応サービスの詳細やご利用の流れについては、以下の記事もぜひご覧ください。
急な発熱も安心 看護師ナニーが解説 ポピンズナニーサービスの「病児・感染症対応」とは?
まとめ「急な発熱、どうしよう」「何が正解かわからない」——その気持ちに寄り添うナニーがいます

お子さまの発熱は、何度経験してもご家族にとって不安なものです。
「熱が出たら冷やすべき?」「食べさせた方がいい?」
そんな疑問や迷いに寄り添い、お子さまのケアとご家族の安心を支えることも私たちナニーの役割の一つです。無理にひとりで抱え込まず、頼れる存在と協力しながら子育ての難しい局面を乗り越えていきましょう。
ポピンズナニーサービスでは、病児ケアについて看護師や救急対応の専門家から直接学べる研修を用意しています。だからこそ、お子様の急な発熱にも落ち着いて対応し、ご家庭をしっかりと支えることができるのです。
発熱は、子どもが育っていく過程のひとつ。
「何度も熱を出して、そのたびに強くなっていくんだな」そう思えるように、ご家庭とナニーがチームとなって、子育てを支えていけたらと願っています。。
働く女性やご家庭をそっと支えるお仕事を、あなたも一緒にしてみませんか?詳しくはこちらをご覧ください→

<参照>
この記事を書いた人
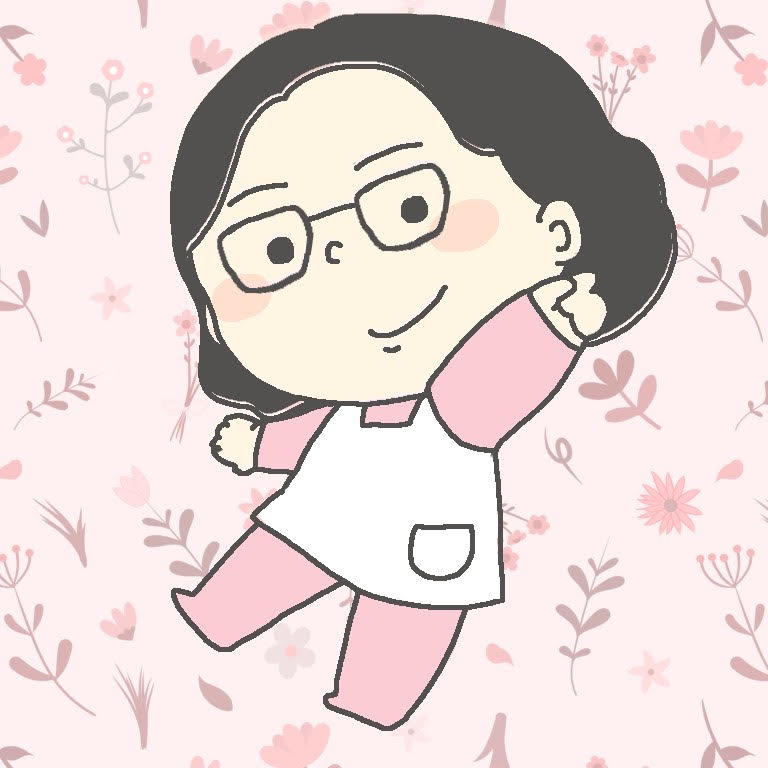
- Naoka
- 看護師、保育士、養護教諭の資格を持つナニーとして活動しています。これまで保育園や小学校、放課後デイサービスなど、さまざまな現場で経験を積んできました。現在ナニーのお仕事をしながら、療育施設にて自閉症スペクトラム症のお子さまたちの支援に取り組んでいます。



 前の記事
前の記事 次の記事
次の記事

