監修:医学博士、東京都市大学人間科学部特任教授
元聖路加国際病院小児科医長 草川 功先生
contents
今こそおさらいしたい熱中症対策
厳しい暑さが続きます。「熱中症警戒アラート」が発令されてもどう対応すればいいものか、戸惑うことも多いことでしょう。本記事では、看護師資格を持つナニーの立場から熱中症のメカニズム、予防法、そして万が一の際の対応策について、エピソードを交えてご説明します。
熱中症エピソード:暑さと闘ったある日
ある日、保育園から帰宅したばかりの3歳のお子さまをお母さまからお預かりしました。いつもは元気いっぱいでよくお話してくれるのですが、その日は少し様子が違い、言葉数が少なく、眉間にしわを寄せてどこかつらそうな表情をされていました。
最初は「少し疲れているのかな?」と思いましたが、お洋服は汗でびっしょり。ご自宅に着くなりリビングの床に横になってしまったため、念のため体温を測ると37.4℃、脈拍もやや早めでした。風邪の可能性も考えましたが、暑さが厳しい日だったことから、まずは軽い熱中症を疑いました。
涼しい服に着替えてもらい、冷たい清涼飲料水を少しずつ飲んでいただきました。さらに氷枕やアイスパックで首や脇を冷やしながらしばらく安静にして様子を観察しました。吐き気やお腹の痛みはなく、水分もしっかりと摂れていたので大きな心配はないと判断し、引き続き見守りました。
しばらくすると徐々に表情が明るくなり、いつもの笑顔を見せてくれるようになりました。その後、晩ごはんも完食され、飲み物もごくごく飲み、トイレも普段どおり済まされたので安心しました。
その日は夕方になっても気温が高く、少し歩いただけで汗が止まらないほどの暑さでした。帰宅時にはベビーカーに取りつけたモバイルファンやハンディファンで風を浴びておられましたが、外気自体が熱風であまり効果を発揮していなかったのかもしれません。
この経験を通して、暑さ対策の大切さを改めて感じるとともに、健康観察の重要性を再確認しました。暑さをしのぐためのグッズも、正しく使ってこそ役立つのだと実感した出来事でした。
熱中症とは

熱中症は、高温多湿な環境に長時間いることで、体温調整機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。屋外だけでなく屋内で何もしていないときでも発症し、救急搬送されたり、場合によっては死亡したりすることもあります。
引用:厚生労働省『熱中症予防のための情報・資料サイト』
高温や多湿の環境下で体温が異常に上昇し、体内の水分と塩分のバランスが崩れることで発症する症状の総称です。
熱中症のメカニズム
人間は汗をかくこと(気化熱)や、体の表面から空気中に熱を逃すこと(熱放散)によって体温調整をしています。暑くなった場合は汗をかいて体温を下げようとします。しかし、気温や湿度が高い中で激しい運動をすると、熱をうまく外に逃すことができなくなり、熱が体の中にこもってしまいます。さらに、炎天下で大量の汗をかくと体の中の水分と塩分が失われ、血液の流れが悪くなり、体の表面から熱を逃すことができなくなります。これにより、脳や他の臓器に十分な血液が行き渡らず、こむら返りが起きたり、意識レベルが落ちたり、体内の臓器に深刻なダメージを与えることがあります。
なぜ子どもは大人より熱中症リスクが高いのか?
子どもは大人よりも熱中症になりやすいと言われています。その理由は
体温調節機能の未熟さ
子どもは体温調節機能が未熟です。汗をかく機能がまだ発達していないため、暑さを感じてから汗をかくまでに時間がかかってしまいます。結果として、体に熱がこもりやすくなり、体温が上昇してしまいます。
体表面積と体重の比率
子どもは体重に対して体表面積が大きいため、気温や湿度など周囲の環境の影響を受けやすいのです。これにより、体内の熱を効果的に逃すことが難しく、反対に夏季の炎天下や照り返しなどの周りの熱を吸収してしまう恐れもあります。そのため、体温が急激に上昇することがあります。
高い代謝率
子どもは基礎代謝率が高く、エネルギー消費が盛んです。そのため、体内で生成される熱が多く、体温が上がりやすくなります。活発に動き回ることが多い子どもはさらに熱中症のリスクが高まります。
自覚と表現の未熟さ
子どもは自分の体調の変化や熱中症の初期症状を言葉で訴えられないことが多いのです。そのため、大人が気づくのが遅れ、重症化しやすくなります。
水分補給の困難さ
子どもは遊びに夢中になると水分補給を忘れがちです。また、自分で適切なタイミングで水分を摂ることが難しい場合もあります。これにより、脱水状態になりやすく、熱中症のリスクが高まります。
環境の影響
子どもは屋外で過ごす時間が長く、直射日光を浴びやすい環境にいることが多いです。特に夏休みは習い事やレジャーを楽しむお子様も多いでしょう。これらの活動により体温が上がりやすく、熱中症のリスクが高くなります。
以上の理由から、子どもは大人よりも熱中症になりやすいと言われています。大人が常に注意を払い、適切な予防と対応をすることが重要です。
熱中症の予防法:お子さまを守るためにできること

1.こまめな水分補給
喉の渇きを感じる前に定期的に水分を摂ることが大事です。特に外遊びに集中していると水分摂取を忘れてしまいがちです。時間を決めるなどして水分摂取を促しましょう。飲み物は水だけでなく、スポーツドリンクや経口補水液など塩分を含む飲み物を摂取すると効果的です。ジュースをあげるのも、水分摂取量を増やすために時折有効です。その場合は、塩分の入っている飲み物も交互に与えるのが良いでしょう。
2.適切な衣類の選択
熱が体にこもらないような通気性の良い素材、例えば綿やリネンの洋服がおすすめです。また、直射日光を避けるために帽子や日傘を利用しましょう。
日焼けの予防も大事です。日光が肌に直接当たらないように長袖を着用しているお子様も多いですが、その場合は、ゆとりのある洋服を着せてあげましょう。そうすることで、体に熱がこもるのを防げます。
3.適切な環境の確保
特に昼間の暑い時間帯は、冷房の効いた室内や涼しい日陰で過ごすことを心がけましょう。外遊びには朝の早い時間帯がおすすめです。外出をする際はクールタオルや冷感スプレーを利用するのもよいでしょう。熱中症の予防のために一番手っ取り早いのは、環境を変えることです。外出先で少し疲れている様子を見せていたら、すぐに涼しい環境に移動しましょう。
以下のような緊急避難的に利用できる公共施設やお店の場所を確認しておくとよいでしょう。
【公共施設】
- 図書館
- 公民館、地域センター
- 市役所や区役所のロビーや子育て支援スペース
【子育て・福祉関連】
- 子育て支援センター
- 児童館
【商業施設】
- ショッピングモールや百貨店の休憩スペース
- スーパーやドラッグストア
- コンビニエンスストア
また、多くの自治体では「クーリングシェルター(暑さ対策のための避難所)」が指定されています。市区町村のホームページで公開されている場合が多いので、いざという時のために一度チェックしておくと安心です。
4.暑さに負けない体づくり
水分不足や疲労があると熱中症になりやすいものです。お子さまが十分に休息が取れるよう生活リズムを整えてあげましょう。夏休みに入るとついつい夜更かしをしてしまい、わずかな睡眠時間で活動を開始してしまうことがあります。そのため、毎日のルーティンを決め、可能な限り就寝時間と起床時間にばらつきが出ないよう工夫しましょう。また、暑い日は食欲が落ちてしまいがちですが、しっかりと栄養バランスの取れた食事をとりましょう。
もし熱中症を疑った場合は
特に軽度・中等度の熱中症では「めまい」「強い疲労感」「頭痛」「吐き気」など、風邪と判断しづらい症状が出るので、医療機関の受診を迷われる方が多いと思います。また月齢の低いお子さまでは、具体的な症状を大人に伝えることが難しいものです。
その中で大事なことは観察です。「あれ、いつもと違うかもしれない?」「元気がなさそう」といった毎日の様子と少しでも違った様子が見られる場合の対策としては以下が挙げられます。
体温と汗の状態を確認
頻繁に子どもの額や背中に触れて、体温が急に上がっているか、大量の汗をかいていないかを確認しましょう。顔が赤く、ひどく汗をかいている場合には深部体温が上昇している証拠です。
表情と態度の変化
いつもと違う疲れた表情、無気力、ぐったりとしていないか観察しましょう。
行動の変化
いつもと違い、好きなおもちゃに手を伸ばさない、動きが鈍い、集中力がない、食事が進まないなどの変化を観察しましょう。
緊急時の対応

まずは涼しい場所へ移動
その場にクーラーの効いた室内や車内があれば、すぐに移動して休ませます。公園やキャンプ場など屋外で難しい場合は、木陰や風通しの良い場所を探し、地面の熱が直接伝わらないようにレジャーシートやバッグを敷くなど工夫しましょう。
近くに図書館やショッピングモール、コンビニなど冷房が効いている施設があれば、避難先として活用するのもおすすめです。
体を冷やす
頭には氷枕を置き、首、脇の下、足の付け根にアイスパックや濡れタオルを当てて体を冷やします。うちわや携帯ファンで風を送るのも有効です。
水を皮膚にかけたり濡れタオルで体を拭いて風を当てると、気化熱で効率的に体温が下がります。
水分補給
飲めそうであれば、冷たい飲み物を少しずつゆっくり飲ませます。いっきに飲むと吐いてしまう場合があるので注意しましょう。
改善しなければ迷わず医療機関へ
ぐったりしている、意識がもうろうとしている、呼びかけに反応が鈍い場合はすぐに119番へ連絡し、救急車を呼んでください。
まとめ
暑さからお子さまを守るための熱中症予防と対応策についてご紹介しました。お子さまの命と健康を守るために、日頃から適度に外遊びをし、暑さに慣れておくとともに、規則正しい生活をキープすることが大切です。しっかりと対策を講じて、元気に暑さを乗り切りましょう!
現在、教育シッター「ナニー」を募集しています。詳しくはこちらをご覧ください→
参考:日本気象協会推進「熱中症ゼロへ」プロジェクト公式サイト

この記事を書いた人
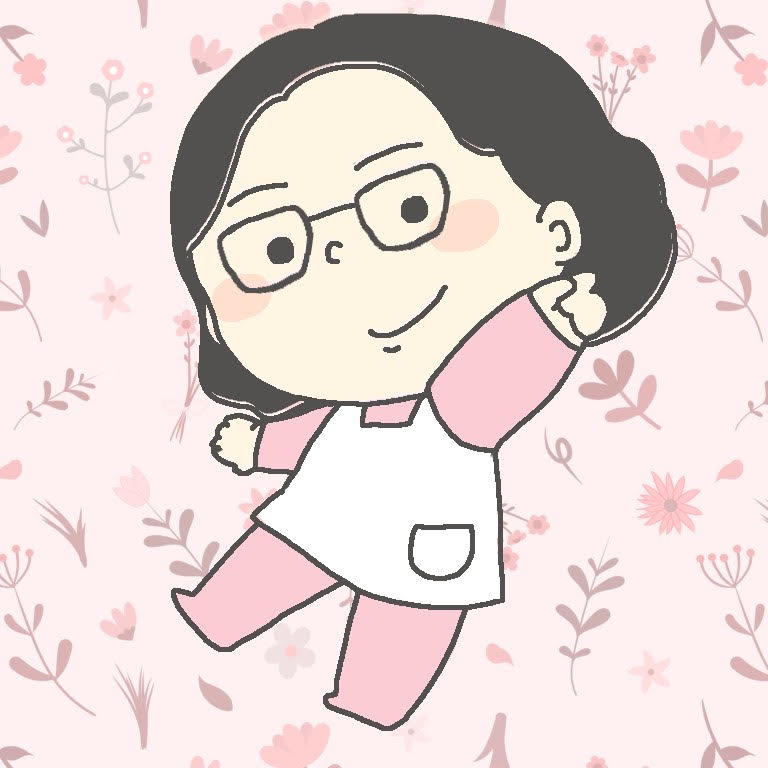
- Naoka
- 看護師、保育士、養護教諭の資格を持つナニーとして活動しています。これまで保育園や小学校、放課後デイサービスなど、さまざまな現場で経験を積んできました。現在ナニーのお仕事をしながら、療育施設にて自閉症スペクトラム症のお子さまたちの支援に取り組んでいます。



 前の記事
前の記事 次の記事
次の記事

