災害はいつどこで起こるかわかりません。特に小さなお子さまがいるご家庭では、いざという時にどのように安全を確保するか、日頃からしっかりと考えておくことが大切です。この記事では、看護師ナニーとしての経験を基に、家庭でできる具体的な防災対策をご紹介します。万が一の時にも落ち着いて行動できるように備えておきましょう。
contents
備蓄と非常用持ち出しバッグ:何をどの程度用意すれば良いのか
災害時の備えの基本は、食料や水、必要な物資を一定量確保しておくことです。ライフラインが途絶える可能性も考慮し、最低でも3日分、可能であれば1週間程度の備蓄が推奨されます。
なぜ備蓄が重要なのか?
大規模災害が発生すると、電気・ガス・水道などのライフラインが停止することが予想されます。行政の支援がすぐに届かない場合、自力で生活を維持するための物資が必要です。食料や水はもちろん、トイレや簡単な調理器具なども重要です。

<具体的な備蓄品リスト>
非常食: レトルトご飯、アルファ米、缶詰、インスタント食品
飲料水: 1人1日3リットルを目安に人数分
その他: トイレットペーパー、ティッシュペーパー、簡易トイレ、カセットコンロ、マッチ、ろうそく
非常用持ち出しバッグ
避難の際に持ち出す非常用バッグも準備しておきましょう。これは家族構成や個別のニーズに合わせて用意する必要があります。
◉食品・飲料: 水、インスタント食品、チョコレートや羊羹などエネルギー源になるもの
◉衣類・防寒具: 下着や衣類、レインウェア、保温シート
◉生活用品: 洗面用具、タオル、懐中電灯、携帯ラジオ
◉その他: 紐なしの靴、軍手、使い捨てカイロ、ブランケット、ペンとノート
お子さま用の非常持ち出し袋
特にお子さま用の非常持ち出し袋には、次のようなものを準備しておくと良いでしょう。
◉おむつ・ミルク: 必要な量を十分に準備し、液体ミルクを活用するのもおすすめです。
◉食料: 離乳食やお子さまの好きなお菓子
◉安心できるアイテム: 絵本やお気に入りのおもちゃなど、心理的に落ち着けるもの
また、アレルギーがある場合は、その情報をメモに記載し、バッグに入れておくと安心です。
医療用具や救急セットの確認
災害時には怪我や体調不良が発生する可能性があるため、家庭用の救急セットを用意しておきましょう。
消毒液やガーゼ、包帯
お子さま用体温計や絆創膏、小児用の解熱剤
※常備薬がある場合は、必ず持ち出しバッグに入れておき、災害時でも服用を続けられるように準備します。
防災マニュアルの作成と家族での共有
災害時に冷静に行動できるよう、家族全員で防災マニュアルを作成し、事前に確認しておくことが重要です。特に避難経路や連絡手段については事前に話し合っておきましょう。
避難経路の確認と練習
家族で避難場所までのルートを確認し、実際に避難の練習をしておくことが大切です。お子さまには分かりやすい言葉で説明し、手をつないで避難する練習も取り入れましょう。
緊急連絡先の確認
家族間での連絡方法や連絡先も事前に確認しておくべきです。災害時には電話がつながりにくくなることがあるため、集合場所や合流方法を決めておくと安心です。インターネットを活用した伝言サービスの利用方法も確認しておくと良いでしょう。
お子さまをナニーやシッターへ預けるときの災害対策
ナニーやシッターにお子さまを預けている間に災害が発生することも想定しておく必要があります。預ける前に、避難経路や避難場所、緊急時の連絡手段を確認しておきましょう。
避難経路と避難場所の共有
ナニーやシッターと共に、どこに避難するのか、どのように連絡を取るのかを話し合っておきます。ご両親が合流できる場所やタイミングも明確にしておくと良いです。
連絡手段の確認
携帯電話が使えない状況に備え、災害伝言ダイヤルや他の伝言サービスの使い方も確認し、ナニーやシッターと共有しておくことも有効です。
看護師としての視点:災害時の健康管理
災害時は避難所生活などが続くことで、衛生状態の悪化や栄養不足など、体調を崩しやすい状況が生じます。特にお子さまの健康管理には注意が必要です。
衛生管理の徹底
手洗いや消毒は感染症予防に不可欠です。避難所では水の使用が制限されることもあるため、アルコール消毒液を携帯し、必要に応じて使用しましょう。マスクも用意しておくと安心です。
栄養と水分補給
避難所生活では食事や水分補給が不十分になることがあるため、お子さまの食事や水分補給には特に気をつける必要があります。できるだけ限り栄養バランスを考えた食事を心掛け、定期的に水分補給をさせましょう。子どもは自分で体調を管理することが難しいため、大人が適切にサポートしてあげることが大切です。
災害時のメンタルケア
災害はお子さまにとって非常にストレスフルな出来事です。不安や恐怖を感じるお子さまに対して、安心感を与えるためのケアが必要です。
心理的なサポート
避難所生活では慣れない環境や周囲の状況に圧倒されることがあります。できるだけ家族や信頼できる大人と一緒に過ごし、安心できる場所を確保しましょう。また、お気に入りのぬいぐるみやブランケットなど、安心感を与えるアイテムを持参すると、心理的な安定につながります。
話を聞くことの大切さ
お子さまが感じている不安や疑問に耳を傾け、無理に恐怖を押し殺させないようにしましょう。優しく寄り添い、「大丈夫だよ」と安心させる言葉かけが大切です。また、災害時のニュースや情報は、必要なものだけをお子さまに伝えるようにし、過度な情報を与えないように配慮しましょう。
防災に関する情報の定期的な更新
防災対策は一度準備したら終わりではありません。新しい技術や情報が出てくることもあるため、定期的に情報を更新し、家族全員で再確認する習慣を持つことが大切です。特にお子さまの成長に合わせて必要な物や対策が変わることもあるため、定期的に備蓄品や避難計画の見直しを行いましょう。
災害時にお子さまを守るための防災対策は、日頃からの準備と意識が重要です。家族全員が防災に対する理解を深め、いざという時にも落ち着いて行動できるよう、しっかりと備えておきましょう。災害時には、予期しない出来事が多く発生しますが、事前にできる限りの備えを行うことで、いざという時の対応力を大幅に向上させることができます。
地域社会との連携
災害時は、家族だけでなく、地域社会との協力が不可欠です。特に小さなお子さまがいる家庭では、近隣の方々や地域の防災リーダーと日頃からコミュニケーションを取っておくことが、緊急時の大きな助けとなります。
地域の防災訓練への参加
地域で定期的に行われる防災訓練には、積極的に参加することをおすすめします。実際に避難の流れや緊急時の対応を体験することで、自分たちの準備の状況を確認でき、地域の避難所や避難経路を知る良い機会となります。特にお子さまと一緒に参加することで、子どもも避難の重要性や流れを理解しやすくなります。
周囲との助け合い
災害時は、助け合いの精神がとても重要です。自分たちが助けられる側になることもあれば、逆に他の家族を助ける立場になることもあります。近所の方々と日頃から顔見知りになり、いざという時に頼りにできる関係を築いておきましょう。
まとめ:日々の備えが大切

「備えあれば憂いなし」という言葉がありますが、お子様を守るための備えは、いざという時に大きな力を発揮します。どうか、この機会にご家庭でも防災対策を見直し、少しでも安心して日々を過ごせるようにしてみてください。

この記事を書いた人
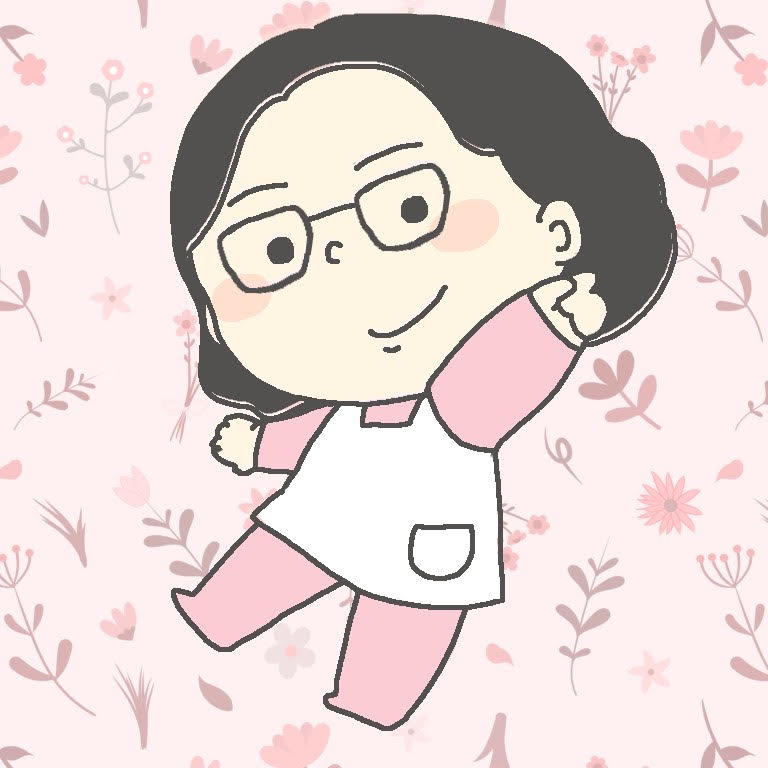
- Naoka
- 看護師、保育士、養護教諭の資格を持つナニーとして活動しています。これまで保育園や小学校、放課後デイサービスなど、さまざまな現場で経験を積んできました。現在ナニーのお仕事をしながら、療育施設にて自閉症スペクトラム症のお子さまたちの支援に取り組んでいます。



 前の記事
前の記事 次の記事
次の記事

