トイレトレーニングの開始時期は悩みますよね。
ナニーとしてお伺いした時に、お母様からよくご相談されます。始めるサインを見逃さずスムーズに進めていくには、どうしたらよいのでしょうか。子どもによって、スタートの時期にはバラつきがありますので、様子を見ながら適切なタイミングで始めるようにしましょう。
トイレトレーニングに必要な心身の発達が備わる時期
1歳7ヶ月〜8ヶ月以降に、簡単な問いかけに「うん」、「イヤ」といった言葉で応じることができるようになります。また、運動能力もその頃から次第に発達してきます。
発達には個人差がありますので、お子さんの心や身体が「トイレに行く」ための準備が出来ているのか、しっかり観察する必要があります。大切なのは、一人ひとりに合わせて開始時期を決めてあげることです。
トイレトレーニングを始める時期の具体的な目安
1歳7ヶ月以降にトイレトレーニングに必要な心身の発達が備わりますが、実際にスタートさせた時期は2歳から2歳6ヶ月が多いようです。子どもによって1歳代から3歳代の間でバラつきがあります。
以下のサインが出てきたらスタートのチャンスです。
- 1.トイレまで自分で歩いて行ける
- 2.便座やおまるにしっかりした姿勢で座っていられる
- 3.大人の問いかけに「うん」「イヤ」など簡単な言葉で答えられる
- 4.おしっこの間隔が2時間以上空く
- 5.「抱っこして」「ちょうだい」など自分の気持ちを伝えることができる
- 6.大人のマネができる
このうち1〜4はできる方がトイレトレーニングがスムーズに進むでしょう。
幼稚園の入園前までにトイレトレーニングを終わらせねば!と焦ってしまうかもしれません。園からは「なるべく入園前にトイレに行けるように」と言われるかもしれませんが,
3年保育に入る、早生まれのお子さんはまだ3歳になったばかりです。どうしても無理な場合は、幼稚園と協力しながらトイレトレーニングを進めることも可能です。集団生活の中で、まわりのお友達がトイレに行くのを目にすると、「自分もできるようになりたい」という気持ちがわいてきます。入園後は案外スムーズにトイレトレーニングが進む場合が多いのです。トイレトレーニングは、一進一退の場合も多いので、おうちの方も精神的に余裕をもって子どものペースに寄り添いましょう。
トイレトレーニングの進め方
ステップ1 絵本を見て「トイレ」を知ってもらおう!
普段の生活の中で「ご飯を食べる」「着替えをする」ことと違って「排泄する」ということを、お子さんは目にすることはありません。お子さんが知らない「トイレに行く」という行為に、まずは興味をもってもらうことからトイレトレーニングはスタートです。普段の生活の中でトイレトレーニングに関する絵本の読み聞かせを取り入れて、トイレを知ってもらいましょう。

ステップ2 トイレに行って、便座に座ってみよう!
お子さんがトイレに興味をもつようになったらチャンス!トイレに誘ってみましょう。
トイレは怖くない!と思ってもらうためにトイレ内は明るく清潔にしておくことが大切です。お子さんが嫌がらなければ、そのまま補助便座に座ってもらいましょう。ここではトイレに慣れてもらうことが目的なので、無理に座らせたりする必要はありません。お子さんの様子を見ながら進めていくことが大切です。
もし、トイレに入るのを嫌がるようなら、もう一度ステップ1に戻ります。
ステップ3 生活リズムに合わせて誘ってみよう!1日に何度かトイレに行ければあと少し!
お子さんがトイレに行くことに抵抗がないようなら
- 1.食事の前後
- 2.出掛ける前
- 3.起床直後
- 4.就寝前
などタイミングを見て、トイレに誘ってみましょう。そしてトイレで、おしっこやうんちが出たら、「おしっこ出たね!」「うんち出たね!」とお子さんと一緒に確認してからオーバーリアクションで、褒めてあげましょう。
ステップ4 自分から「トイレに行く!」と言えるように!
最初は、おうちの方やナニーが生活の区切りなどで数時間おきに、トイレに誘って座る習慣をつけてみましょう。
トイレに行き、成功した時は、たくさん褒めてあげましょう!成功体験を重ねることによって、お子さんは自分から「トイレに行く」と言えるようになってきます。
ステップ5 いよいよパンツ(トレーニングパンツ)を履いてみる!
トイレでの成功率が増えてきたら、まずは昼間にパンツ(トレーニングパンツ)を履かせてみましょう。オムツと違ってパンツは「自分がおしっこをした」という感覚がわかり、パンツの中ですると、「濡れてしまって気持ち悪い」と感じるのがねらいです。そこから「次はトイレに行って、おしっこしたい」「おしっこしたくなったからトイレに行こう」という気持ちが芽生えたらトイレトレーニングは、ほぼ成功です!もちろん何度も失敗を繰り返すことになりますがここで大切なのは、おうちの方は決して叱らず、おおらかな気持ちで接してあげてください。
ステップ6 外出時と夜も挑戦してみよう!
いよいよ最終ステップです。
外出時は、まずは場所選びからです。失敗しても大丈夫な場所(公園、児童館など)を選びます。子ども用のトイレがあるのか事前に調べておきましょう。また、脱ぎ着しやすい服装を選び、着替えも忘れずに。
夜におしっこが出なくなるには、おしっこを溜めるための身体の発達が必要です。
- 膀胱が大きくなる
- 熟睡時に分泌される「抗利尿ホルモン」が働く
昼間はトイレに行くことができても、夜おねしょをしてしまう場合は、夜だけオムツを
使用しましょう。朝、オムツが濡れていない日が続けば、パンツに移行しても大丈夫なサインです。
ナニーが教えるトイレのコツ
①トイレは怖いところではない!と思ってもらう
トイレに行くのを嫌がるお子さんはとても多いです。
どうして嫌なのかナニーが聞いてみると「怖い!」と言います。更に何が怖いのか聞いてみると「ドアを閉めるのがイヤ」、「トイレの流す音が怖い」と教えてくれました。どうやら密室でトイレの流れと共に自分も流されそうで恐怖を感じるようです!
慣れない場所に、わざわざ移動して水が流れる上に座るのは、お子さんにとってドキドキ体験なのです。そういう時は無理にトイレの中に入らず、トイレの前でオムツ替えから始めましょう。
おしっこやうんちをしたオムツが、さっぱりするのはリビングでなくてトイレという意識づけは進められます。
トイレの電球を明るくしたり、ステップ台を用意したり、好きなキャラクターのポスターやシールを利用してトイレは楽しいところと思うように環境を整えましょう。
②うまく進まない時は、一旦ストップしてみる!
もしかしたらスタートが、お子さんにとって少し早かった可能性もあります。思い切って中止して、時期を変えて再チャレンジすると、あっという間に成功したということも、よくあるのです。
③ご褒美シールを活用する
ちょっとしたご褒美が、やる気に繋がります。上手にできたらシールを貼るためのシール台紙をトイレに用意します。
④周りと比較せず、お子さんのペースに合わせる
周りのお友達が、どんどんオムツが外れていくと、おうちの方は気持ちが焦ってしまいます。しかし一番大切なことは、お子さんのペースです。お子さんが出来る時を待つことが大事です。
⑤絶対に叱らないこと
一進一退のトイレトレーニング。失敗するのは当たり前なのです!お子さんの「自分でがんばろう」という気持ちを信じて応援しましょう!
劣等感や恐怖心を与えないよう気をつけましょう。
トイレトレーニングは、お子さんの大きな成長に繋がるのです。
トイレトレーニングは「自分でできるようになる」ことで
自己肯定感を高めるとても大切なステップです。
自己肯定感は、将来、自分の行動や感情をコントロールするための心の土台となり、大きな自信にもなります。
ナニーも精一杯のお手伝いをさせて頂きますので、お子さんとトイレの良好な関係を築きましょう!

この記事を書いた人
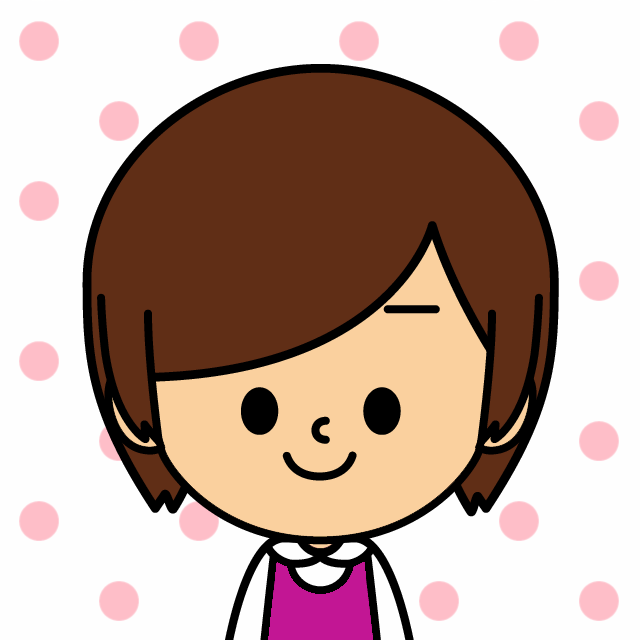
- ハタノケイコ
- 大学にて幼児教育を学び幼稚園教諭ニ種取得。 卒業後は大手百貨店に就職し接客について学ぶ。 児童館での読み聞かせボランティアをきっかけに再び保育の仕事へ。 40代でポピンズに入社し様々な保育現場で仕事をしながら保育士資格取得。 10年の経験と自身の子育てから感じた事を記事に書いて発信中。



 前の記事
前の記事 次の記事
次の記事

